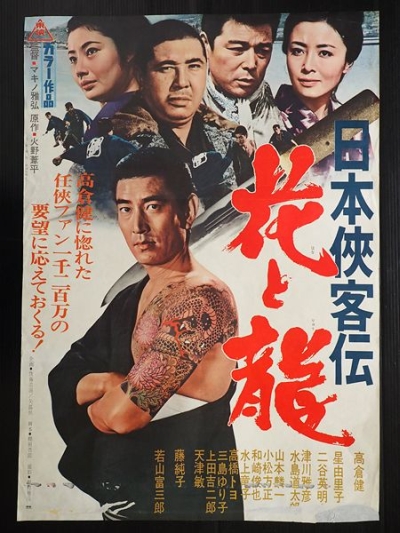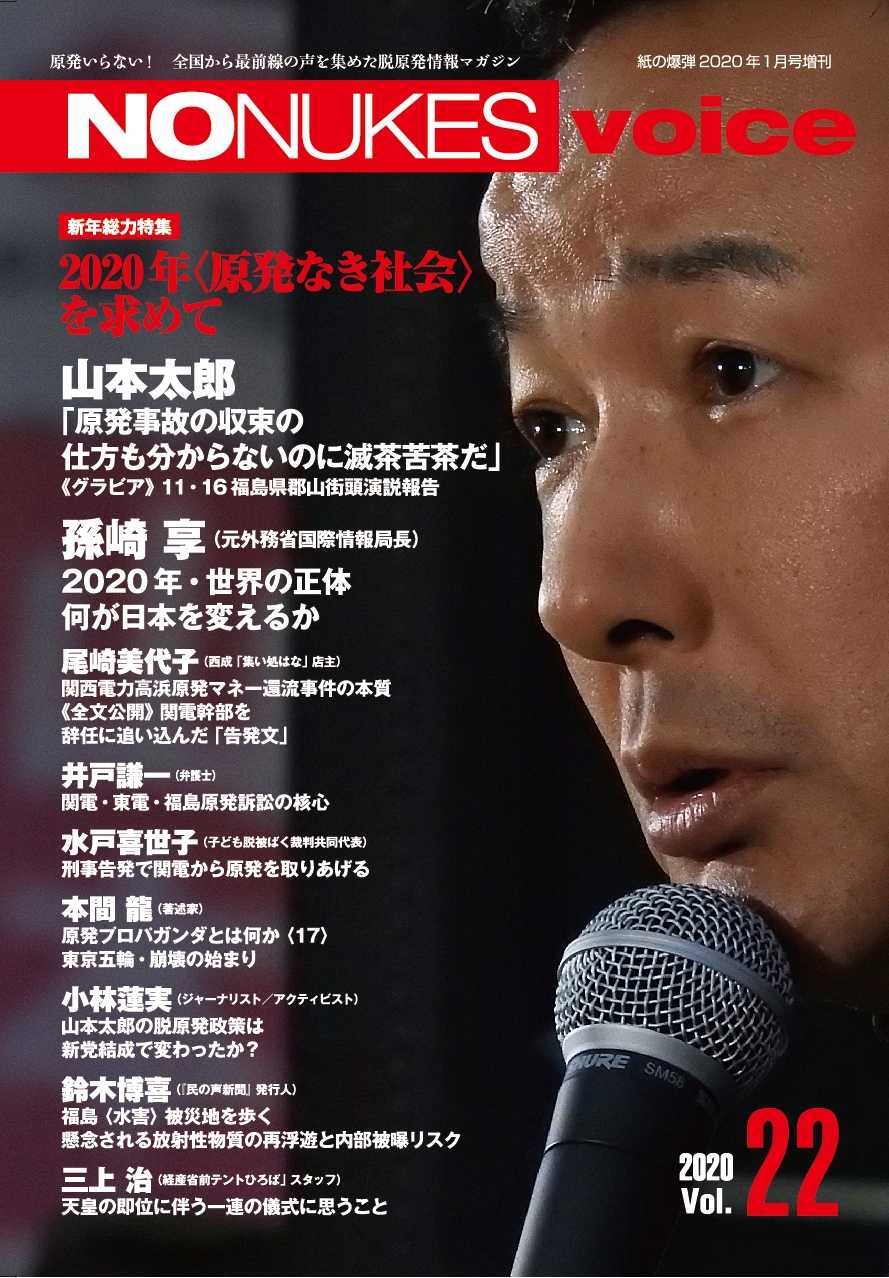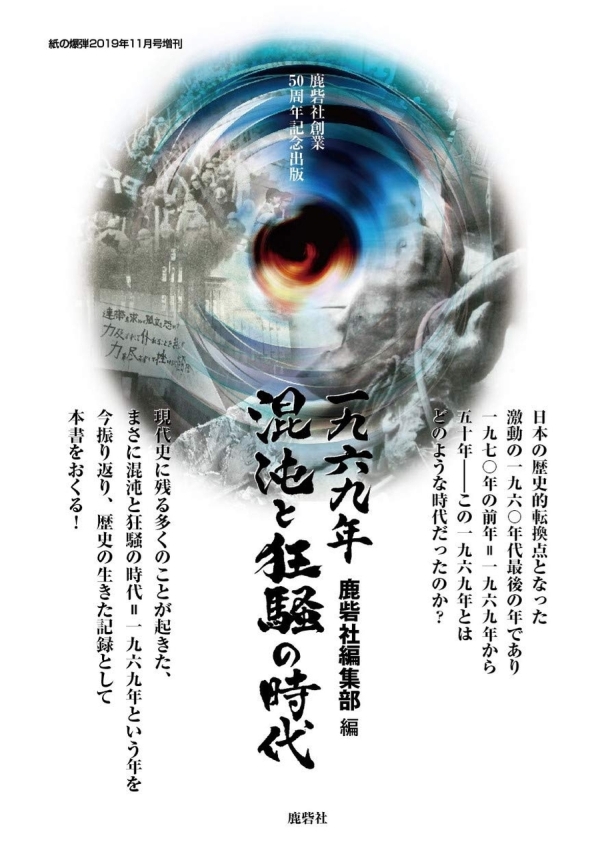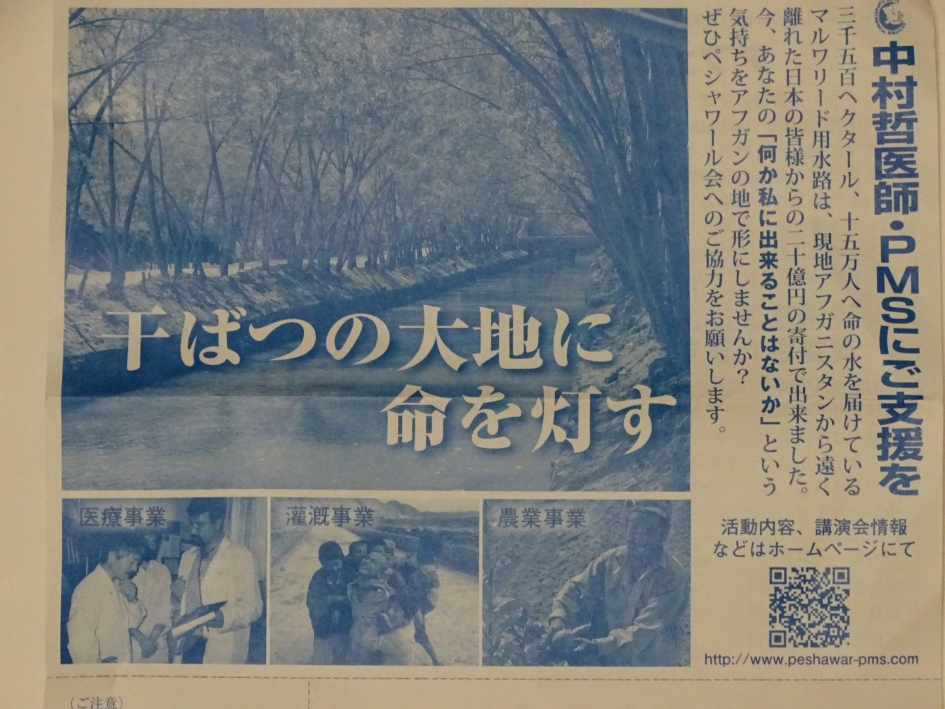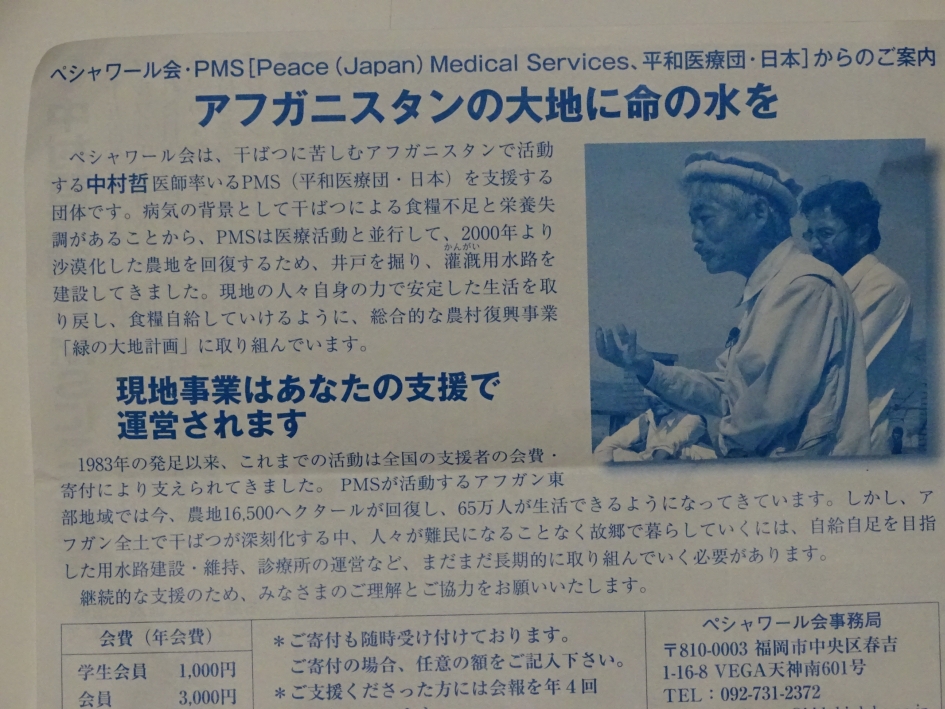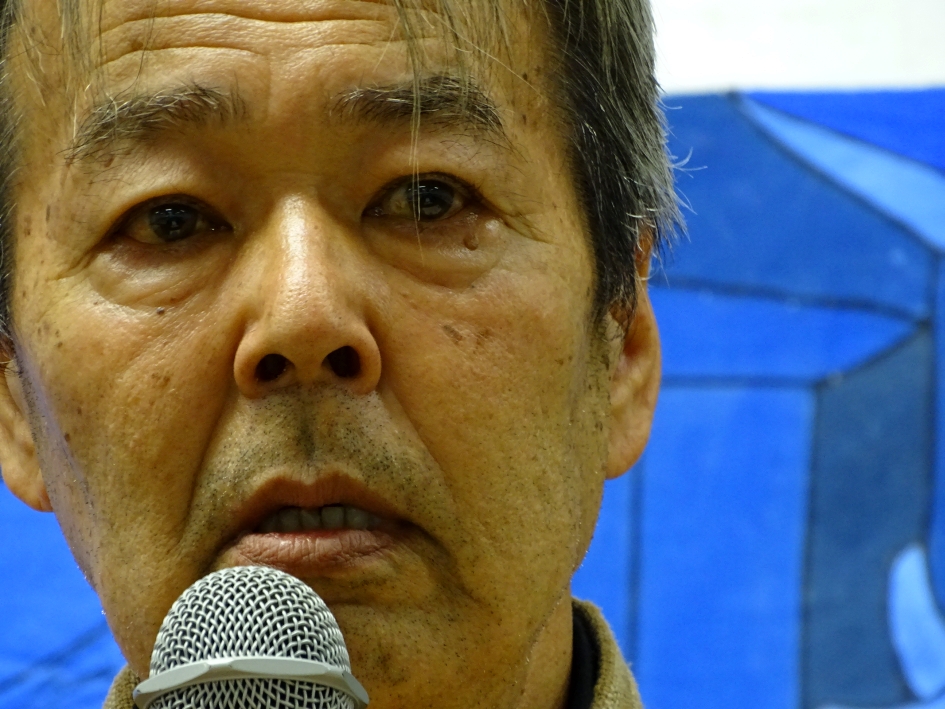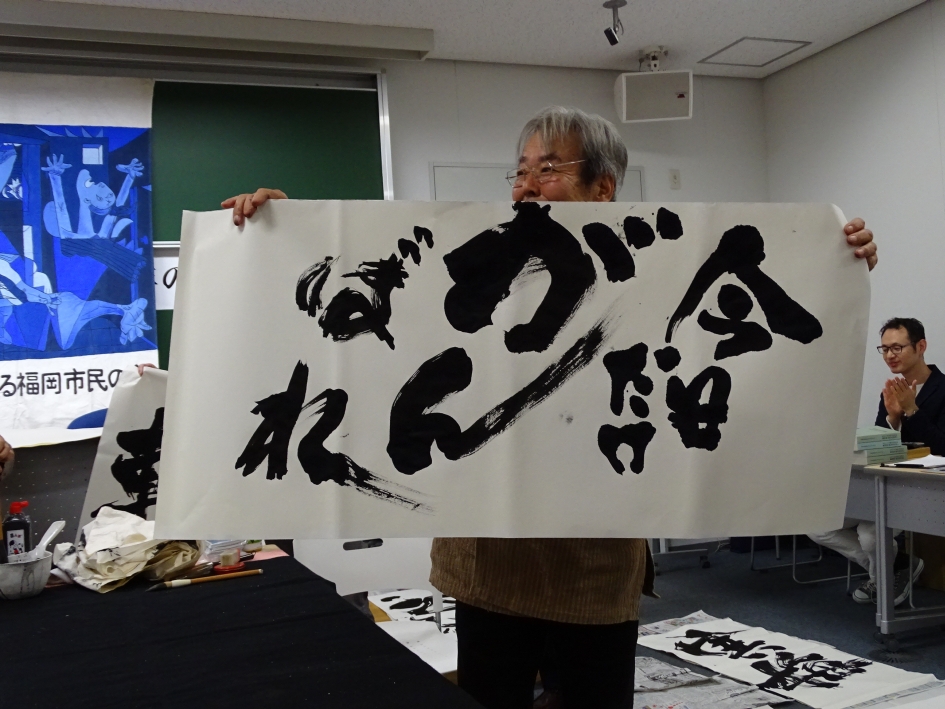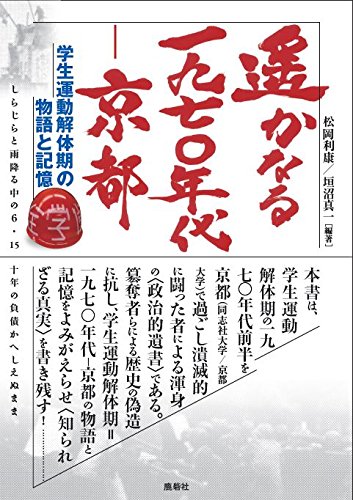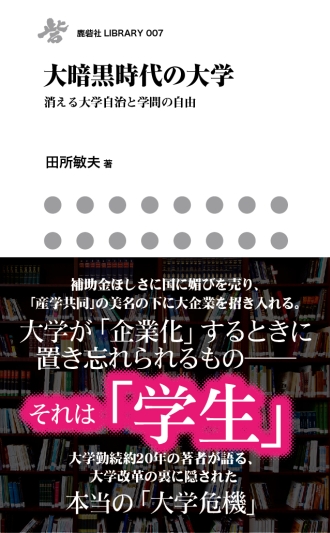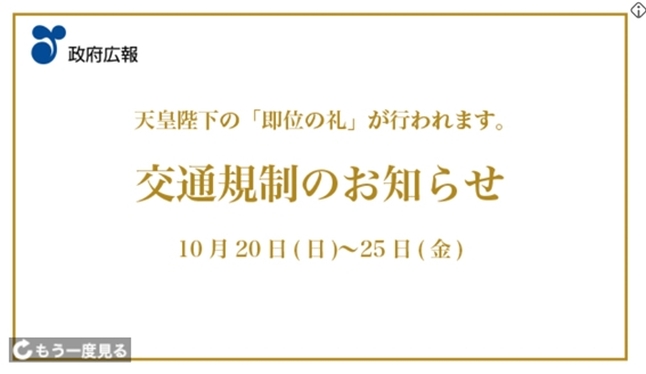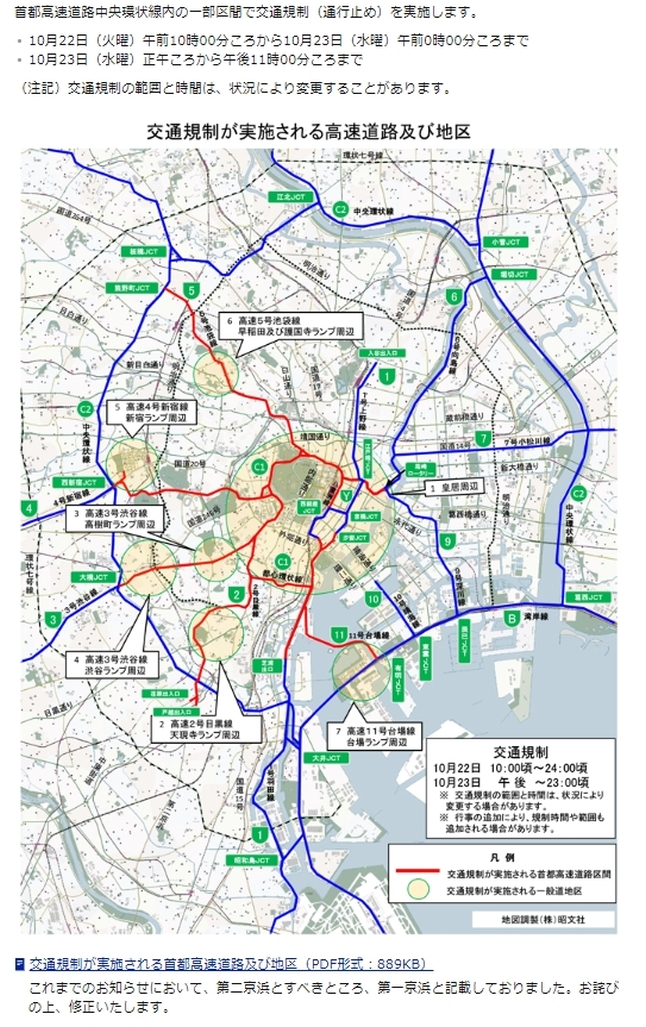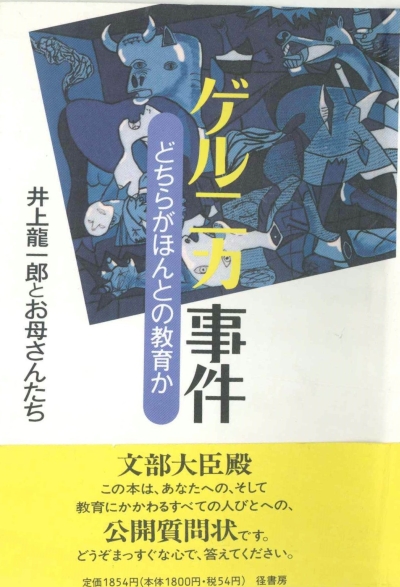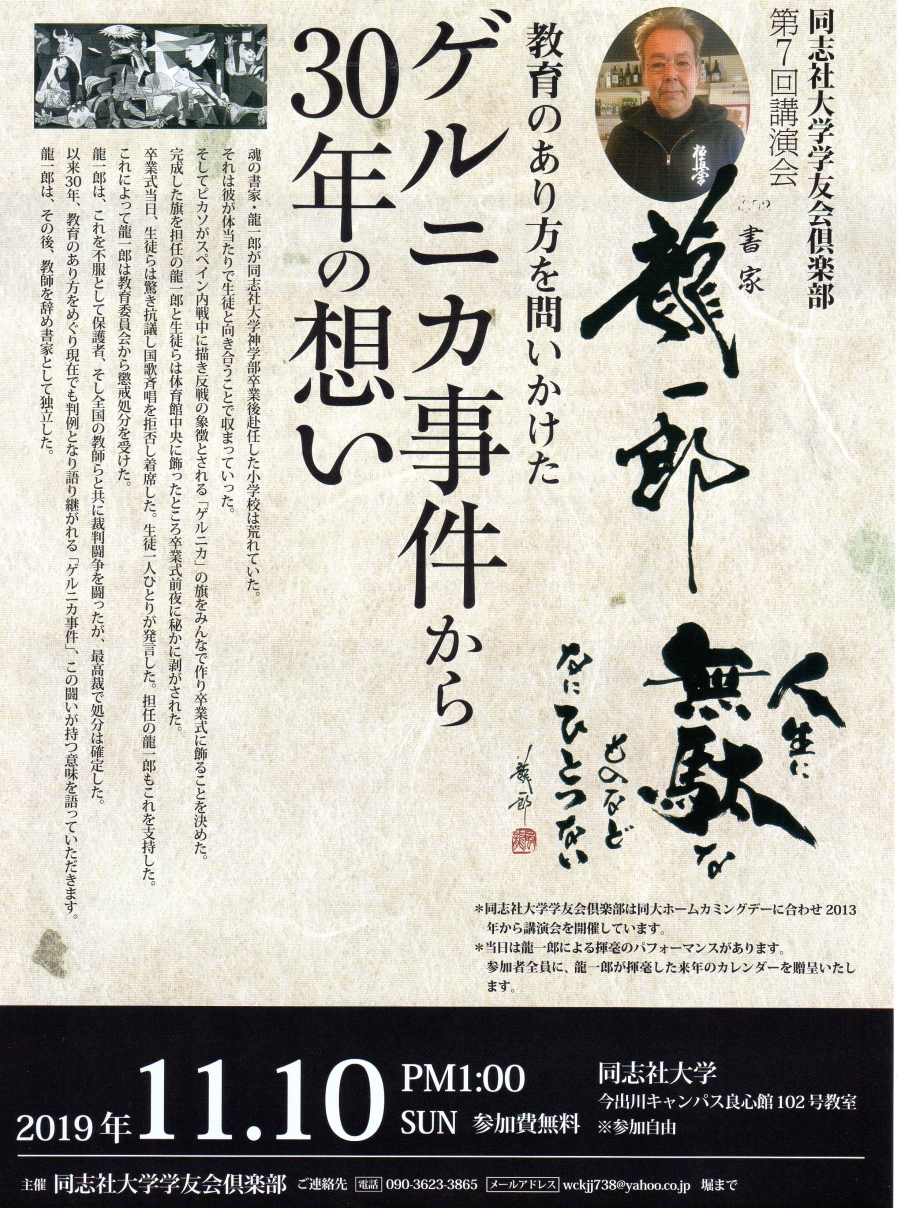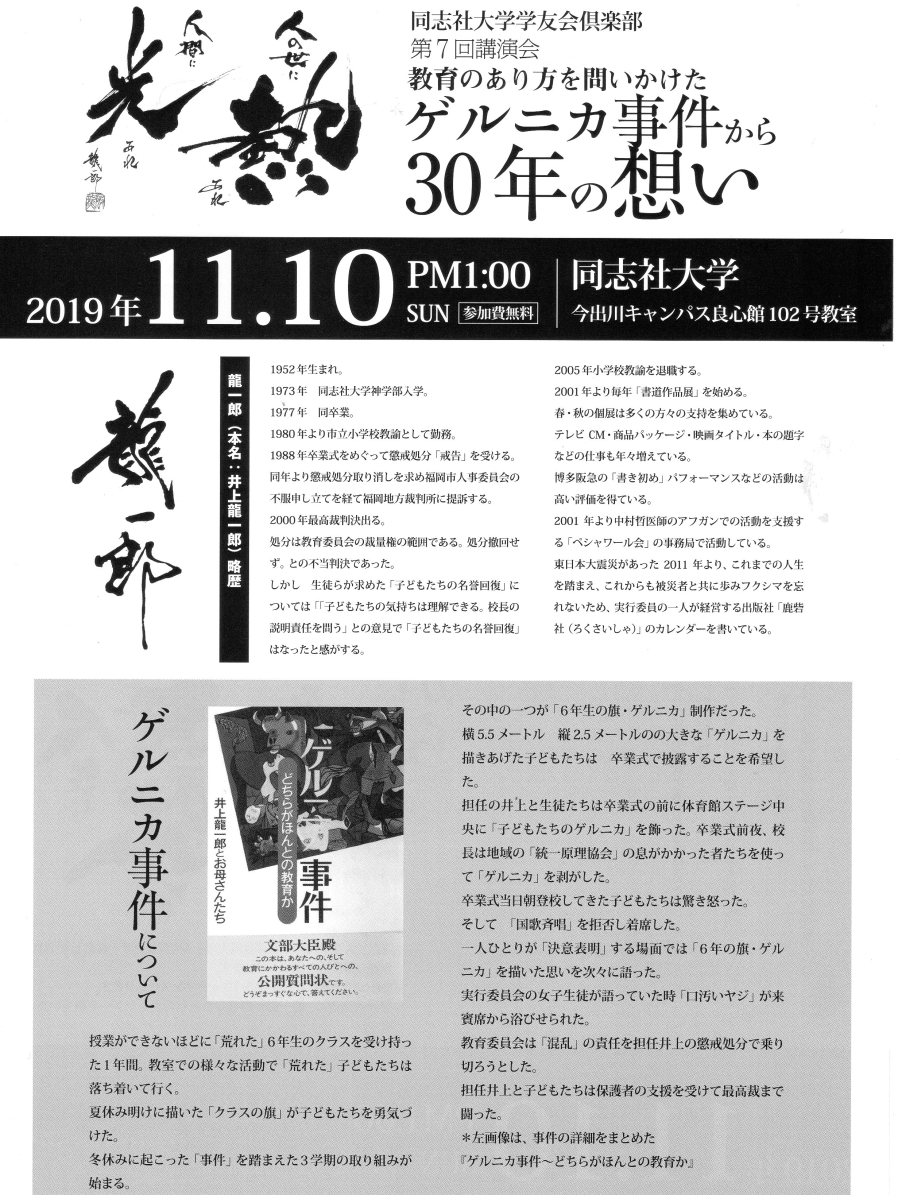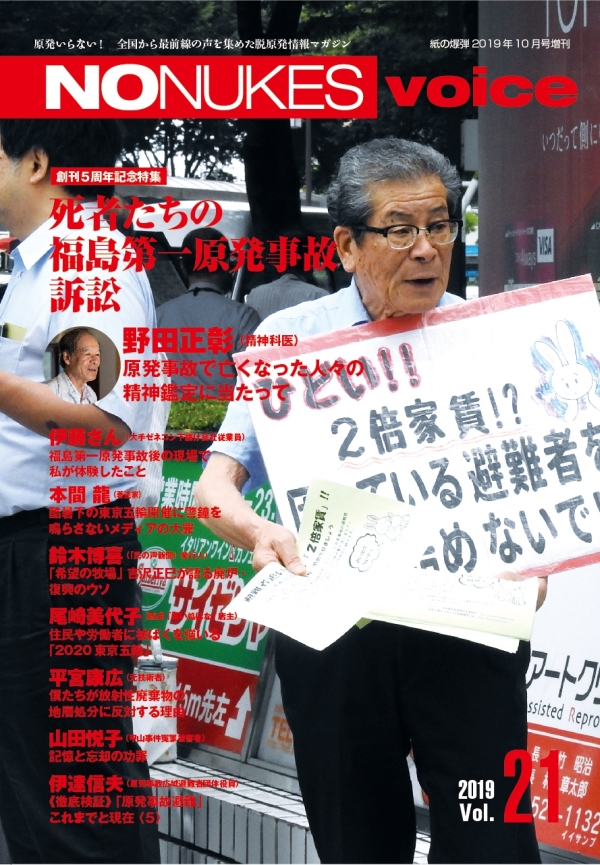10月20日夜、急な取材のため、でかけたものの帰宅できなくなり、安宿で一夜を過ごすことになった。この日はラグビーワールドカップの準々決勝、南アフリカ―日本戦が19時過ぎから行われ、のちの視聴率調査では40%を超える数字を得たという。
自宅にはテレビがないが安宿の食堂では、宿泊客がNHKの中継に見入っていてた。ラグビーは国境を意識させないスポーツとして、だいぶ以前に本通信で好意的に紹介した記憶がある。その一方、日本開催となった本大会に限れば、来年予定されている「企業の祭典」東京五輪の予行演習の側面と、例によって、にわかファンの騒ぎぶりに、ひねくれものは反応してしまい、ろくろく試合も見ていなかった。
◆「Nkosi Sikelel’ iAfrika」(神よ、アフリカに祝福を)
20日、日帰りを予定していた出張が、予想外に長引いたことでわたしも南アフリカ―日本の試合を観戦することができた。そして試合前にわたしは自分の不勉強と、虚を突かれることになった。ラグビーのワールドカップは他の競技と異なり、純粋な国対抗ではない。英国だけでもスコットランド、ウェールズ、イングランドが今大会に出場している(アイルランドも国だけではなく英国領アイルランドとの合同を意識したチームだ)。だから試合前の「国家斉唱」では通常の英国国歌とされるものではない歌詞やメロディーを使わざるを得ない。
そこまではわかっていたが、自分の無知を恥じたのは、南アフリカ国歌が流れたときだ。「え! あの歌が国歌になっていたんか!」と声を出してしまった。あれは何年だっただろうか。リチャード・アッテンボロー監督の映画『Cry Freedom』(邦題「遠い夜明け」)で聞いた曲だ。
◎[参考動画]Nkosi Sikelel’ iAfrika – Cry Freedom [1987]
当時国際社会から非難されながらも南アフリカでは、明確な差別、人種隔離政策“Apartheid”(アパルトヘイト)がまだ蛮行を続けていた。『Cry Freedom』のエンドロールでは、「1962年の国会において、南ア政府は法律なしでの勾留を認めるようになった。これから紹介するのは、それ以降投獄され死亡したひとびとの、名前と死因の公式発表である」の説明のあとに延々と名前が続いたことが忘れられなかった。
『Cry Freedom』の主人公は、南アの有力新聞デイリー・ディスパッチ紙の白人記者ドナルド・ウッズだ。けれども実際の主人公は1968年に「南アフリカ学生機構」を立ち上げ、のちにドナルド・ウッズと親交を結ぶことになる、スティーブ・ビコだ。スティーブ・ビコは1968年に「南アフリカ学生機構」を設立し、南アにおける黒人解放運動の指導者として、もっとも有名な人物のひとりである。つまり『Cry Freedom』は実話をもとにした映画作品であった。ビコは映画の途中で早々に、虐殺されてしまい、フィルムのかなりの時間はドナルド・ウッズの南アからの、脱出物語にさかれている。このあたりに、若かったわたしには「ちょっと、主役が違うんじゃないか」と感じた記憶もある。
メロディーが記憶にあったのは、調べてみるとコザ語、ズール語による「Nkosi Sikelel’ iAfrika」(神よ、アフリカに祝福を)という曲だったようだ。作詞作曲されたのは19世紀。以来アフリカの多くの国で、独立象徴の歌として歌い継がれたようだ(19世紀アフリカの解放歌が、キリスト教に依拠していた事実をどう考えるか、の課題は横に置く)。
南アの国歌は、わたしが一回聞いただけだが記憶にある「Nkosi Sikelel’ iAfrika」だけではなく、途中で著しく変調した。後半はアフリカーンス語の「Die Stem van Suid-Afrika」(南アフリカの呼び声)を編曲したものだ。1997年にネルソン・マンデラが大統領に就任して出来上がった、2つの歌が合体しているので、変調が際立ってきこえたのかもしれない。
◆寒い国で初めて出会った南ア人
『Cry Freedom』を鑑賞したのより、さらに10年ほど前、わたしは最低気温がマイナス30度を下回る国を放浪していた。その時も安宿に宿泊していた。二段ベッドが3つ並ぶドミトリーといわれる、最安値の宿だ。その国の住民と同じく白人の宿泊者が会話をはじめた。
「あんたこの国の人間かい?」
「いや、俺は南ア人だよ」
「フー、大変なところにすんでるな。黒人(blackとその白人は発語した)が面倒だろう」
「ああ、俺は徴兵を終えたばかりなんだ。軍隊はよかったよ。黒人に気をつかうことがなかったから」
「この国でも黒人はいつも問題をおこしてばかりさ」
なんというあけすけな人種差別をする連中か、とかと呆れていたら。こちらに声が向いてきた。
「あんたはどこからきたんだ?」
「南アだよ」
下手くそな英語で嫌味を返したつもりだった。
「そんな英語が下手な南ア人はいないさ」
すぐにみやぶられ、日本からやってきていることを告げて、
「南アの白人にとっては、有色人種は黒人と同じなんだろう?」
実際そうであると聞いていたので、素朴な質問をなげかけた。
「いや…。ウーン。日本人は特別扱いされると思うよ」
こちらの機嫌を気にしたのか、南ア白人は曖昧にこたえ
「あした、3人でクロスカントリースキーをやらないかい? 俺はやったことがないんだ。日本は雪が降るんだろう?」
と、妙ななりゆきで誘いをうけた。予定も立てていなかったので、3人でクロスカントリースキーを借りて、山道を歩き(滑るというほど初心者に簡単なものではなかった)まわった。
わたしの知る南ア人は、彼だけだ。山道を苦労しながらドタバタするなかでも、彼は饒舌だった。
「おれは規律がすきなんだ。だから軍隊が心地よかった。ワン、トゥー、ワン、トゥー!」
わたしは規律が嫌いで、軍隊に入ることなど想像もできない。
「雪山はきれいだな! 白はいい! 人間も白に決まってる!」
うそのような話だが、黄色人種のわたしの横で、休憩のために腰を下ろして,たばこを吹かしながら大きな声で、もう一人の白人に同意をもとめる。彼は“Apartheid“が廃止され、ネルソン・マンデラが大統領になる日が来るなど、考えもしなかったことだろう。
わたしは、たったひとりの南ア人とは1泊2日をともにしただけだから、そこから決めつけるのは乱暴すぎるかもしれないが、その後、日本で聞くニュースやなどからも、南アフリカについては複雑な感情しか持てなかった。
それだけに、その後ろくろく南アフリカの情報に関心を向けなかった自分の不勉強を、ラグビーの試合によって偶然知るしる機会を得たのは果報だった。まさかあのメロディーが「国歌」になるなんて。信じられなかった。両チームの選手には申し訳ないが、そのことの驚きは、かなり長時間持続した。わたしは「君が代」が大嫌いだ。陰鬱なメロディーで、「解放」などとは無関係な歌詞。対照的に、キリスト教を下地にしているとはいえ、アフリカ全土で歌われた、黒人解放歌が国歌だなんて、素晴らしいじゃないか。
◎[参考動画]Nelson Mandela – Nkosi Sikelel’ iAfrika (God Bless Africa)
南アには貧困、エイズ、引き続き人種による軋轢など、さまざまな問題があることは知っている。犯罪発生率も際立って高いことも。解放歌が国歌になっているぐらいで、感激しているのは、おめでたい奴だとじぶんでも思う。でも正直、久しぶりに感激した。きっと、それほどにわたしは、常日頃、冷めきっているのだろう。
▼田所敏夫(たどころ としお)
兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。
 タブーなき言論を!絶賛発売中『紙の爆弾』11月号! 旧統一教会・幸福の科学・霊友会・ニセ科学──問題集団との関係にまみれた「安倍カルト内閣」他
タブーなき言論を!絶賛発売中『紙の爆弾』11月号! 旧統一教会・幸福の科学・霊友会・ニセ科学──問題集団との関係にまみれた「安倍カルト内閣」他
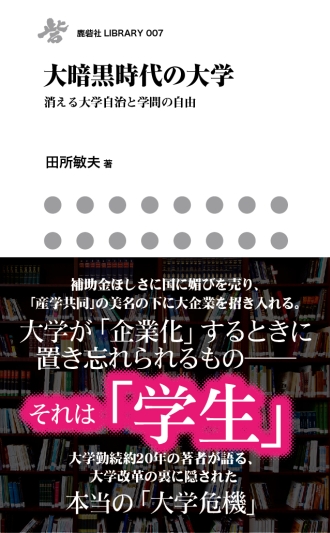 田所敏夫『大暗黒時代の大学──消える大学自治と学問の自由』(鹿砦社LIBRARY 007)
田所敏夫『大暗黒時代の大学──消える大学自治と学問の自由』(鹿砦社LIBRARY 007)