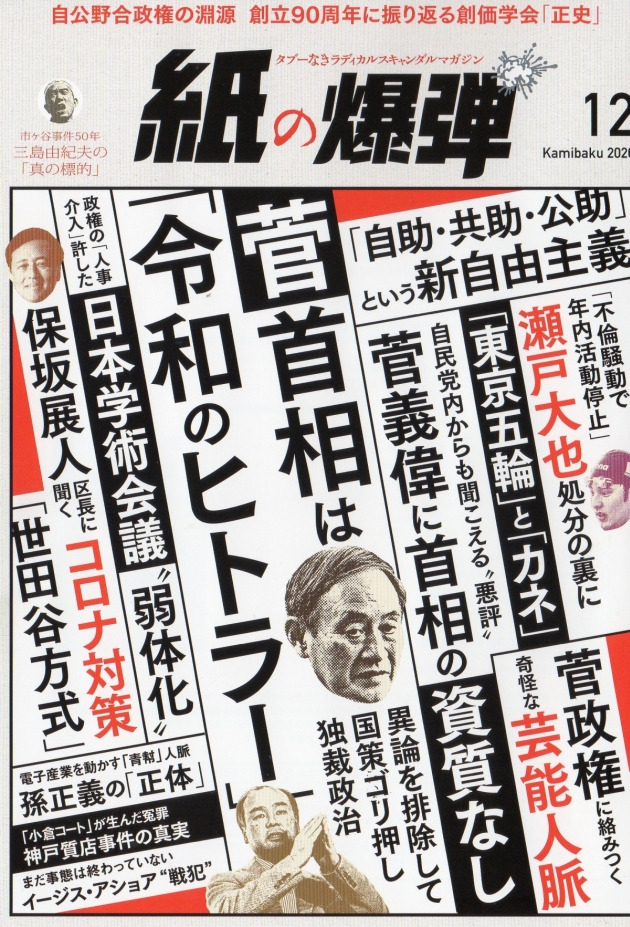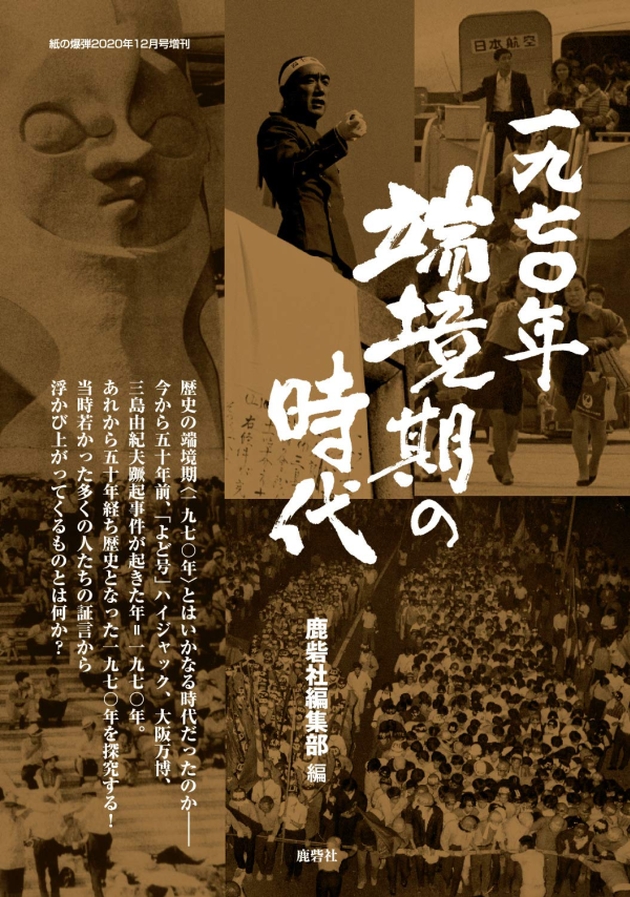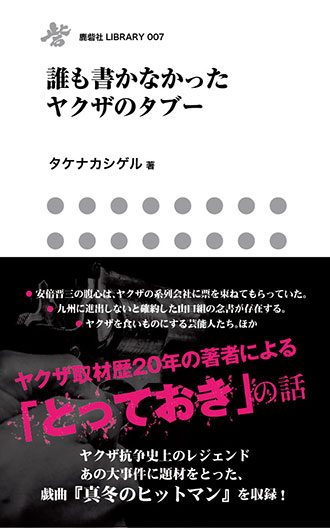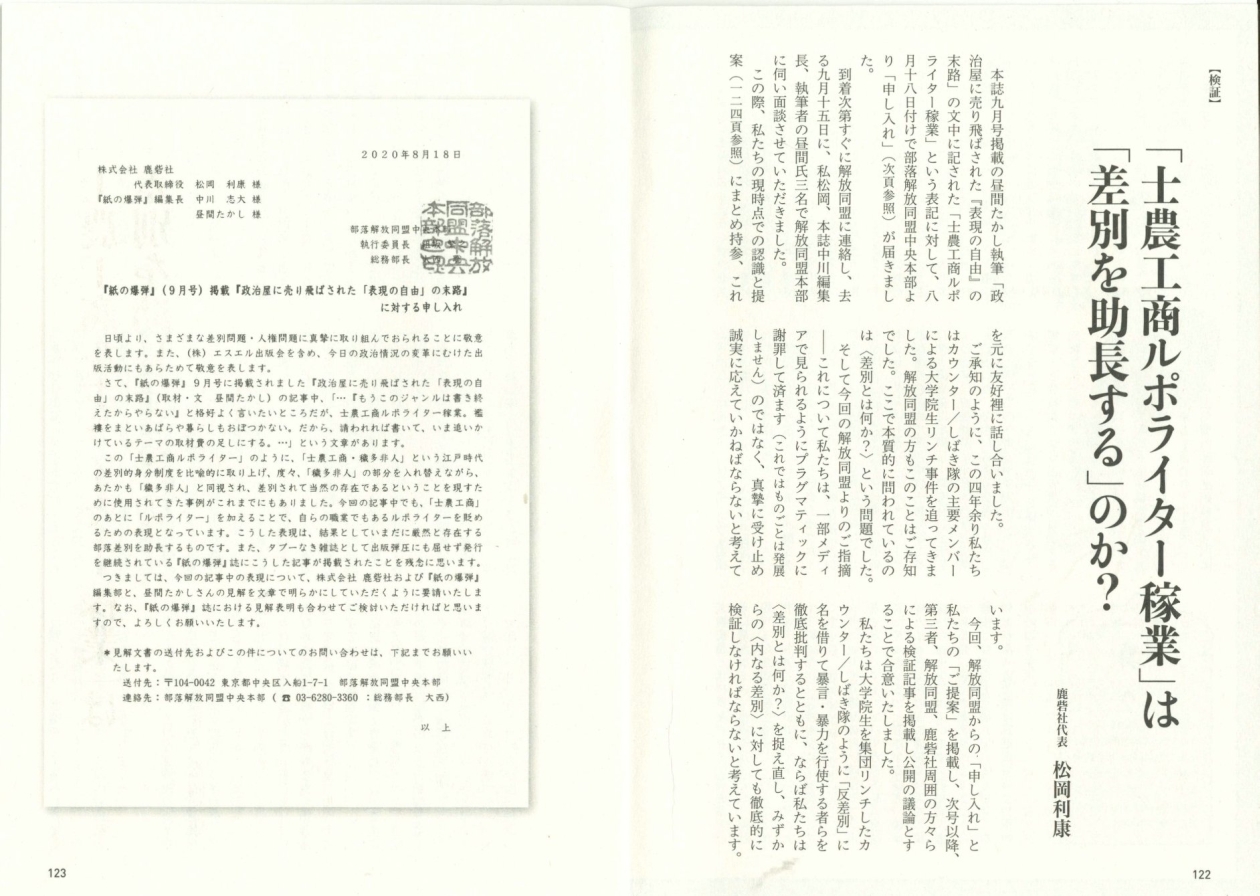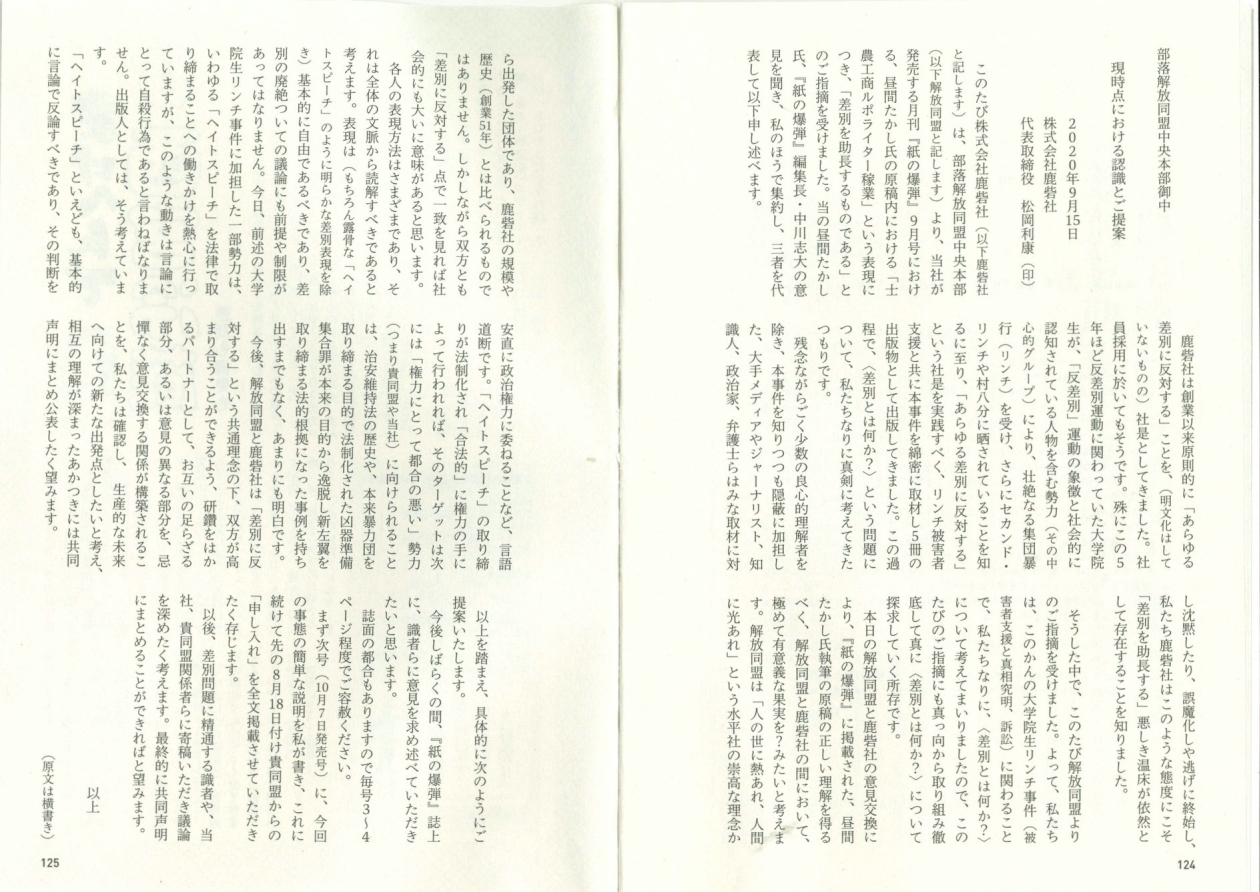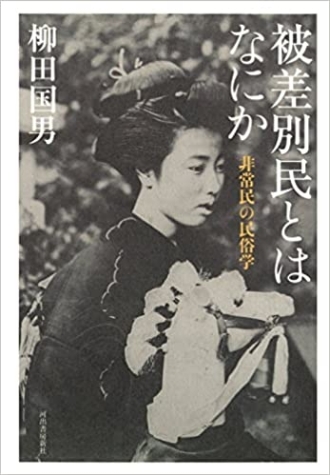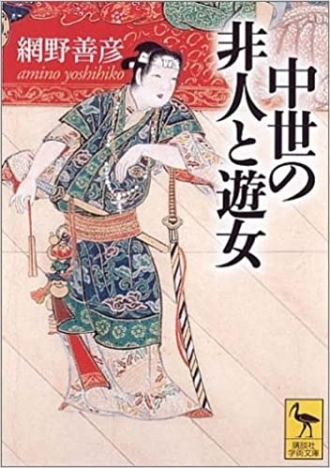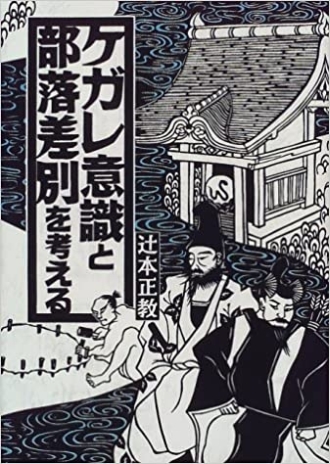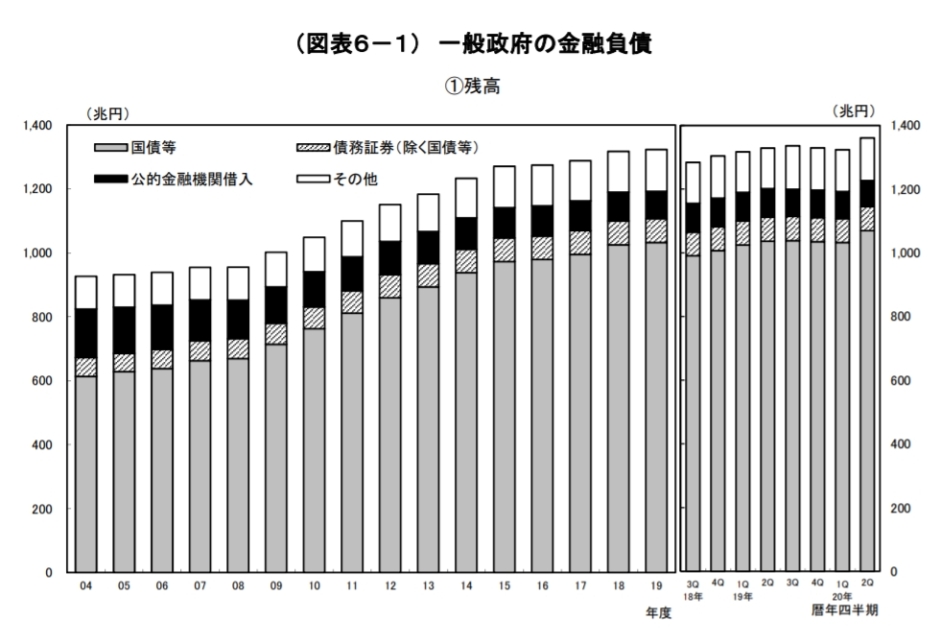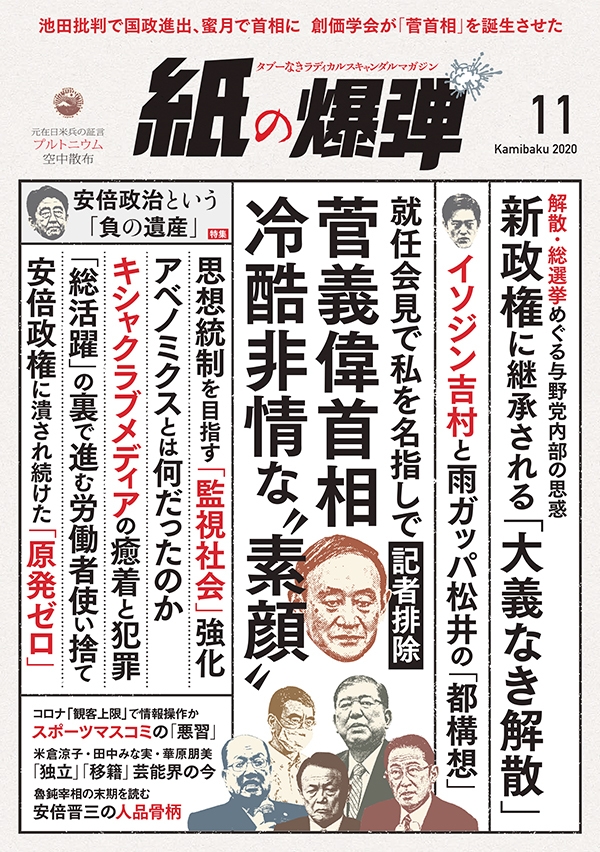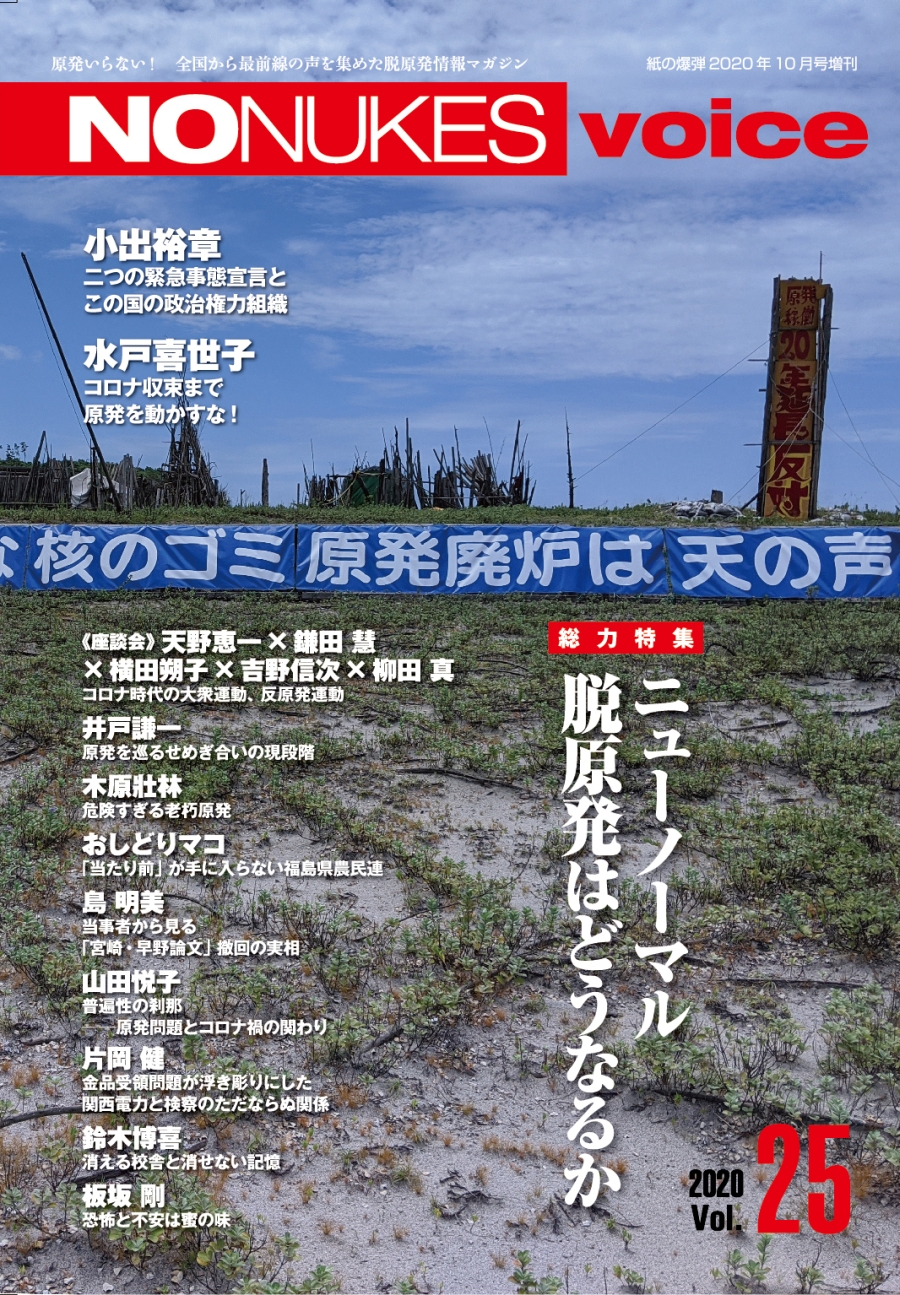◆やはり検察人事介入は訴追を怖れてのことだった
あのとき、安倍元総理は今日のようなことがあるのを想像しただろうか。まさに驕れる者も久しからずだが、これを想定していたからこそ、芸能人による反対運動まで巻き起こり、大きな波紋を呼んだ検察庁法改正案問題があったのではないか。
すなわち黒川弘務検事長の定年延長という、いわば自陣営の審判役を検察トップに確保する人事案を、安倍晋三は冷静沈着にも考えていたのだろう。それは検察庁法改正として課題を先のべにしながら、いまも三権分立を掘り崩す政府の策動として続いている。
最高裁判事の〇×式の投票に「この裁判官が下した判決」および法曹界の賛否両論の併記を書き添えるなど(現状は無意味な氏名だけ)、検察人事も国民投票に付すべきものではないか? 本気で三権分立を実現するのなら、将来は行政の長(総理大臣)もふくめて、国民投票を実施するべきである。
◎[参考動画]高検検事長の『定年延長』は安倍政権の“守護神”だから?(TV東京 2020年2月5日)
◎[参考動画]黒川検事長が辞任へ 森大臣「賭博罪にあたる恐れ」(ANN 2020年5月21日)
さて、桜を見る会前夜祭における安倍元総理のウソが明白となった。5年間で2000万円のうち、安倍事務所が916万円を補填していたというのだ。安倍晋三国会で、かたくなに否定してきた明細書(安倍元総理の政治団体=晋和会あて)をホテル側が保管していたのである。
パーティーへの選挙民の参加費を議員が支払う。これは単なるウソにとどまらず、「選挙民への寄付(買収)」にほかならない。
公職選挙法違反(公職選挙法199条の2の1項)である。そして事務所で支払わなかったとして、政治団体の収支に記載をしなかった。これは政治資金規正法違反(政治資金規正法第12条2項)でもある。
それぞれ、一年以内の禁固又は30万円の罰金(公選法)、5年以下の禁固又は100万円以下の罰金(政治資金規正法)である。安倍晋三は逮捕、起訴、そして禁固刑で収監される「可能性」が出てきたのだ。
◎[参考動画]安倍前総理がコメント “桜”前夜祭補填疑惑(ANN 2020年11月24日)
◆ふつうの論理が通用する社会にもどせ
そもそも11000円が最低価格のホテルパーティーに、参加者が5000円しか支払わなかった時点で、安倍および安倍事務所の虚偽は明白だった。
にもかかわらず、参加者個々人が契約主体であり、そのさいの領収書や明細書は発行されなかった、などと作り話をしてきたのだ。ホテルはいわばサービス業の頂点であり、ニューオータニやANAホテルなど、わが国を代表する高級ホテルは明朗会計を謳っている。その意味では、安倍の「明細書は発行されなかった」という答弁は、ホテル側の名誉を毀損するものでもあった。
日本学術会議の任命を拒否するという、国民を代表しての「義務」を果たさないまま、その理由を明らかにしない。つまり、学問研究への政治介入の現実を認めようとしない菅総理の「強弁」のお手本が、まさに安倍の「明細書は発行されなかった」なのである。
国民の負託による審議の場で、ウソをつきとおす異常な事態は、これ以上続けさせてはならない。いまこそ安倍晋三とその秘書団を逮捕し、ふつうの論理が通用する社会にもどす必要があると指摘しておこう。
◎[参考動画]安倍前総理「桜を見る会」前日の夕食会をめぐる国会答弁(TV東京 2020年11月25日)
◆秘書への責任転嫁をゆるすな
さて、虚偽が明らかになった以上、問題はその責任の取り方である。すでに安倍元総理の周辺は「国会答弁で補填を否定したが、事務所の秘書(公設第一秘書)が安倍氏に虚偽の報告をした」と防衛線を張っている。
慧眼な読者諸賢はすぐにこの言葉で、ある種の危惧を抱くことであろう。虚偽報告をしたとされる秘書が、責任をとって最悪の選択をする可能性である。
すでに安倍政権と財務省高級官僚は、安倍が「私と妻がかかわっていたら、私は総理大臣も国会議員も辞めますよ」という啖呵を忖度し、財務省の職員を死に追いやっているのだ。今回もすべてを秘書に押し付け、国会の証人喚問にも応じない(自民党に拒否させる)可能性が高い。
したがってトカゲのしっぽ切り体質が、新たな犠牲者を出さないとも限らないのである。だからこそ検察はただちに安倍を逮捕して、証拠隠滅や部下の自殺を防止しなければならない。安倍本人に「あなたが政治責任と刑事責任を取り、国民に範をしめしなさい」と。
◎[参考動画]総理「関与なら辞任」 国有地“格安”払い下げ(ANN 2017年2月18日)
◎[参考動画]安倍総理「籠池氏はウソ八百」昭恵夫人の活動を…(ANN 2018年2月5日)
◆菅義偉のポンコツ答弁
その安倍を官房長官として擁護してきた菅義偉総理といえば、あいかわらずポンコツ答弁である。
昨年の内閣員会で、重ねて「領収書を出せばわかること」と問われたときに「ホテルの領収書はない。議事録に残るわけですから、責任は以上のとおりです」と答えていたんは記憶に新しい。
そのみずからの虚偽答弁を問われても、秘書官のメモを片手に、
「わたくしは、そ、総理から言われたことを、答弁したものであります」「そ、総理は、その場に居ませんでしたから」
ようするに、自分は「子供の遣い」だったというのだ。そうではない、虚偽が議事録に残ったことが問題なのだ。ウソは真実をもって、書き換えられなければならない。そして虚偽答弁には、政治責任がとられねばならない。
だが、わが菅義偉は、さらに言葉に詰まりながら、
「そ、それは、そ、総理が説明されることだと思います」「いずれにしましても、いま、捜査が行なわれているかどうかわかりませんが……(ヤジ)、捜査機関の活動に関わることですから……、わたしの立場で、答弁は差し控えさせていただきます」とくり返すしかなかった。
捜査は安倍事務所への聴取として厳正に行なわれているのだから、現役の総理が自分の答弁を説明しても何ら支障はない。すでに安倍元総理は、一部補填(事務所からの寄付にあたる)があったのを認めてもいるのだ。
100歩ゆずって「わたしに訴追の怖れがあるので、答弁は差し控えたいと思います」ならばともかく、である。
秘書官のメモ便りのポンコツ答弁ぶりゆえに、安倍晋三のような大見栄の啖呵を切ることもなく、その分だけ安全運転とはいえる。が、答弁に尻込みする姿は、一国の総理としてはいかにも風格がないと評しておこう。
そして、そのポンコツ総理から「捜査中なので答える立場にないし、仮定の質問には答えられないが、一般論として虚偽答弁であったなら、その時は対応(謝罪)したい」という答弁は得られた(11月25日参院予算委、福山哲郎委員への答弁)。
いずれ事件の概要が明らかになり、安倍元総理が喚問されたうえで、前総理と現総理が首をそろえて国民に謝罪する日も近いかもしれない。
◎[参考動画]“桜前夜祭”巡り…菅総理「事実違えば私にも責任」(ANN 2020年11月25日)
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。医科学系の著書・共著に『「買ってはいけない」は買ってはいけない』(夏目書房)『ホントに効くのかアガリスク』(鹿砦社)『走って直すガン』(徳間書店)『新ガン治療のウソと10年寿命を長くする本当の癌治療』(双葉社)『ガンになりにくい食生活』(鹿砦社ライブラリー)など。