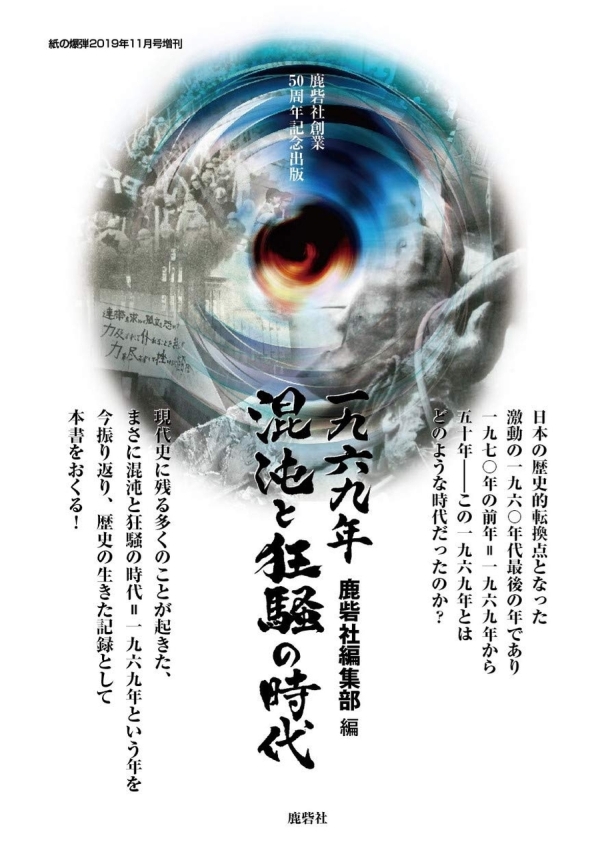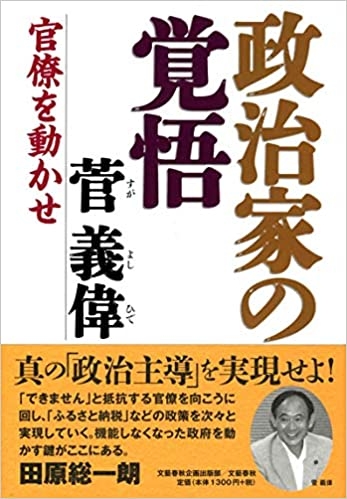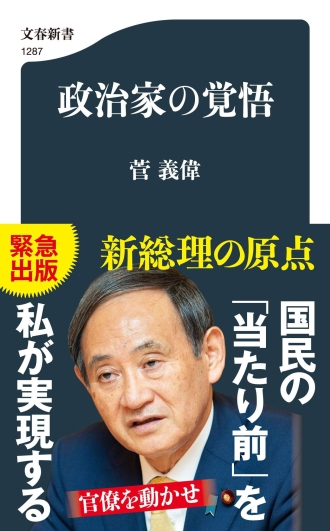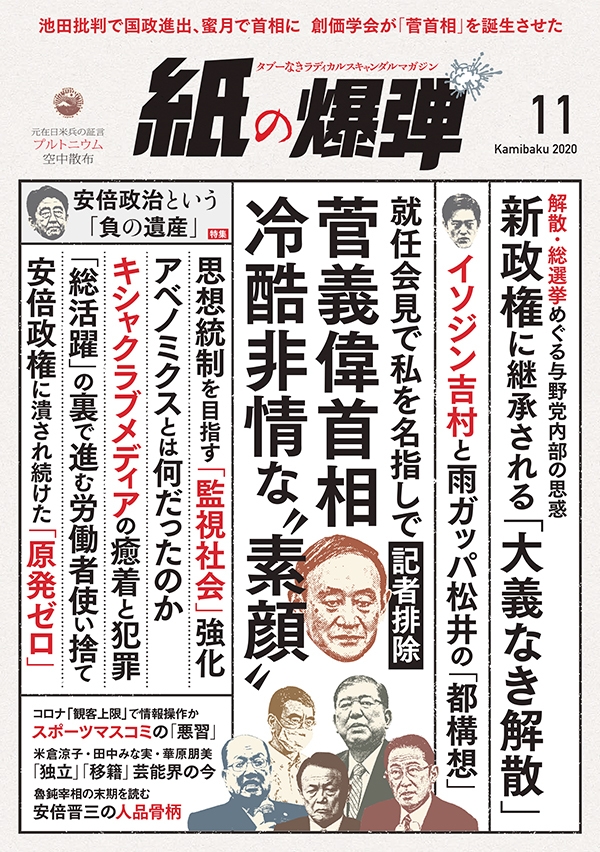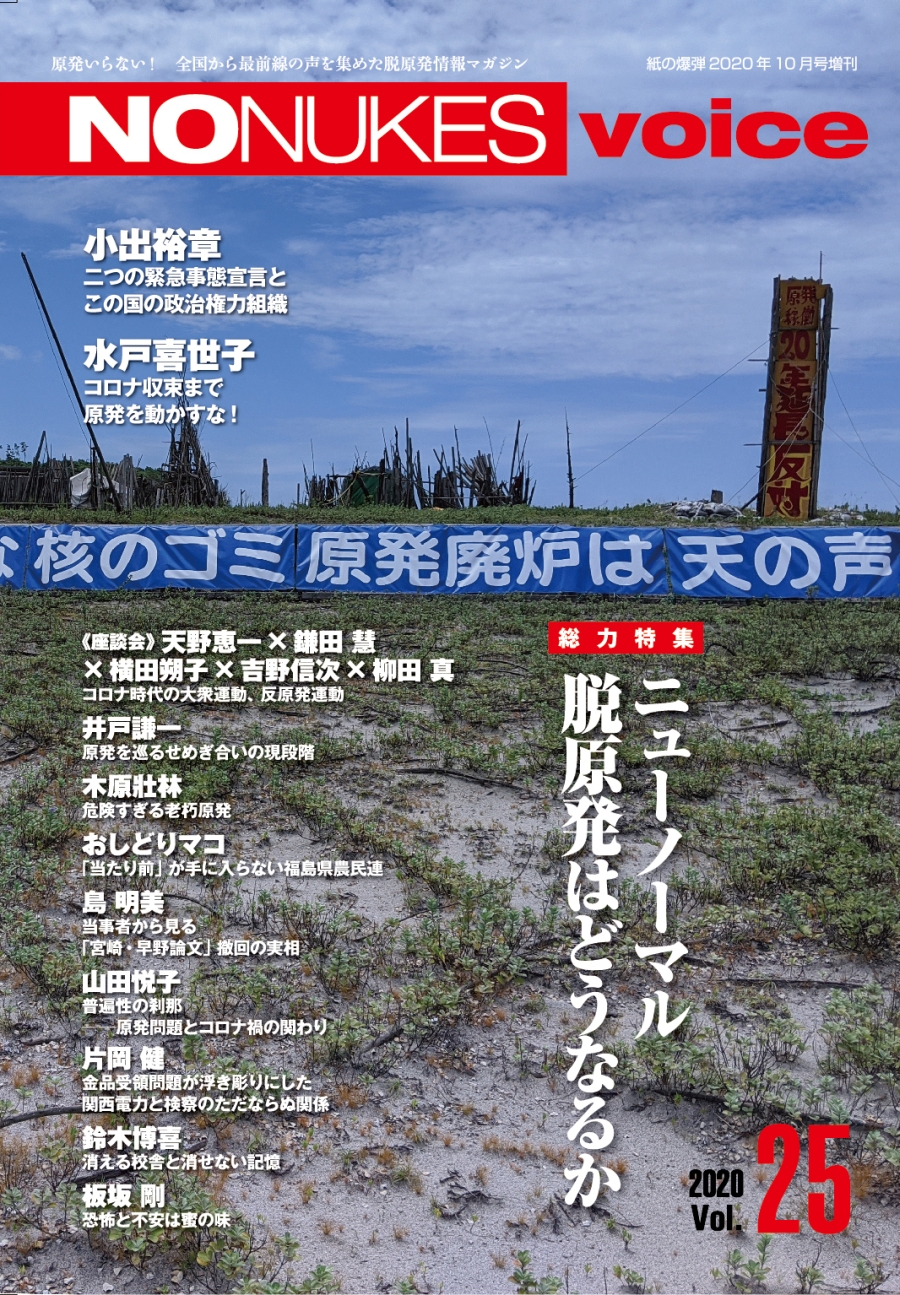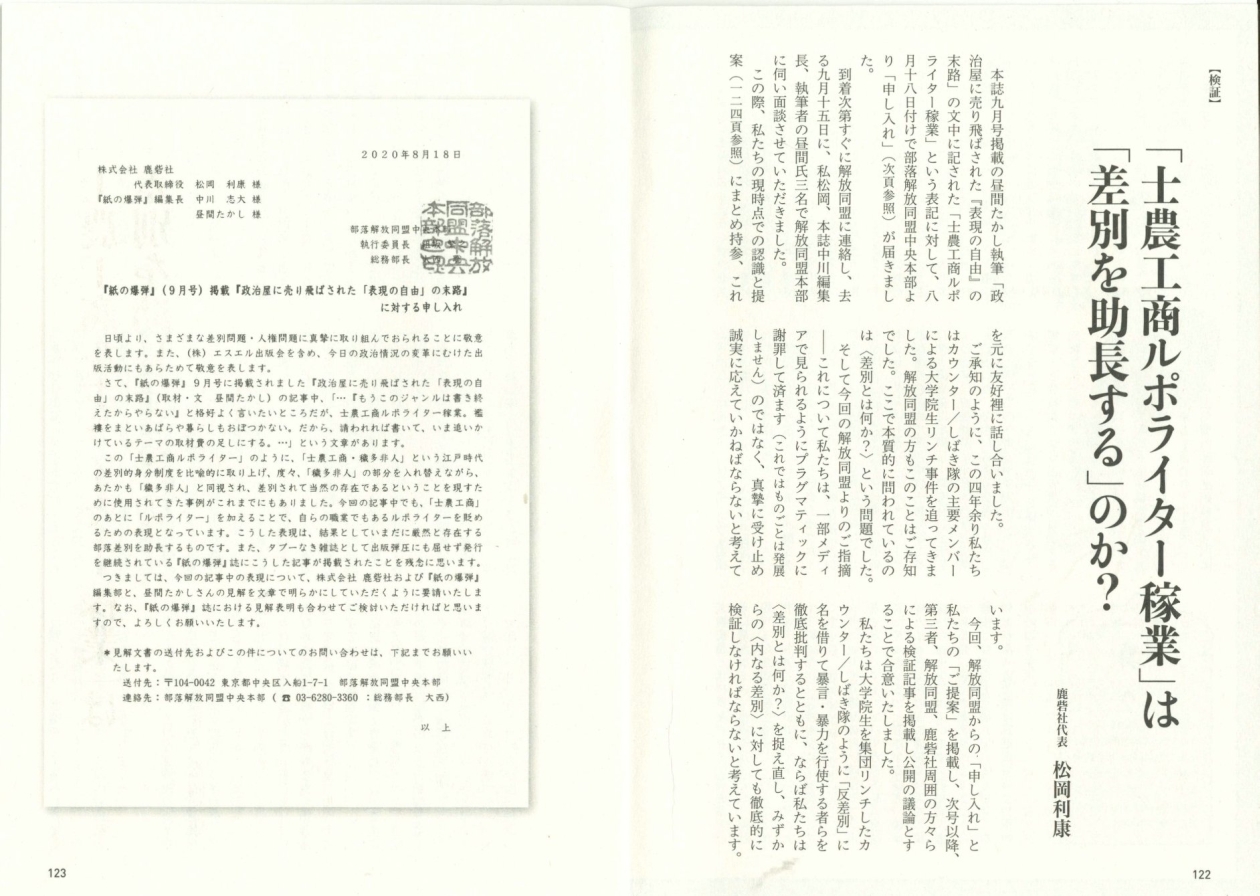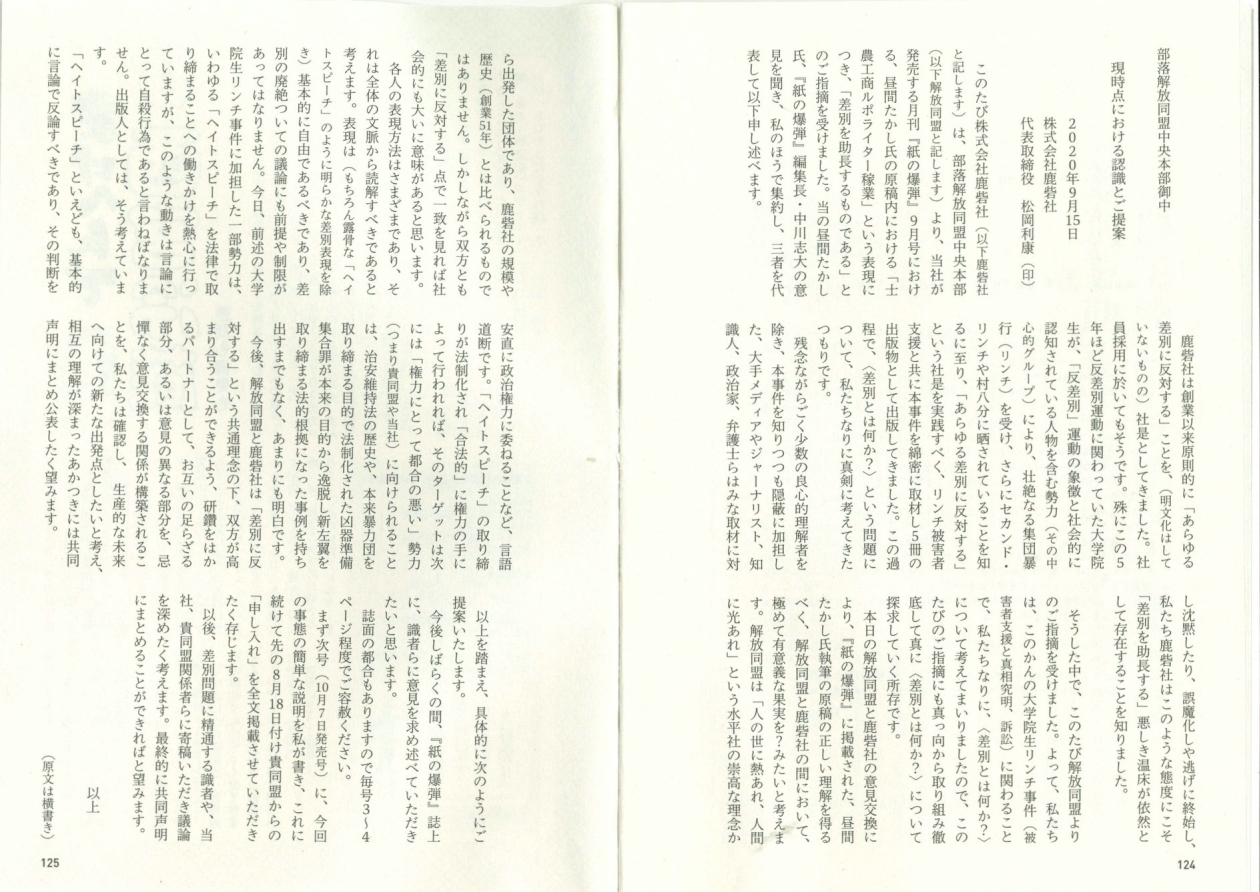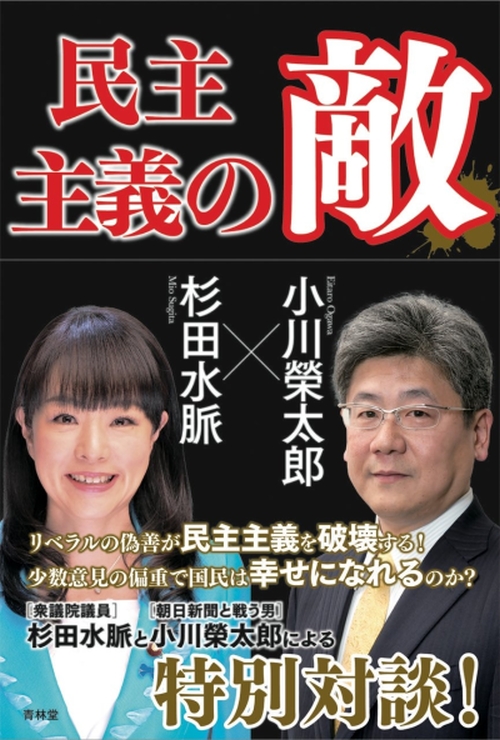119代光格(こうかく)天皇は、近代の天皇権力を強く主張した天皇である。30年以上も在位し、退位後の院政をふくめると、幕末近くまで50年以上も権力を握っていた人物である。博学にして多才。朝儀再興にも尽くし、その事蹟は特筆にあたいする。

なかでも有名なのは、寛政の改革期に松平定信と争った尊号一件と呼ばれる事件であろう。自分の父親(閑院宮典仁親王)に太上天皇号の称号を贈位しようとしたところ、松平定信がそれに猛反対して争った事件である。父親の典仁親王が摂関家よりも位階において劣るため、天皇は群議をひらき参議以上40名のうち35名の賛意をえて、太上天皇号の贈位を強行した。皇位を経験しない皇族への贈位に、先例がないわけではなかった。
ところが、老中松平定信はこれを拒否した。議奏の中山愛親、武家伝奏の正親町公明を処分し、勤皇派の浪人を捕縛する事態に発展した。この事件の裏には、十一代将軍徳川家斉が実父・一橋治済に大御所号を与えようとしていた事情があり、治済と対立関係にある定信は贈位を拒否するしかなかったのだ。そして勤皇派の台頭を背景にした公武の対立が、徐々に煮詰まりつつあった。
光格天皇の行動の基底には、彼が傍系であったことが考えられる。閑院宮家からいきなり天皇家を継ぐことになった光格天皇は、血統としては傍系であって、後桃園天皇の養子になることで即位している。天皇としての立場も当初は微妙な位置にあり、そのことから自己のアイデンティティを持つために、天皇の権威を強く意識したのではないかと考えられる。

◆孝明天皇と幕末の激流
その子・仁孝天皇もたいへんな勉強家で、朝儀の再興につとめ、漢風謚号の復活や学習所の設立を実現する。この学問所(のちに京都学習院)には、気鋭の尊皇攘夷派が集うことになる。そして仁孝天皇の崩御後、幕末のいっぽうの大立役者、孝明(こうめい)天皇の即位へといたる。
学究肌の祖父・光格天皇、実父・仁孝天皇にたいして、孝明帝は政治的かつ意志的な天皇であった。一貫して強行な攘夷論をとなえ、しかしその政治方針は佐幕・公武合体派だった。幕末動乱における孝明天皇の役割り、決定的なシーンをふり帰ってみよう。
ペリー来航に先立つ弘化3年(1846年)、孝明天皇は父帝崩御をうけて16歳で即位した。この年、アメリカの東インド艦隊司令官・ビッドルが来航したほか、フランス・オランダ・デンマークの船舶があいついで来航し、通商をもとめてきた。
16歳の孝明帝は幕府にたいして、対外情勢の報告と海防の強化をうながしている。まさに少壮気鋭の君子である。朝廷内部に口出しをする幕府に反発していた、歴代の天皇とはおよそ次元がちがう。国のすすむべき指針を、みずから口にしたのである。
いよいよペリー艦隊が来航すると、天皇はさらなる海防強化を幕府にもとめ、参勤交代の費用を国防費にあてるよう提案している。そして幕府がむすんだ日米和親条約には「開港は皇室の汚辱である」と、断固反対の意志をあらわす。老中堀田正睦の調印許諾の勅許を、天皇は断乎として拒否したのである。
けっきょく、幕府は大老井伊直弼が勅許を得ないまま欧米各国と通商条約をむすび、ここに日本は開国する。その一報をうけた孝明天皇は激昂した。もはや今の幕閣は頼りにならない。尊皇攘夷派の重鎮である水戸斉昭に、幕政改革の詔書を下賜するのだった(戊午の密勅)。ここにいたって、幕府と朝廷の外交方針をめぐる対立は極限にいたる。それは当然ながら、すさまじい反動をもたらした。
すなわち、幕藩体制が崩壊させかねない朝廷のうごきに激怒した井伊直弼による安政の大獄、尊皇攘夷派にたいする熾烈な弾圧がおこなわれたのである。そして日本は、局地的ながら、流血の内乱に陥った。
桜田門外の変によって井伊直弼が殺害されると、京都市中は尊皇攘夷派の活動が活発になり、それを弾圧する寺田屋事件(薩摩藩による粛清)。8月18日の政変による、長州派公卿の追放(七卿の都落ち)。さらには禁門の変において、長州勢を一掃する事態となる。尊皇攘夷をとなえる長州を、攘夷をねがう朝廷が排除するというアンビバレンツな事態は、ひとえに幕府との関係をめぐる落差である。そこに孝明天皇の悲劇があった。この「落差」については、くわしく後述する。
天皇は公武合体を促進するために、妹宮の和子内親王を14代将軍家茂に嫁さしめようとした。有栖川熾仁親王と婚約中であった和宮がこれを拒否すると、生まれたばかりの寿万宮をかわりに降嫁させるなどと、妹を相手にほとんど脅迫である。和宮の降嫁が実現しなければ自分は譲位する、和宮も尼寺に入れるなどと、無茶なことを言いつのっての縁組強行だった(「公武合体の悲劇」参照)。
しかしながら、幕府とともに攘夷を決行するという天皇の政治指針は、開国・倒幕の情勢に押しつぶされていく。諸外国の艦隊が大坂湾にすがたを見せると、さすがに通商条約の勅許を出さざるをえなかった。慶応2年には薩長同盟が成立し、世論は「開国」「倒幕」へと傾いていくのである。
孝明天皇と薩長の「落差」を解説しておこう。近代的な改革・開明性を評価される明治維新は、じつは毛利藩(長州)と島津藩(薩州)による徳川家打倒の私闘でもあった。関ヶ原の合戦いらい、徳川家の幕藩体制のまえに雌伏すること268年。倒幕は薩長両藩の長年の念願であり、ゆるがせにできない既定方針だったのだ。
天皇は形勢逆転をはかって、一橋慶喜(水戸出身)を将軍に擁立するが、その直後に天然痘に罹患した。いったん快方に向かうものの、激しい下痢と嘔吐にみまわれてしまう。記録には「御九穴より御脱血」とある。この突然の死には暗殺説があり、長州藩士たちによるものとも、岩倉具視らの差し金によるものともいわれる。いずれも明確な証拠があるわけではないが、傍証および証言はすくなくないので後述する。
◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。