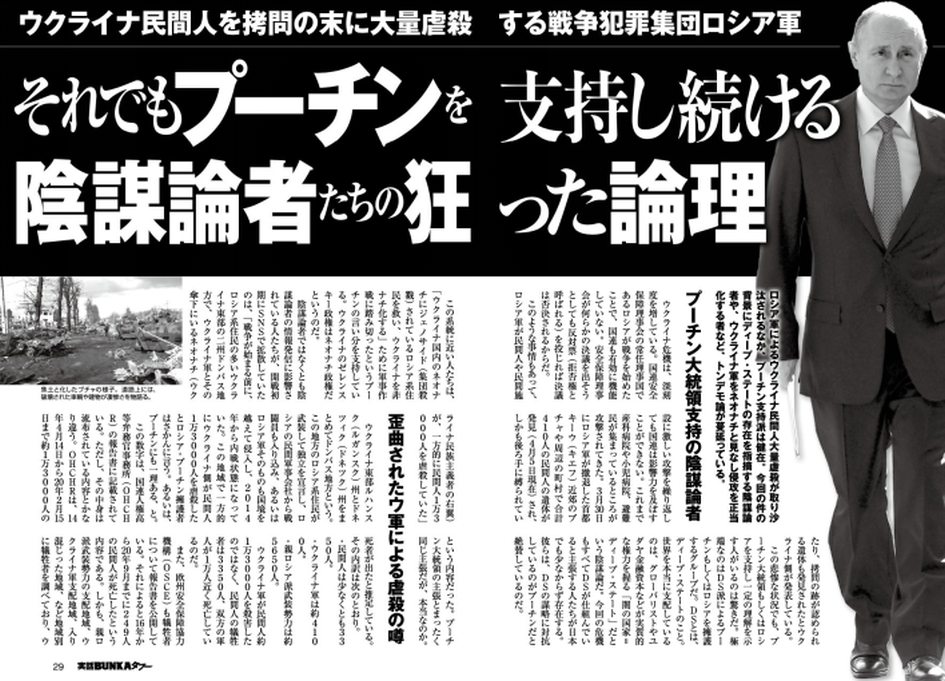一般的に、保守派・右派がウクライナ政府を支援し、左派がロシア連邦を支持している、と思われがちだ。ロシアが社会主義革命の聖地だからだろうか。あるいは保守派のなかにも、アメリカの覇権主義を警戒して、プーチンを支持する人がいる。アメリカのネオコンを中心にした、ディープステートの世界支配を唱える元駐ウクライナ大使馬渕睦夫など、トンデモ系(史実・事実の論拠なし)の著作や発言に飛びつくのは、しかし左右を問わない。
妄想を論拠にしたトンデモ議論に付き合えばきりがないので、ここでは引き続き、左翼の理論的な混乱を解説していこう。右翼にはほとんど合理的な理論指針がないので、メディアの画像をちゃんと見ている人たちは、大きな誤りに陥らないとも言えよう。
前回は、第一次世界大戦に際しての第二インターの分裂をたどってきた。
◎ウクライナ戦争をどう理解するべきなのか〈1〉左派が混乱している理論的背景
第一次大戦は、それまでの民族的な国境紛争や王家の継承戦争といった、いわば絶対主義王政時代(近世ヨーロッパ)の戦争とはちがう。帝国主義段階の拡張政策・市場再分割がおもな動因であった。
そして兵器の高度化とともに、戦争動員が国民的な経済資源と人的資源にまで及んだ、いわゆる「総力戦」となって顕われてきたのだ。そこで、左派も戦争に対する態度が問われてきた。
第二インターの指導者であるカール・カウツキー自身は戦争に反対の立場だったが、分裂を回避するために祖国防衛の立場をとっている。のちに、レーニンか「プロレタリア革命と背教者カウツキー」としてこき下ろされる。
だが、帝国主義論においては現在のグローバリズム(資本の国際化)が、カウツキーの「超帝国主義論(世界大に発展した帝国主義諸国は、もはや協調に至らざるをえない)」を実証した。ぎゃくにレーニンの帝国主義間戦争の必然性は、第二次大戦以降は証明されていない。もちろん代理戦争と呼ばれる、地域戦争や紛争は後を絶たないが、兵器の発達が帝国主義国同士の世界戦争を回避させているのだ。
◆レーニンの戦争革命論
第一次大戦までの左翼(共産主義者・社会民主主義者)は、帝国主義本国にあって自国の敗北のために闘う路線を採っていれば良かった。自国帝国主義打倒とプロレタリア国際主義である。帝国主義本国においては、これは今日も変らない。
この帝国主義本国内の左翼反対派は、よく「サヨクは反対論ばかりで政策がない」と謗られる原因だ。ある意味ではラクな政権批判であり、対案なき批評なのである。対案がないということは、単なる悪口にすぎない。
新左翼の老舗雑誌といわれる『情況』でも、国防論特集を組んだときに、オールドボリシェヴィキ(団塊以上)から猛反発が起きたものだった。かりに政権交代があったときに、旧民主党の鳩山政権のようにトータルな国防政策を欠いた「沖縄米軍基地撤去」の空公約では、政権は立ちいかない。そのあたりの政策遂行能力の有無は、現在の日本の左派においては、いまだに重大な欠陥となっている。
ともあれ、戦争に疲弊する本国政府の政治危機を衝いて、プロレタリア階級が政治権力を奪取した。これが、マルクスの「窮乏化革命論」「恐慌革命」にたいする「戦争を内乱・革命政権の樹立」として定立された。戦争革命論である。じっさいにロシアでは第一次大戦の疲弊に乗じた革命政権(1907年2月・10月)が成就したのだった。
革命ロシアはひきつづきドイツ革命・イタリア革命で、世界革命を展望できると考えられていた。しかし、そうはならなかった。反革命の国際的な干渉とドイツ革命の敗北によって、レーニン率いるボリシェヴィキは世界革命の展望をうしない、やがてスターリンのもとで一国社会主義の道を歩むことになるのだ。そのかんに、革命ロシアはウクライナをはじめとする周辺国にソビエト政権を打ち立てて、ソビエト連邦へと併呑していく。これは周辺国を内戦の渦に叩き込むことになった。
◆ウクライナ・ロシア戦争
階級問題を軸心としたマルクスの思想と理論が、民族問題の解決を射程に入れていなかったことに、ボリシェヴィキは逢着したのだ。
帝国主義と民族植民地問題において、レーニンが民族自決の原則と、その上での連邦制を主張したのに対して、スターリンはソビエト連邦への上からの吸収を主張していた。この議論が決着を見ないうちにレーニンは没する。ちなみに、米大統領ウイルソンの民族自決の原則(第一次大戦後)は、レーニンの提案を容れたものだ。
現実のソビエトは、周辺諸国の民族派を弾圧し、工業化のための農産物の供出を強要し、膨大な餓死者を強いていたのである。ちなみに、ウクライナ・ロシア戦争は1917年から足掛け5年におよんでいる。ロシアとウクライナの紛争は、いまに始まったことではないのだ。
ともあれ、ロシアにおいてはボリシェヴィキが政権をにぎり、プロレタリアートがソビエト権力を担うことになった。したがって、帝国主義の干渉にたいして「国防」が問われることになったのだ。
プロレタリアートとその党が帝国主義内部にあって、自国帝国主義を打倒する闘争に終始するのとちがい、みずから赤軍を国軍として組織して、防衛戦争を組織しなければならなくなったのだ。
レーニンがブレスト・リトウスク条約でドイツと停戦・講和し、革命政権を保ったのは、革命政権を維持する苦肉の策である。そして戦時共産主義経済と新経済政策で、ソビエト政権は農民を犠牲にした工業化をはかる。とりわけ農業地帯への締め付けは過酷だった。
そしてスターリン革命と称される第二次五か年計画の過程(1932年~)で、ウクライナの農産物は中央政府に徴発された。これは社会主義的原始的蓄積とも称され、同時に農場の集団化・国有化が行なわれた。
これをウクライナでは、スターリンのホロドモール(ウクライナ語でホロドは飢饉、モールは疫病を示す)という。それはまた、スターリンが「ウクライナ民族主義」を撲滅する過程でもあった。
◆ナチスドイツのバルバロッサ作戦
さて、前段で左翼の政策能力を問題にしたが、侵略戦争に遭遇したときほど、その政治能力の有無が問われることはない。
現在のウクライナ政権は、ロシアの侵略戦争に対して、NATOの支援頼みだとはいえ、じゅうぶんにその能力を発揮しているといえよう。はたして、ゼレンスキー政権の戦争継続を批判する日本の左翼は、自分たちが侵略戦争に遭遇したときに、どんな行動をするのだろうか。
非暴力(無抵抗)で虐殺されるのか、それとも降伏して強制移住させられるのか、ぜひとも意見を訊いてみたいものだ。スターリン麾下の革命ロシアも、第二次世界大戦に否応なく巻き込まれた。ナチスドイツの東方侵略である。
ドイツ総統アドルフ・ヒトラーは、ソビエト連邦との戦争を「イデオロギーの戦争」「絶滅戦争」と位置づけ、通常の占領政策をとらなかった。つまり、最初から虐殺のための戦争として発動したのだ。
1941年6月22日、ドイツ軍は「バルバロッサ作戦」としてソ連を奇襲攻撃した。ヨーロッパのドイツ占領地から反共主義者の志願者、武装親衛隊によって徴発された人々がドイツ軍に加わった。外交官加瀬俊一によれば、この反共討伐軍は、ヨーロッパでは人気があったという。
開戦当初、ソ連軍が大敗を喫したこともあり、歴史的に反ソ感情が強かったバルト地方や、共産党の過酷な政策からウクライナの住民は、ドイツ軍を「共産主義ロシアの圧制からの解放軍」と歓迎した。
とくに東欧の反共産主義者は、ロシア国民解放軍やロシア解放軍としてソ連軍と戦った。プーチンが「ウクライナ民族主義者たちは、ナチスに協力した」とするのは、一面では当たっているのだ。
ところが、スラブ人を劣等民族と認識していたヒトラーは、彼らの独立を認める考えはなく、こうした動きを利用しようとしなかった。親衛隊や東部占領地域省は、ドイツ系民族を占領地に移住させて植民地にしようと計画し、これらは一部実行された。
ヒトラーは『我が闘争』において、ドイツ人のための生存圏を東欧・ロシアにもとめ、ドイツ人を定住させることを構想していた。そこではドイツ人が「支配人種」を構成し、スラブ系住民のほとんどを根絶またはシベリアへ移送し、残りを奴隷労働者として使用する構想だった。
◆大祖国戦争
当時、スターリンによる粛軍によって、ソ連軍(赤軍)は弱体化していた。1941年の夏までにウクライナのキーフ、ハリコフが陥落した。ドイツ軍は9月には、モスクワ攻略作戦を発動する。最新鋭の6号戦車(タイガー)を主力にした機械化師団、ユンカース急降下爆撃機の支援で、圧倒的な戦力をほこるドイツ軍はモスクワまで十数キロに達した。ところが、この年は冬の訪れが早かった。戦車隊は雪と泥濘で進撃を止められ、戦局は膠着した。スターリンが「大祖国戦争」を呼号したのは、このときである。
アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトが、ソ連への武器供与を決断したのも、ドイツ軍のモスクワ攻囲が完成した時だった。現在のウクライナ戦争(ロシアの侵攻)とよく似ていることに気付くはずだ。
さてこのとき、左翼(共産主義者)は自国帝国主義(アメリカやイギリス)の武器供与に反対すべきだっただろうか? フランスでは共産主義者をふくむ抗独レジスタンスが、やはり米英の武器供与(空輸)を受けていた。米英の左派は、この武器供与に反対するべきだったのだろうか。史実は反ファシズム戦争として、民族ブルジョワジーから民族主義右翼、社会主義者・共産主義者がこぞって、ナチスドイツの軍事侵略に反対し、民主主義擁護の戦争に参加したのである。
このように、帝国主義戦争においては、かならず民族的な抑圧・虐殺が起きる。帝国主義間戦争のなかに、かならず反侵略の自衛戦争が生起する。このときに、自国の平和だけを唱える者はいない。少なくともマルクス主義左翼は、国際共産主義者として、抑圧民族の自衛戦争を支援・参加するはずだ。
だがなぜか、今回のウクライナ戦争において、日本の新左翼と反戦平和市民運動はそうではないという。やはり革命ロシアの記憶がプーチンを擁護させるのだろうか。それとも「戦争」という言葉それ自体に、忌避反応してしまうのだろうか。次回は民族解放戦争に論を進めよう。
◎[関連リンク]ウクライナ戦争をどう理解するべきなのか
〈1〉左派が混乱している理論的背景
〈2〉帝国主義戦争と救国戦争の違い
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。