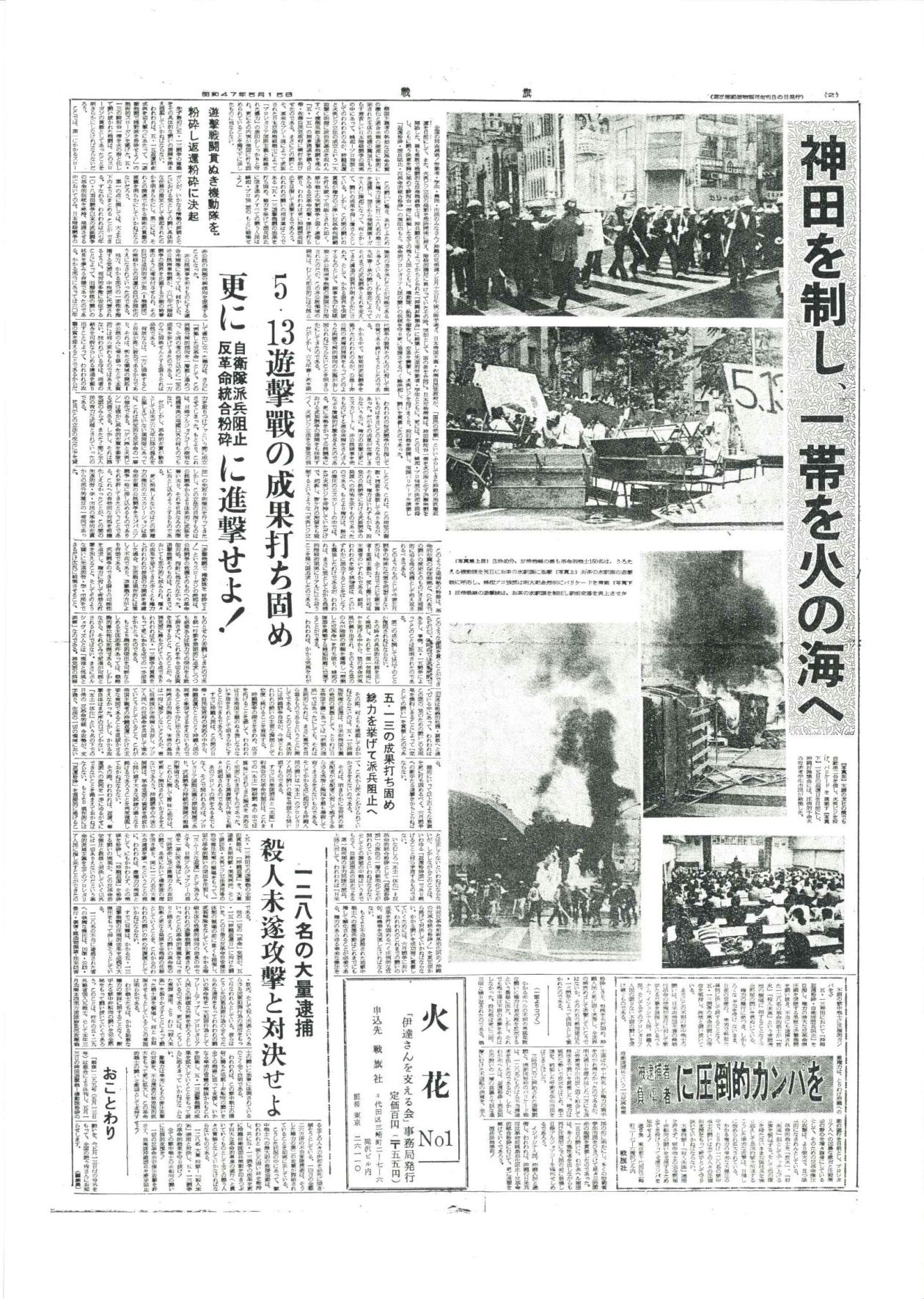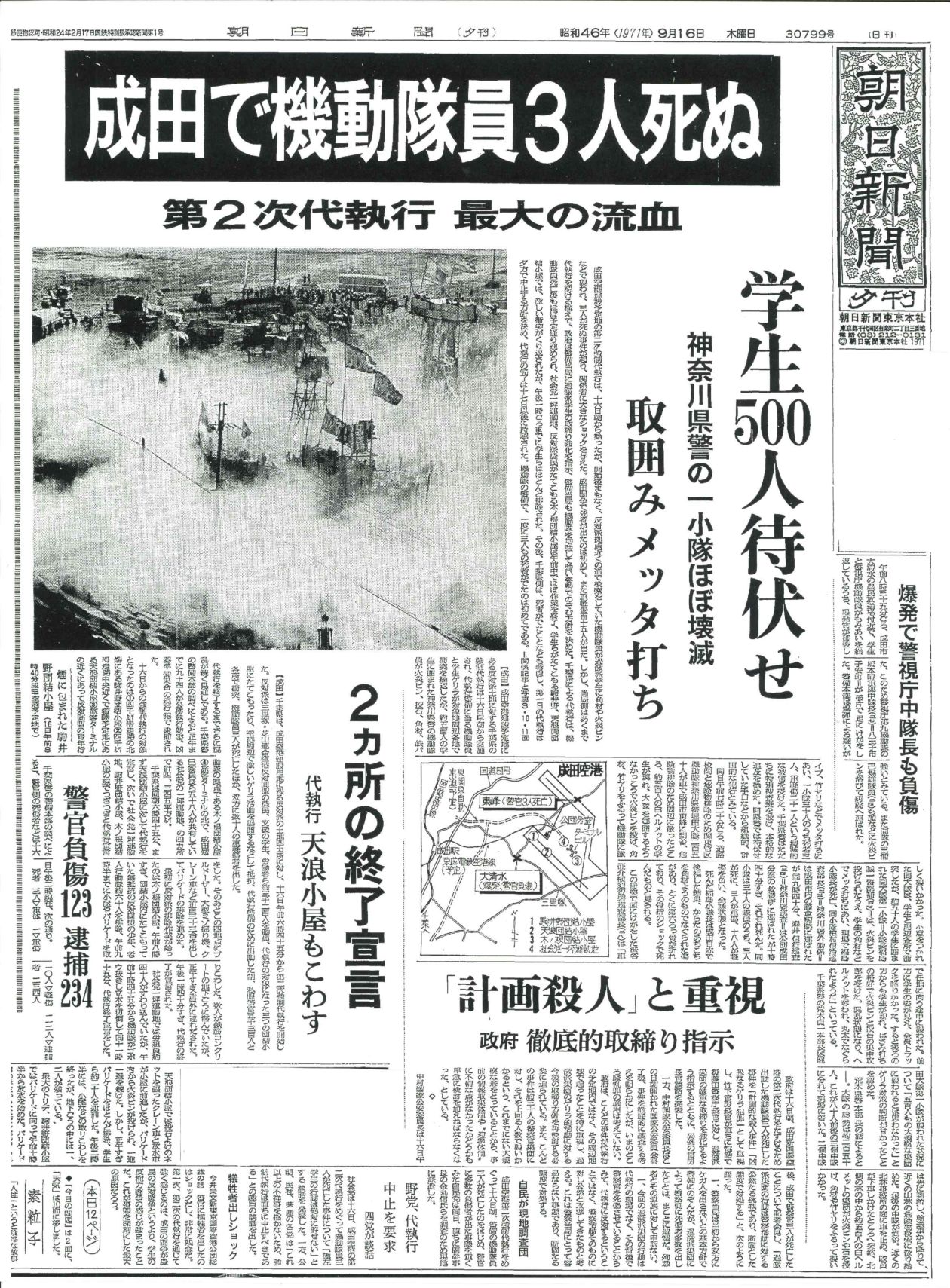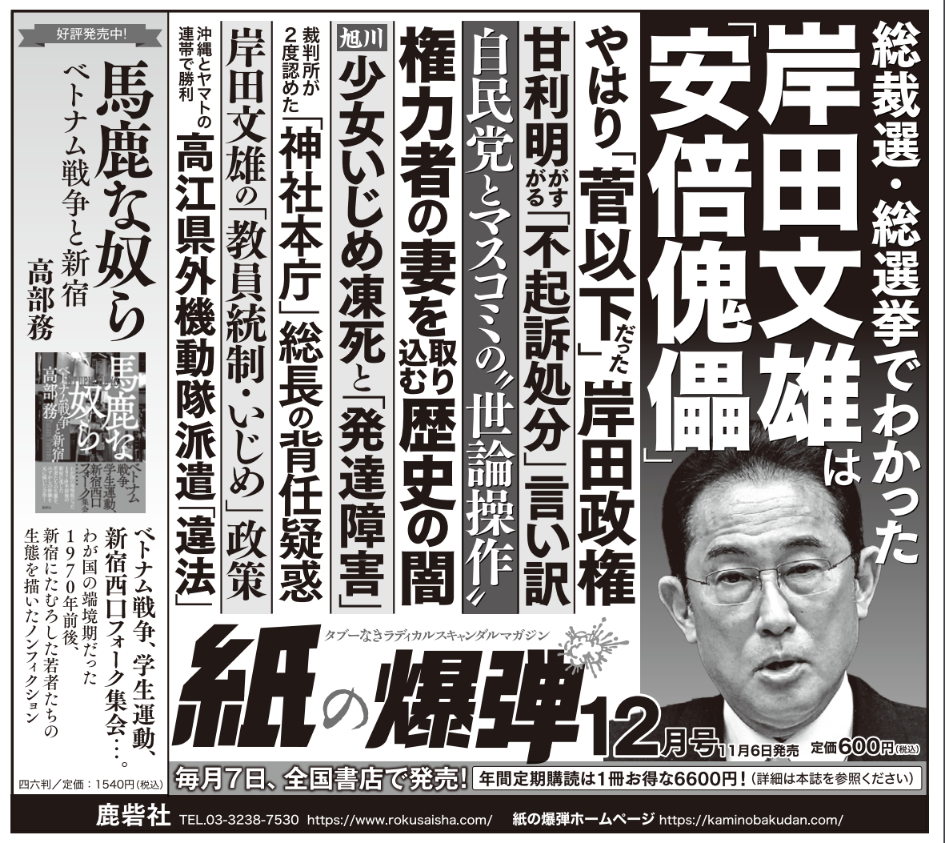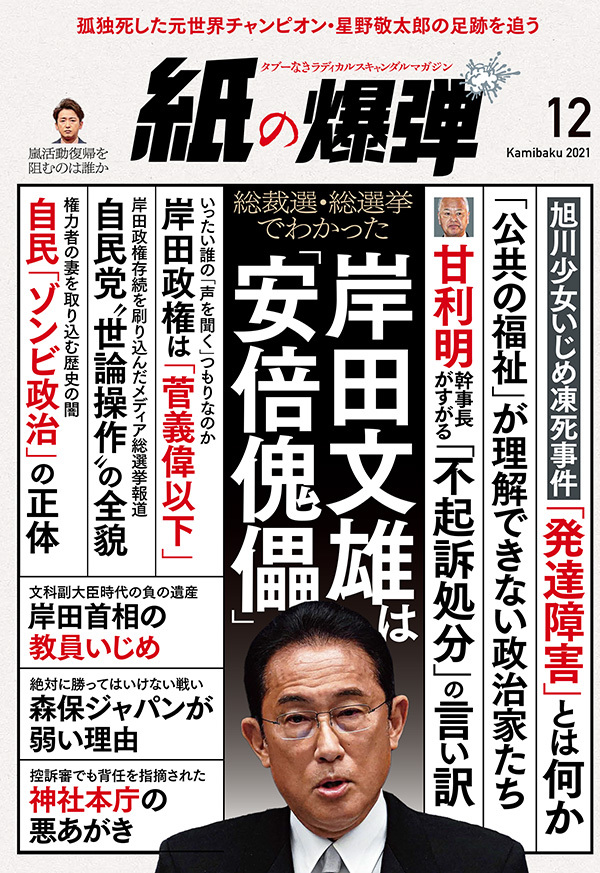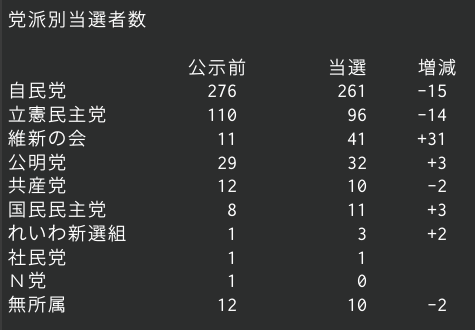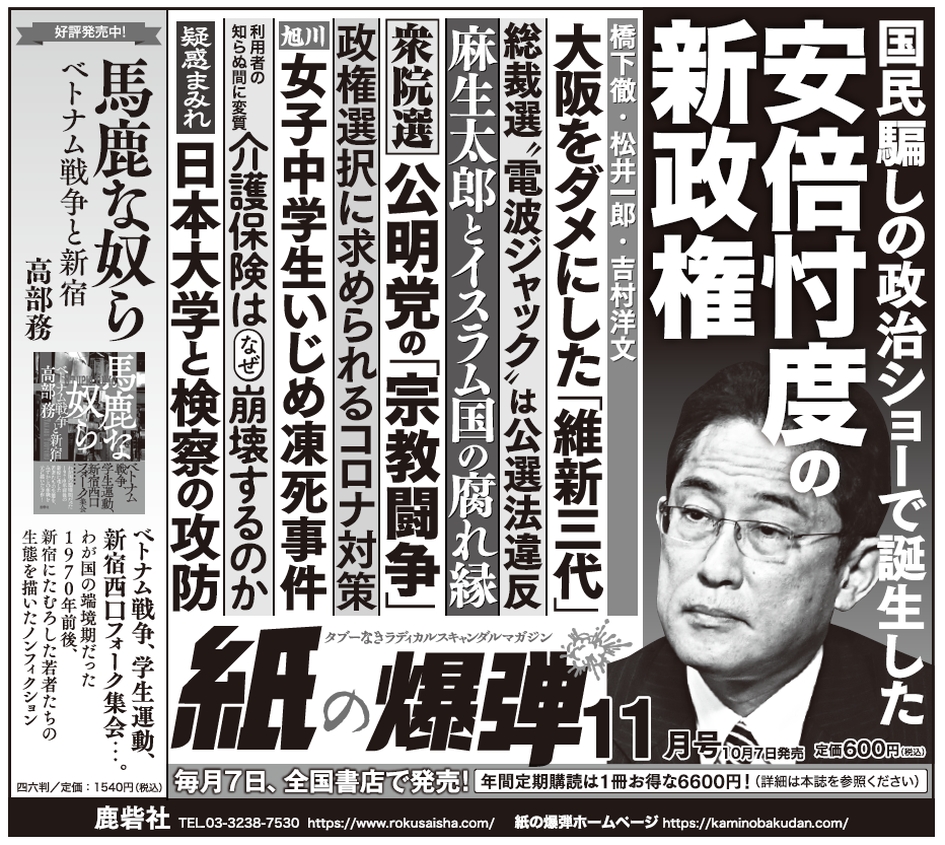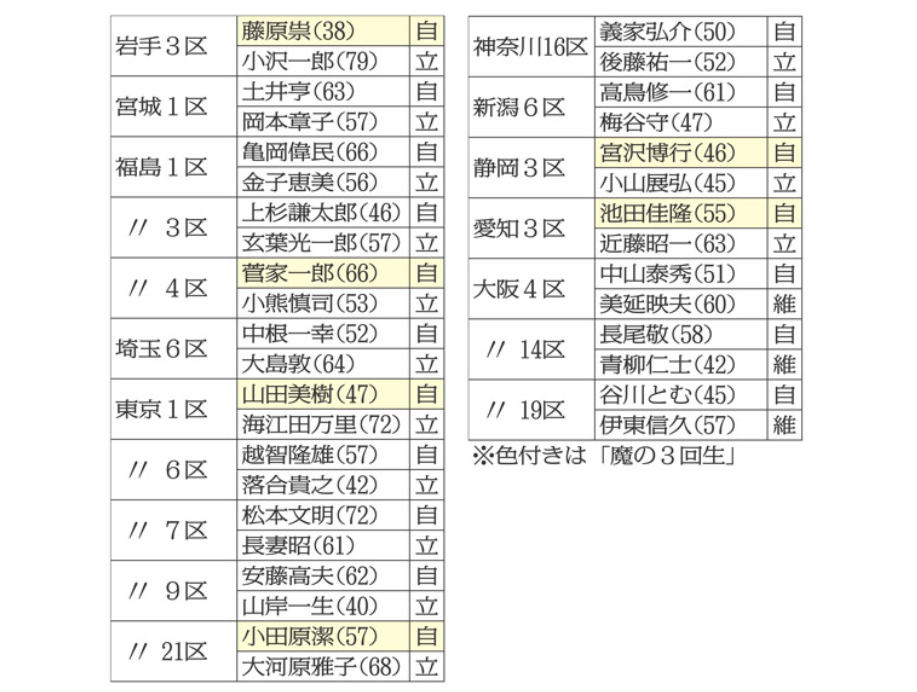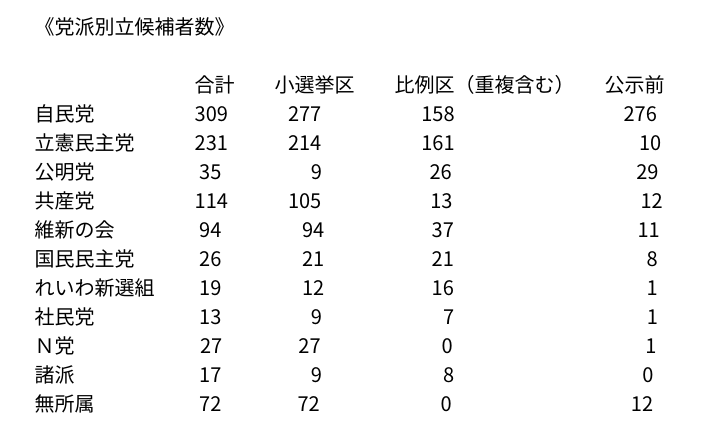『抵抗と絶望の狭間』(鹿砦社)の書評の第二弾である。
71年は学園闘争の残り火、爆弾闘争の季節であると同時に、東映と日活がポルノ路線へと舵を切った年でもあった。
高部務さんの「一九七一年 新宿」(作家・ノンフィクションライター。著書に『馬鹿な奴ら──ベトナム戦争と新宿』)によれば、東映が7月に『温泉みみず芸者』(鈴木則文監督)でピンク映画へ路線転換した。主演女優は、のちに東映スケバン映画で一世を風靡する池玲子である。
それから四カ月遅れて、日活がロマンポルノ路線をスタートさせる。第一弾は『団地妻 昼下がりの情事』(西村昭五郎監督、主演女優白川和子)と『色暦大奥秘話』(林功監督、主演女優小川節子)である。
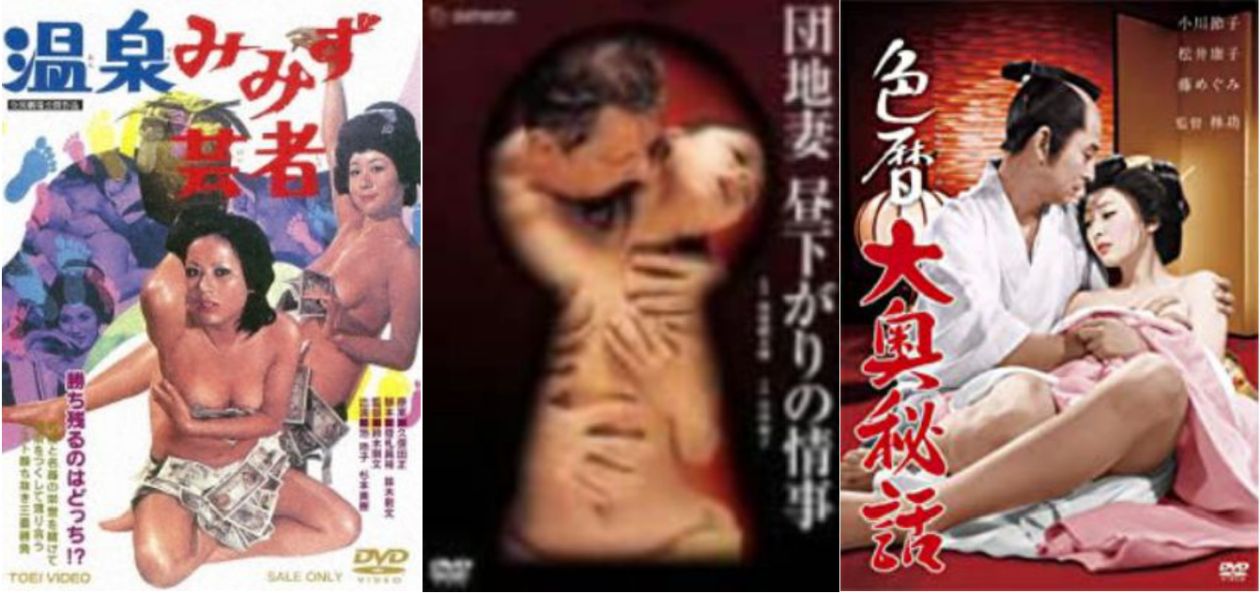
高部さんの記事には、70年代のピンク映画、ポルノ映画の裏舞台があますところなく紹介されている。
爾来、ポルノ映画はレンタルのアダルトビデオが普及する80年代初期まで、エロス文化の王道として君臨したものだ。やはり71年は戦後文化の転換点だったといえるのだろう。
わたしの記憶では、『イージー・ライダー』の日本公開が70年で、その洋画ブームの時期にスクリーンでバストの露出がOKになったと思う。ついでフランス製の性風俗ドキュメント映画『パリエロチカNo.1』の公開があって、思春期のわれわれはフランスのエロスに驚いたものだ。そして海外ポルノの浸食。
その意味では海外作品によって、71年のポルノ路線は道がひらけていたというべきであろう。68年公開の『卒業』(ダスティン・ホフマン主演)では、アン・バンクロフト(恋人の母親)の色っぽいシーンがコラージュのようになっていたものだ。
引用したのはDVDのパッケージだが、映画館のポスターや看板(手描き)はバスト露出がなく、公序良俗が守られていたようだ。
◆SM小説の黎明
板坂剛さんの「一九七一年の転換」によれば、三島由紀夫が団鬼六の『花と蛇』を絶賛したという。覆面作家沼昭三の『家畜人ヤプー』を激賞した三島なら、当然の評価であろう。羞恥と悦楽に苦悶する美女、緊縛という肉刑は三島にとってど真ん中の素材であっただろう。
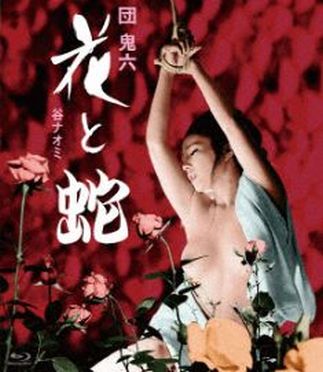
その団鬼六は教員時代に、63年ごろからSM小説を書きはじめ、70年には芳賀書店から『天保女草紙耽美館』を、71年には同じく芳賀書店から『団鬼六SM映画作品集 1-2 耽美館』を出版している。ちなみに芳賀書店は、小山弘健やいいだもも、滝田修ら新左翼系の書籍を出版していた版元で、新左翼とエロスの親和性の高さを、何となく反映しているような気がする。
したがって団鬼六は、もう71年には谷ナオミ主演映画の原作者として、確固たる地位を占めていたことになる。じつは谷ナオミのデビュー前から、彼女を買っていたという。
その谷ナオミと吉永小百合を、板坂さんは「この時代の二大女優」だと評している。わたしもそれには賛成だ。ちなみに、谷ナオミの芸名は、谷崎潤一郎の「谷」と彼の作品『痴人の愛』のヒロイン「ナオミ」との組み合わせとされる。いかにも60・70年代らしい、文芸エロスである。
板坂さんによれば、全共闘世代の大半がサユリスト(吉永小百合ファン)だったという。三島は『潮騒』に出演した吉永小百合を「清純なピチピチした生活美の発見」と評し、戦前の薄幸な肺病型の美人との対比を強調している(本文での引用)。ここに板坂さんは「一九七一年の転換」をみるのだが、非常に興味深いのは、吉永小百合と谷ナオミの類似点である。それは女優としては陽と陰でありながら、純真無垢な目つき顔つきだという。
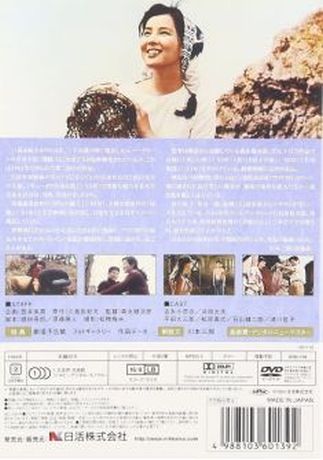
なるほど、吉永小百合の清廉な健康美にたいして、谷ナオミは大きな乳房に象徴される肉体美であろう。そして純真無垢というのはおそらく「穢される美」なのではないだろうか。
吉永小百合を穢すものは、スクリーンに描かれる社会的かつ日常生活の困難であり、谷ナオミを穢すのはサディズムとマゾヒズムの凌辱である。
とくに谷ナオミの場合、高貴な財閥夫人が凌辱される被虐の美は、いかにも戦後的なロマンだが、そこに若々しい戦後日本の欲望と活力を見ることができる。ハードなSM小説が読まれなくなり、男たちがむき出しの欲望をなくした今は、日本の衰退期なのかもしれない。むしろコロナ禍の不況は吉永小百合的な、日常生活の困難があたらしい女優をもとめるのかもしれない。
ところで、吉永小百合と谷ナオミの両者を分けるのは、バストの大きさだと板坂さんは指摘する(笑)。女優でありながら早稲田の文学部を卒業した知性派の吉永小百合と、肉体派という表現が最もふさわしい谷ナオミのどちらが、みなさんは記憶に残っているでありましょうか。また、若い人たちはどう感じますか?
◆炸裂する板坂節
前回の書評が長くなりすぎた関係で、扱えなかった板坂剛さんの対談シリーズは今回も健在だ。
『一九六九年 混沌と狂騒の時代』の日大闘争左右対決は、両者が高校時代の同窓生だったこともあって「話はもういいから、外に出て決着をつけようか」など、とくに秀逸だったが、今回は相手が民青だった人である。面白さ爆裂にならないはずがない。
この元民青氏は6.11(最初の右翼との激突)の現場にいて、全共闘のバリケードづくりをともに担いながら、なぜか闘争の渦中に民青に転じるという異例の経歴をもっている。しかも父親の会社を継いで、社長として人生を乗りきってきたという。
マジメな話もしている。ちょっと引用しよう。
S 「僕の価値観からすれば、日大全共闘は正しいと評価するけど、東大全共闘は間違っていたと評価する。従って日大が東大に行ったことは間違っていたという方程式が、僕の頭の中では成立しているんだ」
板坂「一応筋は通っているね。もう今後は日大も東大もひっくるめて『全共闘運動はああだったこうだった』っていう論じ方はやめて欲しい」
視点はともかく、これはわたしも正しいと思う。雑誌で日大闘争の特集をやったさいに、元日大生から言われたものだ。「三派系の学生は六大学が主流だから、地方出身者が多いでしょう。日大全共闘は、そうじゃないんです。日大は東京の学生が多いですからね、慶応や一橋、東京四大学の入試で落ちた人たちが、日大全共闘には多いんですよ」
おそらく地方出身者(六大学+中大)には、この「東京四大学」が何のことなのか、わからないであろう。旧制7年制高校、もしくは財閥系の大学。ということになる。具体的には、武蔵大学(東武財閥)、成蹊大学(三菱財閥)、成城大学(地元財閥)、そして学習院大学(旧華族系)の四大学である。この四大学は野球にかぎらず、年に一度の体育会の対抗戦をやっている。※関西では甲南大学が旧制7年制で、東京四大学と提携した学生募集活動を行なっている。
この四大学には入れなかったが、すこし裕福な家庭の子弟が入学したのが日本大学なのである。そして、そのあまりにもマスプロで劣悪な教育施設(教室に募集人員が入りきれない)に愕き、憤懣をかかえていたところに、不正問題(使途不明金)が発覚したのだ。
最初はひとにぎりの活動家たちの蹶起に、ふつうの学生が賛同してこれに参加した。どちらかというと、秩序派のむしろ右翼的な発想を持っていた学生たちが参加したからこそ、地をゆるがす巨万のデモが実現されたのである。
いっぽう、東大闘争の発端は医学部の処分問題であり、医学部の主流派はブント(社学同)。駒場はフロント(社会主義学生戦線)が教養部自治会の執行部、そして文学部自治会が革マル派。駒場反帝学評(社青同解放派)も勢力を持っていた。ようするに、最初から党派活動家による闘いだったのだ。
全共闘運動は全国に波及したが、バリケード闘争は日大闘争と東大闘争の真似事にすぎない。したがって、雑誌のキャッチを「全共闘運動とは日大闘争のことである」に決めたのだった。その位相は、板坂さんとSさんの論調にも顕われているといえよう。(つづく)
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。3月横堀要塞戦元被告。
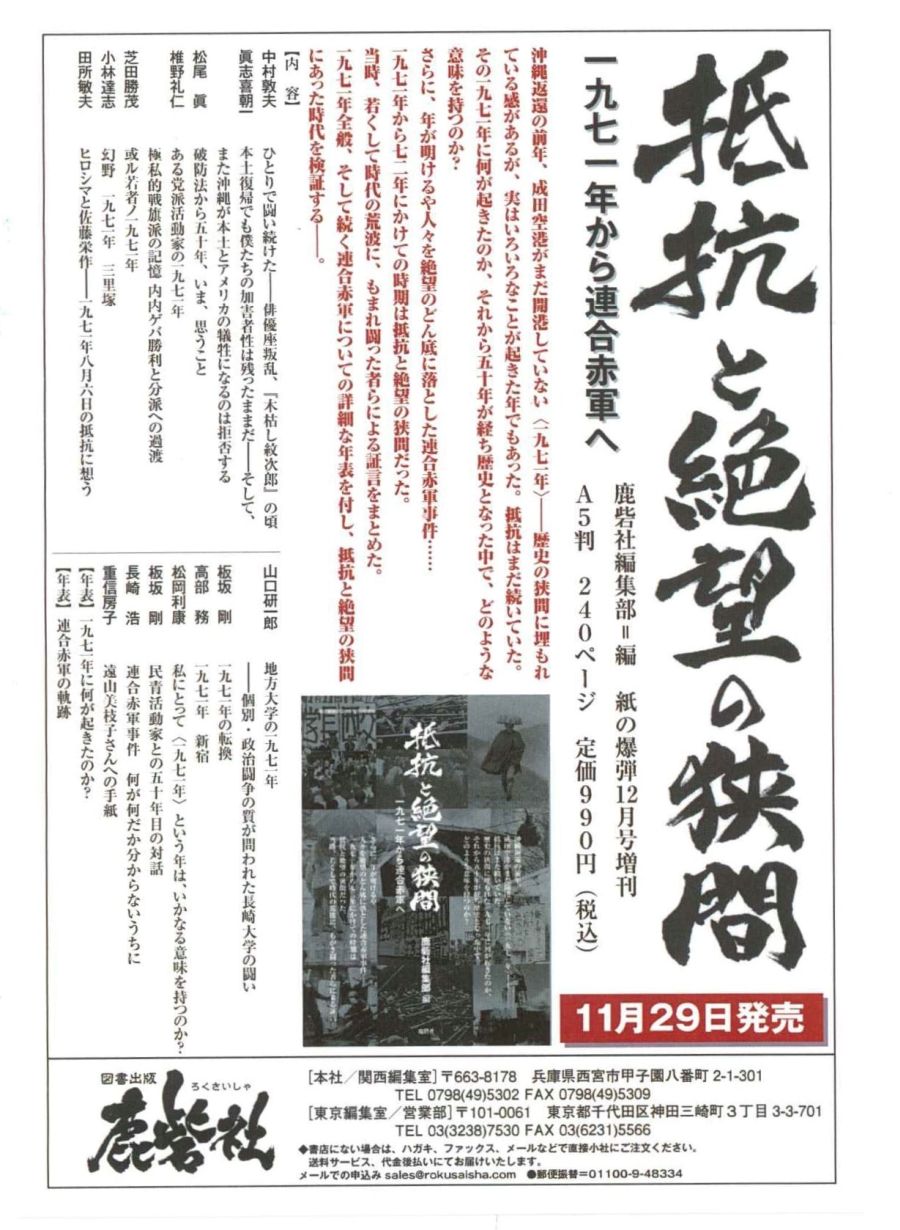
紙の爆弾12月号増刊
2021年11月29日発売 鹿砦社編集部=編
A5判/240ページ/定価990円(税込)
沖縄返還の前年、成田空港がまだ開港していない〈一九七一年〉──
歴史の狭間に埋もれている感があるが、実はいろいろなことが起きた年でもあった。
抵抗はまだ続いていた。
その一九七一年に何が起きたのか、
それから五十年が経ち歴史となった中で、どのような意味を持つのか?
さらに、年が明けるや人々を絶望のどん底に落とした連合赤軍事件……
一九七一年から七二年にかけての時期は抵抗と絶望の狭間だった。
当時、若くして時代の荒波に、もがき闘った者らによる証言をまとめた。
一九七一年全般、そして続く連合赤軍についての詳細な年表を付し、
抵抗と絶望の狭間にあった時代を検証する──。
【内 容】
中村敦夫 ひとりで闘い続けた──俳優座叛乱、『木枯し紋次郎』の頃
眞志喜朝一 本土復帰でも僕たちの加害者性は残ったままだ
──そして、また沖縄が本土とアメリカの犠牲になるのは拒否する
松尾 眞 破防法から五十年、いま、思うこと
椎野礼仁 ある党派活動家の一九七一年
極私的戦旗派の記憶 内内ゲバ勝利と分派への過渡
芝田勝茂 或ル若者ノ一九七一年
小林達志 幻野 一九七一年 三里塚
田所敏夫 ヒロシマと佐藤栄作──一九七一年八月六日の抵抗に想う
山口研一郎 地方大学の一九七一年
──個別・政治闘争の質が問われた長崎大学の闘い
板坂 剛 一九七一年の転換
高部 務 一九七一年 新宿
松岡利康 私にとって〈一九七一年〉という年は、いかなる意味を持つのか?
板坂 剛 民青活動家との五十年目の対話
長崎 浩 連合赤軍事件 何が何だか分からないうちに
重信房子 遠山美枝子さんへの手紙
【年表】一九七一年に何が起きたのか?
【年表】連合赤軍の軌跡
◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B09LWPCR7Y/
◎鹿砦社 http://www.rokusaisha.com/kikan.php?group=ichi&bookid=000687