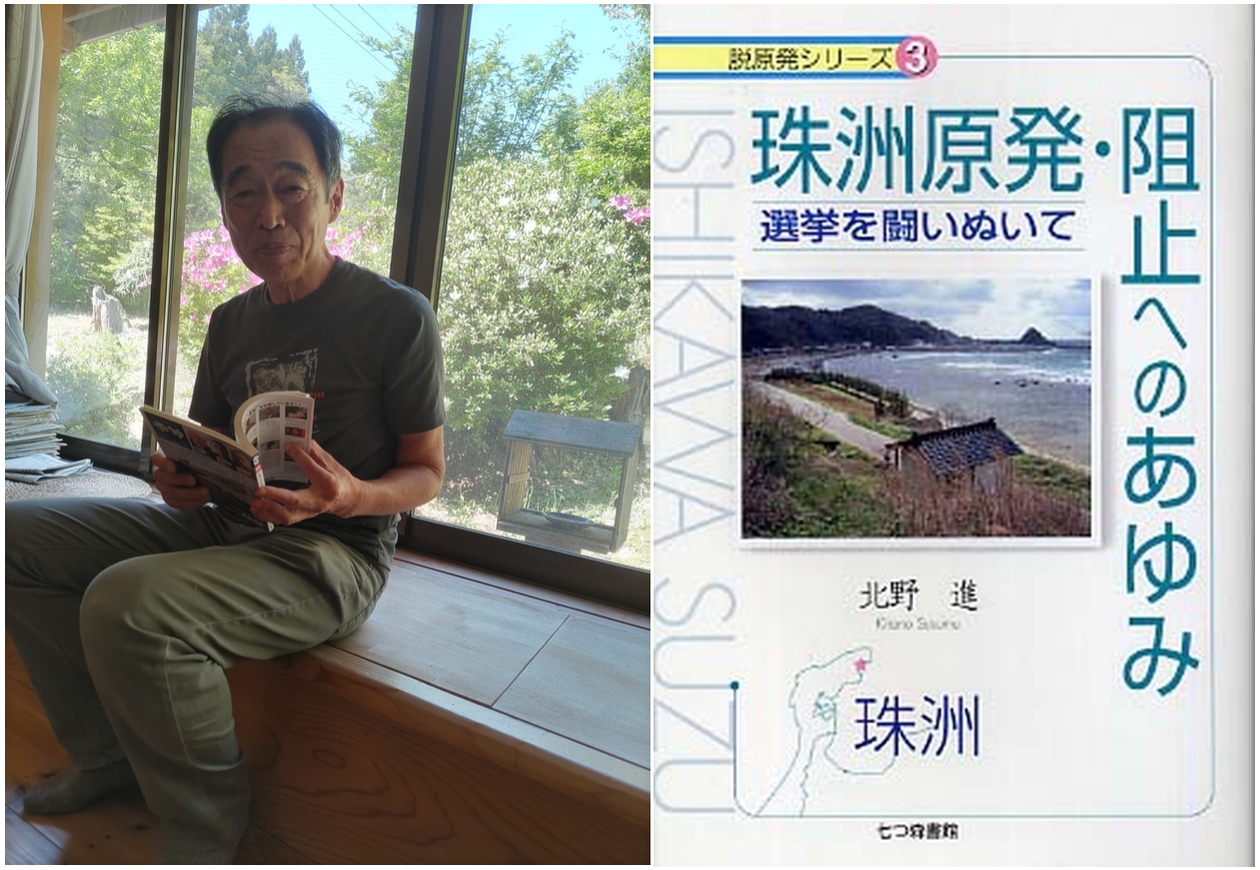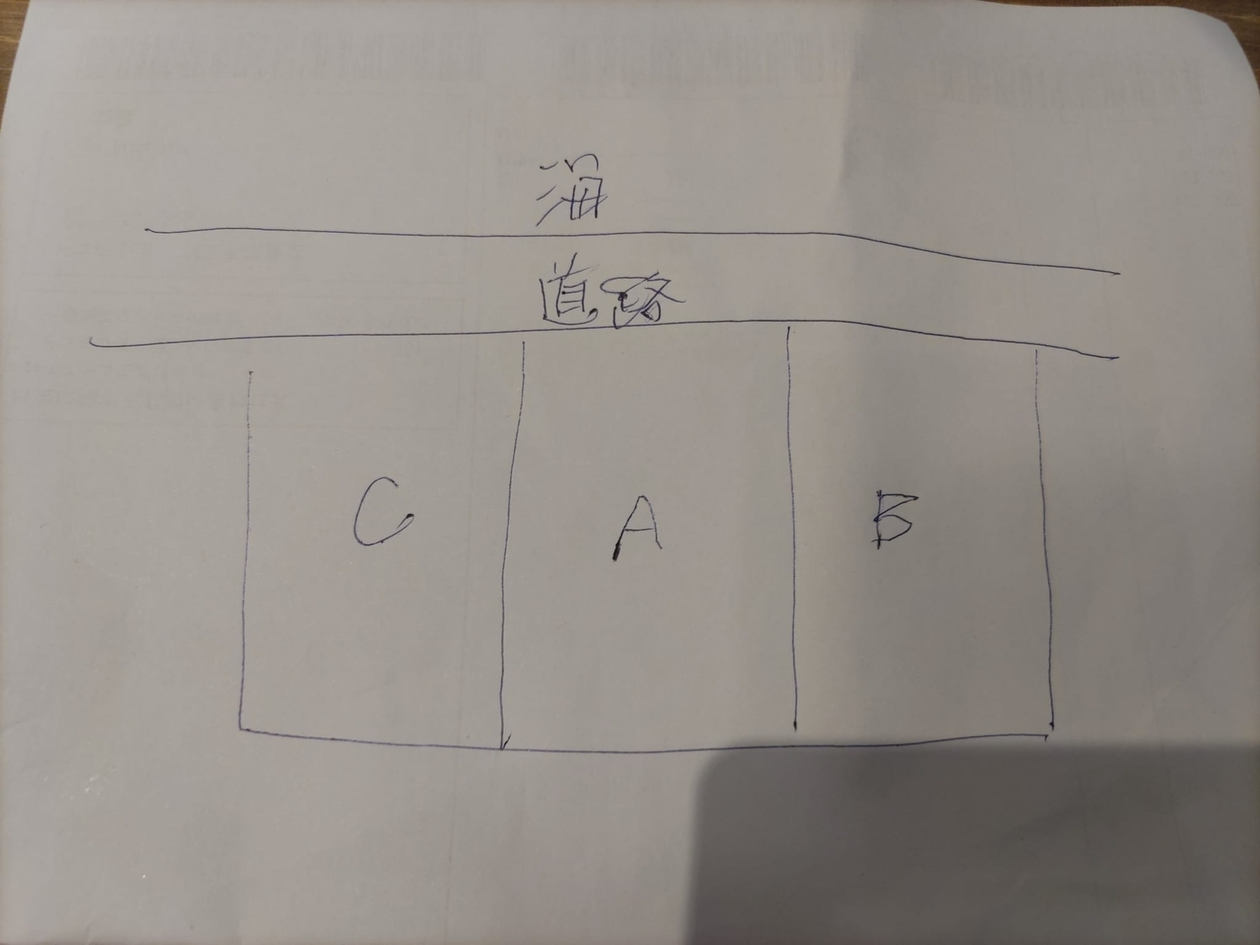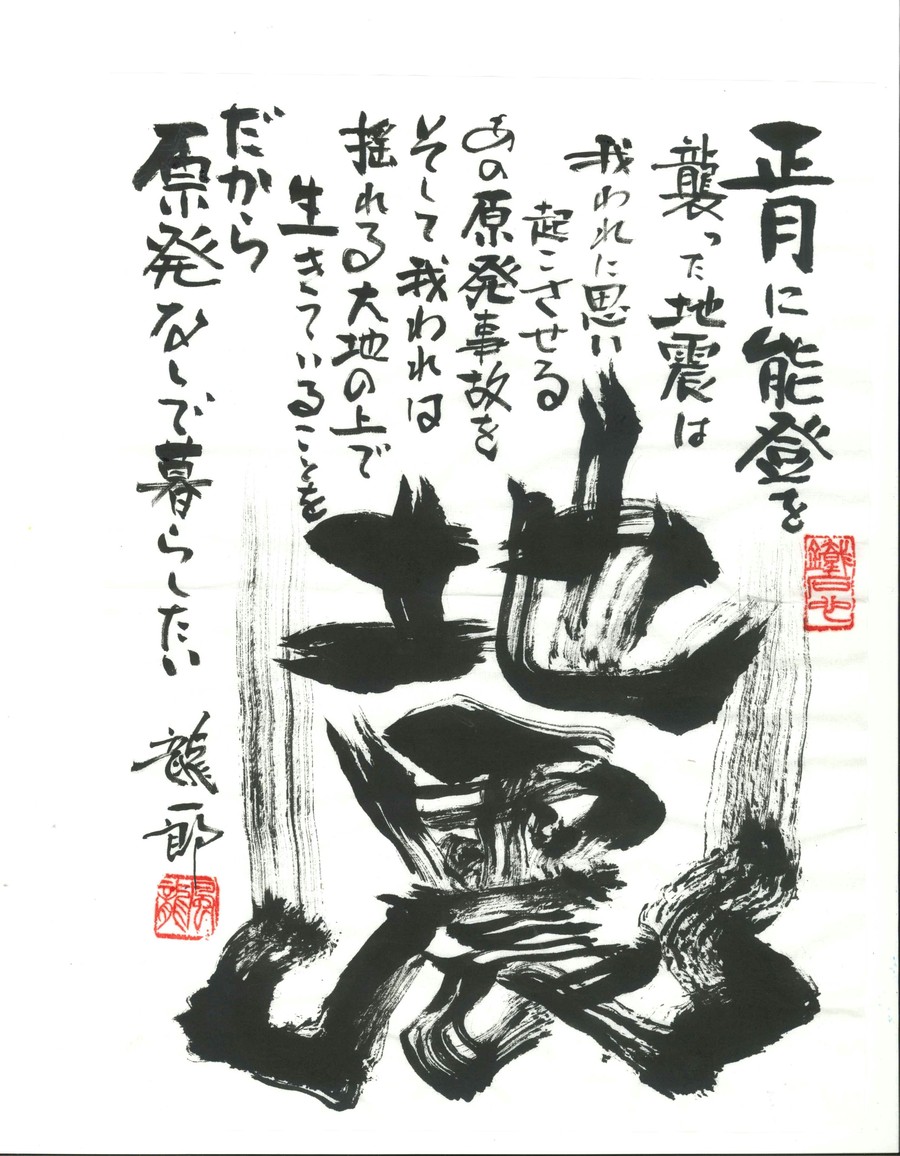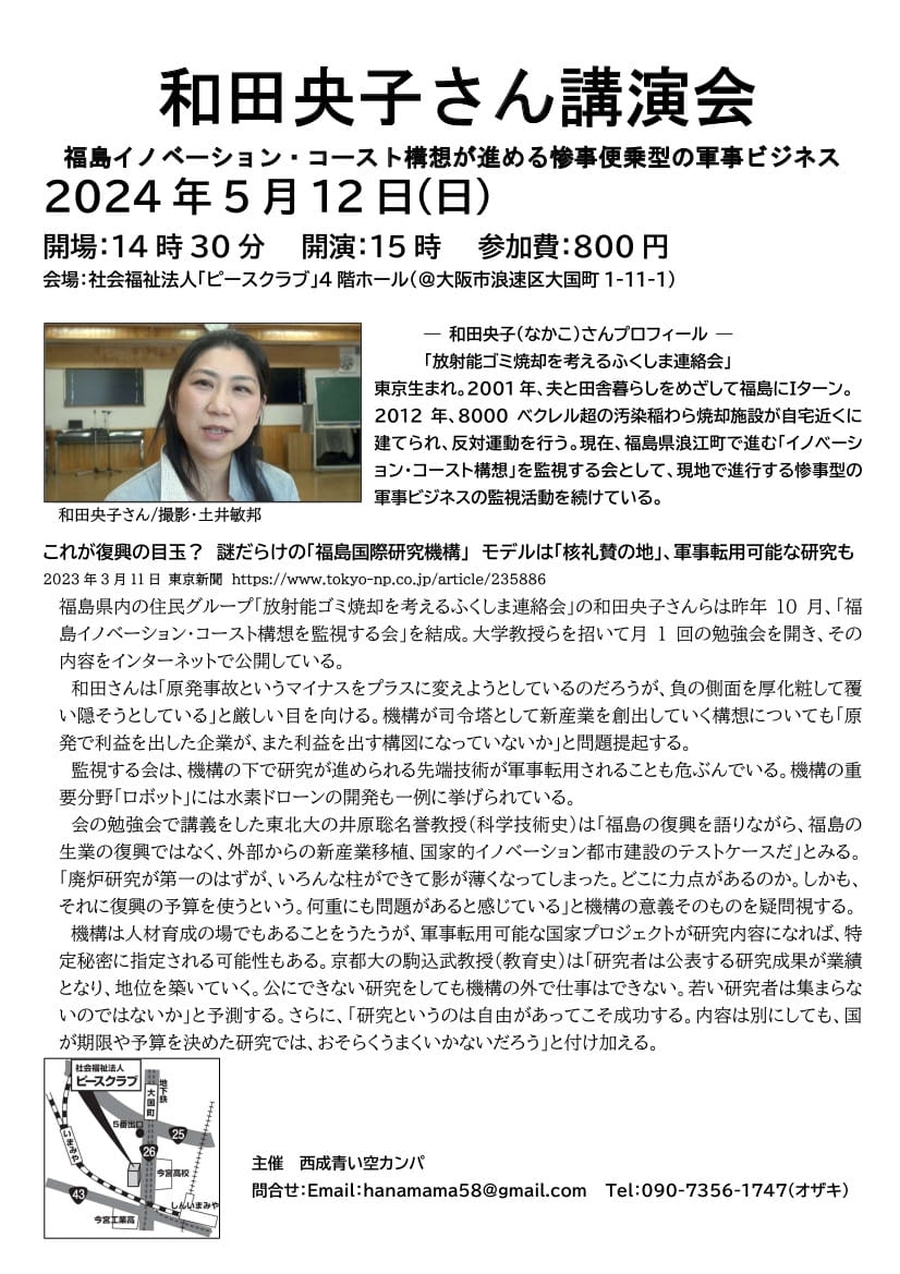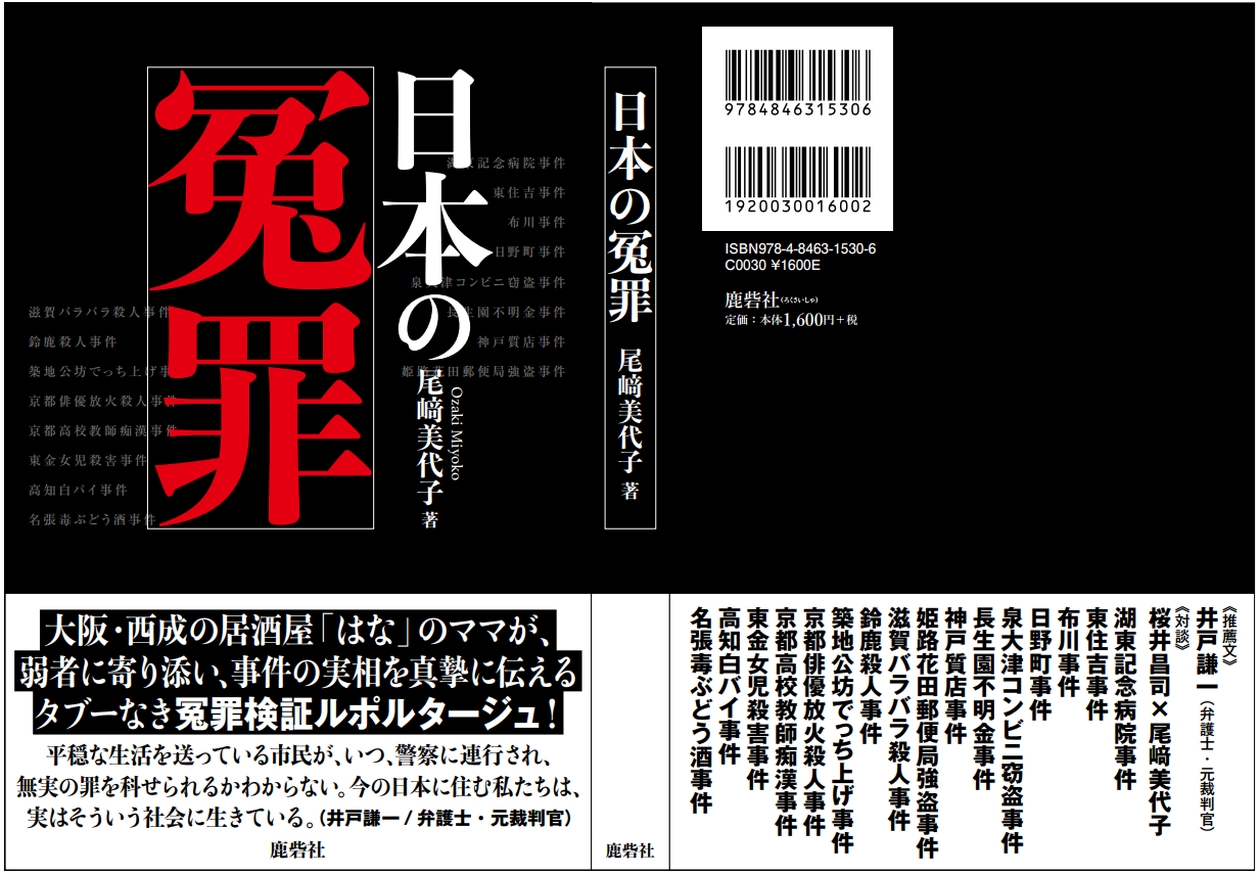◆はじめに──「挙国一致」の目標と化した「脱炭素」
斎藤幸平の『人新世の「資本論」』(集英社新書)がベストセラーとなっている。斎藤は化学者のパワル・クルッツェンにならって人間の活動が地球の表面を覆いつくした時代として現代を「人新世(じんしんせい)」と名付ける。「人新世」では、とりわけ大気中の人為的CO2の増大による温暖化が気候危機をもたらしているとして警鐘をならす。そして晩年のマルクスの思想を「脱成長コミュニズム」と読みとり、危機からの脱出口とする。
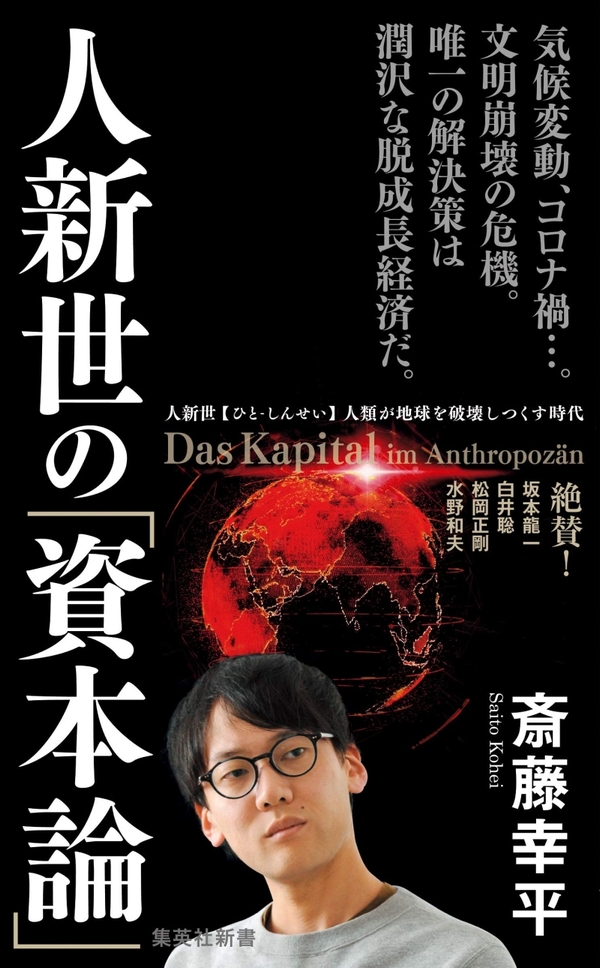
最近、斎藤のように「人為的CO2温暖化説」による「気候危機」への対応として、「脱炭素」が「挙国一致」の目標となっている。昨年10月には菅義偉首相が所信表明演説で、CO2など温質効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにすると宣言した。これをうけて11月衆参両議院が全会一致で「気候非常事態宣言」を採択。「1日も早い脱炭素社会の実現をめざす」とした。
そして、CO2を多く発生させるとされる石炭火力発電の建設中止を求める市民運動が拡がる一方で、政府や電力会社は運転中はCO2を発生しないとされる原発再稼働や新型小型原発開発を推進する。
また、環境破壊の著しいメガソーラーや風力発電の拡大が待望されている。「人為的CO2温暖化説」やそれによる「気候危機」は正しいのか、また、それににもとづく対策は「脱成長コミュニズム」と言えるのか。原発廃絶との関連から本書を読み解きたい。
◆SDGsは独占資本のビジネスチャンス
国連はSDGs(持続可能な開発目標)としてクリーンなエネルギーや気候変動対策を掲げ2030年までの達成をめざす。これに対して斎藤幸平はSDGsは現代版「大衆のアヘン」であると批判して「政府や企業がSDGsの行動指針をいくつかなぞったところで気候変動はとめられないのだ。SDGsはアリバイ作りのようなものであり、目下の危機から目を背けさせる効果しかない」(P4)と述べる。
SDGsが経済成長の持続であり、環境危機を救わないとの斎藤の主張には共感できる。連日、日経新聞などに掲載されるSDGs推進の記事をみると、まさにCO2削減を口実にしたビジネスチャンスとして資本が歓迎していることは明白である。政府や独占資本はSDGsが儲かるものだからそれを推進するのである。
SDGsはもともと「気候危機」を止めるためではなく「目下の危機」を利用して独占資本の利益を拡大することを目的に推進されている。
◆「人為的CO2温暖化説」に科学的根拠はあるか
斎藤はSDGsを批判するが、SDGsの根拠である「人為的CO2温暖化説」(以下、「CO2説」)を十分に検討することもなく、「気候危機」への対策を求める。「CO2説」はパリ協定(国連気候変動枠組条約第21回国際条約会議=COP21で採択)やIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の提言である。
しかし「CO2説」は「科学的根拠が薄弱なまま政治的に引き回されている」(小出裕章『隠される原子力核の真実』)。まずCO2はそれ自体としては人類に有害ではないし、植物にとってはむしろその成長を促す物質であることを押さえておきたい。確かに19世紀後半以降、温暖化の傾向はみられる(150年間で1度程度の上昇)が、地球はこれまで寒冷化と温暖化を繰り返してきた。
斎藤は「二酸化炭素濃度が南極でも400PPMを超えてしまった。これは400万年ぶりのことで400万年前の『鮮新世(せんしんせい)』の平均気温は現在よりも2~3度高かった」(P5)とのべる。400万年前は人類が存在いたかどうかも疑わしいので、もちろん「CO2説」とは無関係である。
斎藤の指摘は地球の歴史で気温の高いときにCO2の濃度も高いという事実にすぎない。温暖化により海洋に溶けていたCO2が大気中に放出される結果、CO2が増大するのである。「CO2説」は原因と結果を取り違えている(近藤邦明『温暖化の虚像』電子書籍)
◆「人為的CO2温暖化説」と「気候危機」に関係はない
斎藤は「CO2説」の結果、気候変動により近年の自然災害が起こっているとするが、「CO2説」が成り立たない以上、気候危機とは無関係である。そして近年自然災害が増大しているかについても十分な検証が必要である。
例えば、斎藤は、温暖化により「台風の巨大化は一層進む」(P21)と述べるが、池田清彦は「気象庁のデータを全部調べてみたが、日本では台風の数は傾向として徐々に減っているし、大きさも小さくなっているし、被害総額も昔の方がうんと大きかった」(池田清彦『環境問題の嘘 令和版』)と述べる。斎藤はデータに基いて「気候危機」を論ずるべきであった。(つづく)
本稿は『NO NUKES voice』(現・季節)29号(2021年9月9日発売号)掲載の同名記事を本通信用に再編集した全2回の連載記事です。
▼大今 歩(おおいま・あゆみ)
高校講師・農業。京都府福知山市在住