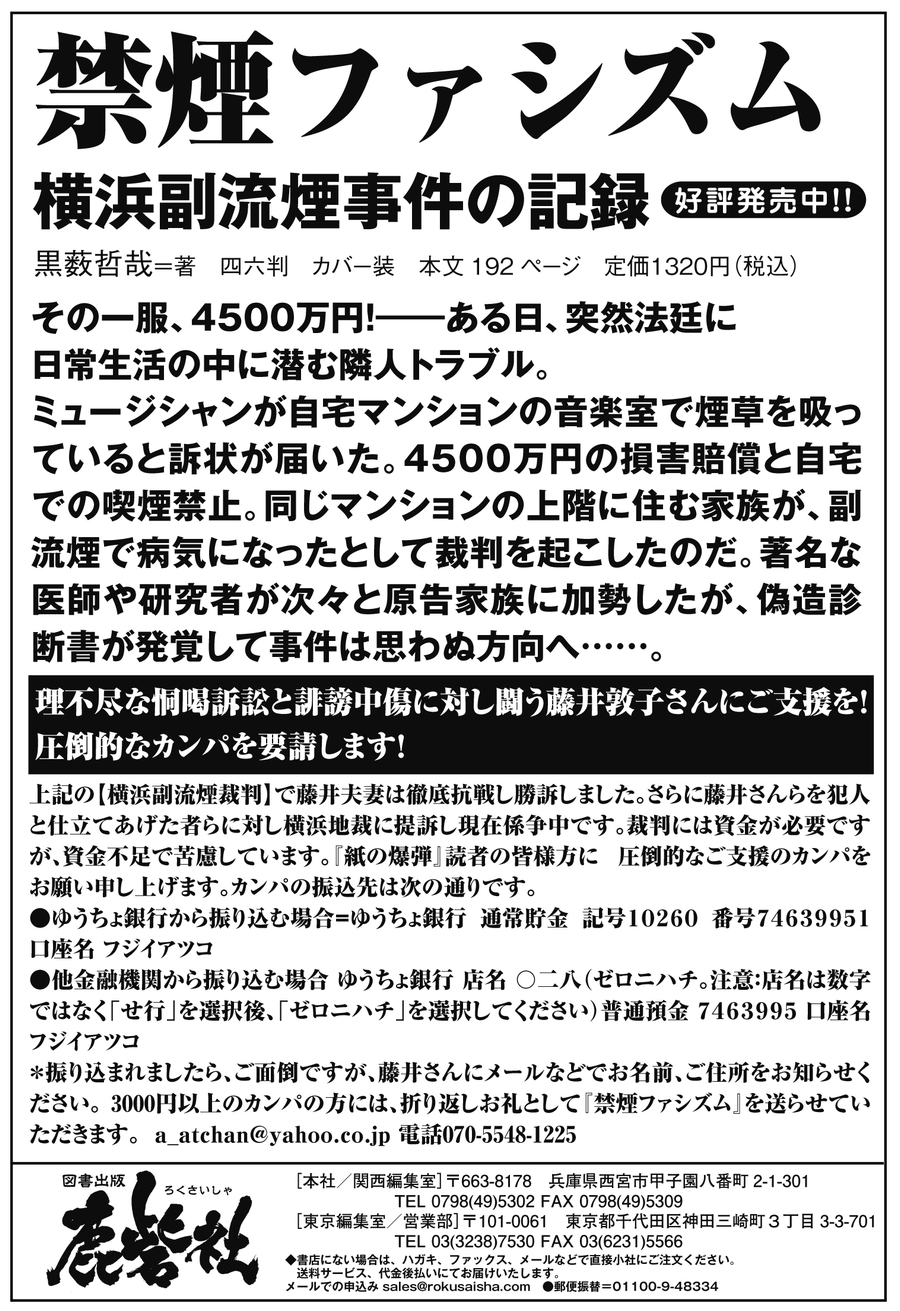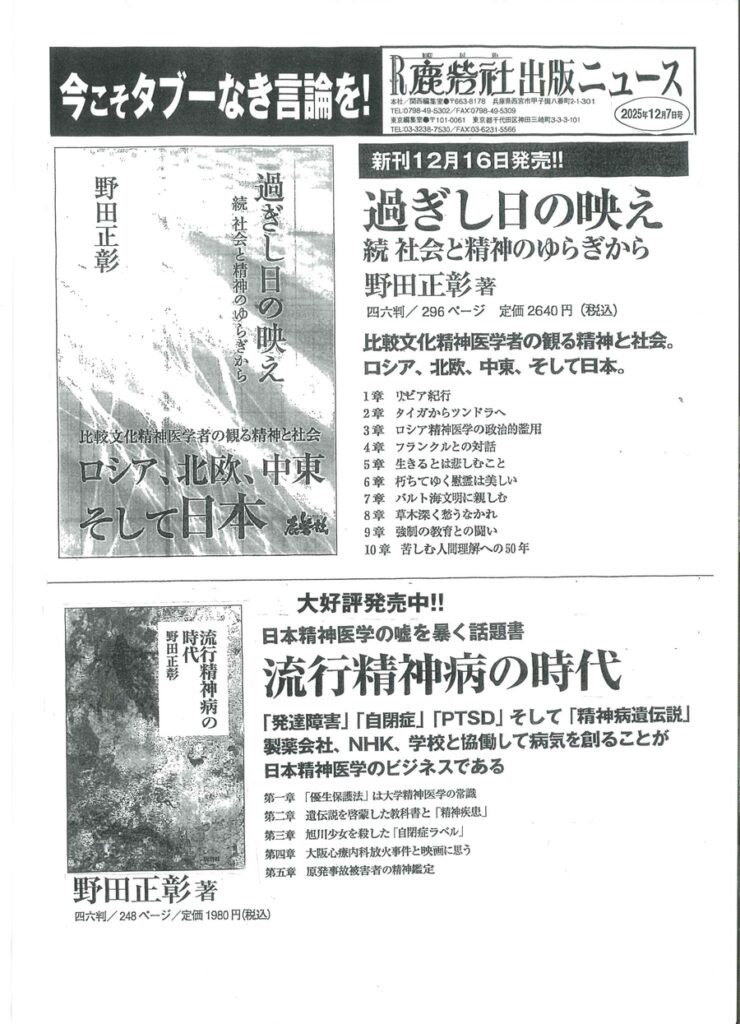江上武幸
近時、弁護士が依頼者の金銭を横領する事件が多発しています。また、弁護士事務所の法人化、支店の設置、広告宣伝の自由化により、相談料無料・着手金無料をうたったホームページが多く見られるようになりました。日本版アンビュランス・ローヤーの出現という問題です。
(注:アンビュランス・ローヤーとはアメリカの俗語で、交通事故などの被害者が乗った救急車(ambulance)を追いかけ、病院で動揺している被害者やその家族に接触し、損害賠償請求の訴訟を持ちかけて依頼を得ようとする弁護士たちを指す言葉です。基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする日本の弁護士制度にはなじみません。)
検察関係では、証拠の捏造や改ざん・隠ぺい、検事正による女性検事への性加害事件や、検事総長就任予定者による新聞記者との賭けマージャンなど、信じがたい事件が起きています。
※京大卒業で検事に任官したクラスの友人が、6年目にして将来の出世コースに乗っているかどうかが分かってきたと話してくれたことは以前述べた通りです。実は私も、長兄が警視庁に勤務していたこともあり、検事を志望していた時期がありました。しかし、指導教官から任官の誘いを受けたことは一度もありませんでした。高校時代にベトナム反戦ビラを正門前で配ったことがあったからでしょうか。
裁判官の世界では、袴田事件に見られるような、無実の人間に対する死刑判決をめぐる再審無罪や、がんに罹患している無実の被疑者の保釈請求が却下されたことによる病死、退職後の裁判官の大手弁護士事務所への再就職問題など、裁判官への信頼を大きく揺るがす状況が見られます。
※(元)法務大臣の河井克行氏は、2008年に『司法の崩壊-新弁護士の大量発生が日本を蝕む』(PHP研究所)を出版しています。
河井氏は2019年9月11日に法務大臣に就任しましたが、同年7月の参院選をめぐる運動員買収の疑惑により、2020年6月に逮捕され、2021年に懲役3年の実刑判決を受けて収監されています。就任後まもない2019年10月31日付で辞任しており、週刊誌報道から辞任、さらに逮捕・実刑判決に至る経緯は、法務大臣経験者に対する刑事処分としては異例に見えます。自民党の裏金議員に対する検察の対応の甘さと比べると、その差は際立っています。
そのため、河井氏が法務大臣として司法制度改革の見直しを言い出しかねないことを危惧した勢力が背後にいたのではないかと考えざるを得ません。
「存在が意識を決定する。」という言葉が、ずっと気になっています。自分が新聞社側の代理人であったら、検事であったら、裁判官であったら、という考えが頭をよぎることがあります。生まれたときの人間の脳はまっさらです。その後の体験と学習の積み重ねによって脳細胞同士がつながり脳が発達していきます。生まれ育った環境や受けた教育、労働・社会体験の有無や内容によって、ひとりひとりの脳が異なっていくのは自然なことです。
*家族や親せき、近所の人たちから戦争体験の話が聞けた機会があった世代や、読書好きで戦争文学を読んだことのある世代は、なんとか戦争を肌で感じることができるかもしれません。しかし、戦争のない時代に生まれ育った人間が(私もその一人です)、戦争の恐怖・残酷さ・悲惨さを感じ取るには、教育の力によるしかありません。
先の戦争の歴史を教える教育がなされたのは、朝鮮戦争が始まるまでのほんのわずかな期間でした。1947年発行の文部省『あたらしい憲法のはなし』は、1950年の朝鮮戦争勃発を機に使用されなくなりました。
1947年8月2日、当時の文部省は、同年5月3日に施行された日本国憲法を解説するため、新制中学校1年生用社会科の教科書として『あたらしい憲法のはなし』を発行しました。その教科書で平和主義、戦争(戦力)放棄条項について、中学生に向けて次のように呼びかけています。
「こんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでしょうか。何もありません。ただ、おそろしいことがたくさんおこっただけではありませんか。戦争は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。」(ウィキペディアより)

漫画家・中沢啓治氏の原爆劇画『はだしのゲン』が学校の図書館から姿を消すようになったのは、2012年頃からとされています。この漫画を読んだ子供と読んでいない子供とでは、原爆の悲惨さや残酷さを認識する脳作用が大きく異なるであろうことは、容易に推測できます。
防大生が制服姿で靖国神社の参道を行進する姿や、軍服姿の大人が日の丸を掲げて歩く姿を見ると、戦争の悲惨さや残酷さを認識する脳細胞群が十分に形成されないまま成長した人間の危うさを、ひしひしと感じます。
※存在が意識を規定するのであり、意識が存在を規定するのではありません。教育を十分に受けることができれば、誰でも大学に進学できる程度の脳の形成は可能です。オウム真理教や統一教会などのエセ宗教が狂信的信者を作り出すのも、洗脳によって思考が固定化されるためです。
経済的に裕福な家庭に生まれ育ち、空腹も労働の体験もなく、受験勉強一筋で育ってきた、戦争を知らない子供たちが、大人になって、いっぱしの政治家・官僚・自衛官として権力を手にしたとき、どんな世界が到来するのか。そう考えただけで恐ろしくなります。
※世襲議員の小泉進次郎防衛大臣が自衛隊服を着込んで、パラシュート降下訓練のまねごとをしているのをニュースで見ました。随分前のことですが、地元で著名な陶芸家から、ある会合に呼ばれたとき、玄関前に整列した会員が一斉に敬礼して出迎えたという話を聞いたことがあります。また、大の男たちが近くの山中でゴーグルをつけ、エアソフトガン(遊戯銃)で戦争ごっこをしているという話を聞いたこともあります。その話を聞いたときに感じたのと同じ、何とも言いようのない気持ちに襲われました。
都会に生まれたか田舎に生まれたか、裕福な家庭に育ったか貧しい家庭に育ったか、両親そろった家庭で育ったか片親の家庭で育ったかといった個人的事情にかかわりなく、すべての若者が無償で高等教育を受けることができ、女子学生が奨学金返済のために夜のアルバイトをしなくて済むよう、返済不要の奨学金制度が整備されていれば、全国津々浦々から優秀な若い人材が生まれてくることが期待できます。
最近、在日3世の李相日監督の映画『国宝』を見ました。冒頭の長崎市の料亭での、やくざの新年会の出入りの場面を見ながら、暴力団そのものを禁止する法律があれば、多くの若者がやくざの世界に足を踏み入れることもなく、堅気として生きていくことができたはずだ、という思いに駆られました。
小選挙区制のもとでの世襲議員や、森友学園の土地払い下げ問題で、公文書の改ざん・廃棄を部下に指示したとされる高級官僚、学歴詐称やセクハラ・パワハラ問題が絶えない自治体の首長らと、映画『国宝』に登場する親分衆の顔を見比べると、役柄とはいえ、その風格の違いは歴然としていました。「親ガチャ」という言葉の持つ意味が、はっきりと分かる場面でした。笹川良一・児玉誉士男ら政界の黒幕が戦後も脈々と生き続けることができたのも、警察や自衛隊が対処できない問題が発生したときに備えさせるためであるとの見解がありますが、十分うなずけます。
表題の「司法の独立・裁判官の独立」からは大きくそれてしまいましたが、意図するところはお分かりいただけるのではないかと思います。
※古賀茂明(元)通産官僚、前川喜平(元)文部科学事務次官、孫崎享(元)外交官、岡口基一(元)裁判官らが、政治家・官僚・マスコミ人の劣化による「日本全体の崩壊」を危惧しておられます。そのような良識ある官僚OBや現役官僚の方々がたくさんおられるのは救いです。
岡口(元)裁判官によれば、近時、裁判官の任官希望者が減っており、中途退職者も増えてきているとのことです。「鯛は頭から腐る」「沈む船からネズミは逃げる」と言われますが、出世に関心のない若い世代の人たちが中心となって沈む船にとどまり、腐った鯛を生き返らせてほしいものです。
先の大戦で、本来死ぬべきではなかった多くの若者が真っ先に死に追いやられ、本来戦争責任をとって死ぬべきであった大人たちが、のうのうと生き残るという恥ずべき歴史を日本は持っています。そのような歴史を繰り返してはなりません。
※先ごろ102歳で人生を閉じられた裏千家の千玄室さんは、80年前の戦争を知る世代の人間がいなくなってしまったことで、日本が再び、あのような悲惨な戦争を引き起こす情けない国になるのではないかと心配し、残された私たち一人ひとりに警戒を怠らないよう警告して旅立たれました。生前、田中角栄氏も同じことを話しておられたとのことです。
※新聞・テレビ等のマスメディアの報道の自由度が世界第70位で、先進国の中では最低にランキングされるという惨憺たる状況にありますが、若い世代の新聞・報道記者らが奮起して国民の知る権利に応え、傾いた船をまっすぐに進めるために頑張ってくれることを期待しています。
次回は、弁護士人口の大幅増大、弁護士事務所の法人化と宣伝の自由化、弁護士報酬規程の撤廃などがもたらした弁護士業界の弊害と解決策等について、地方の単位弁護士会の決議・意見書等を参考に、私見を述べたいと思います。
なお、引き続き西日本新聞と毎日新聞の押し紙裁判の行方に注目していただければ幸いです。
※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2026年1月19日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。
▼江上武幸(えがみ・たけゆき)
弁護士。福岡・佐賀押し紙弁護団。1951年福岡県生まれ。1973年静岡大学卒業後、1975年福岡県弁護士会に弁護士登録。福岡県弁護士会元副会長、綱紀委員会委員、八女市役所オンブズパーソン、大刀洗町政治倫理審査会委員、筑豊じんぱい訴訟弁護団初代事務局長等を歴任。著書に『新聞販売の闇と戦う 販売店の逆襲』(花伝社/共著)等
▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/
◎twitter https://twitter.com/kuroyabu