槇奈緒美さんは、福島県富岡町で被災した。避難所を転々とする日々が続くなか、「1号機爆発」も「被ばく」も気にはなったが、難病を抱える身でもあり、毎日生きていくことに精一杯だった。「避難した事実そのもの、そのしんどさを分かち合えればと考えている」。以下に記した話の何倍もの話を、奈緒美さんに聞いた。原発事故からまもなく9年経つというのに、その重みは変わらない。

◆不安を抱えながら引っ越した富岡町で被災した
中学にはいってまもなく母親を失った奈緒美さんは、妹と父親の3人で、父親の実家のある福島県富岡町に引っ越した。1986年、チェルノブイリの原発事故が起きた年だ。幼いころ読んだ「はだしのゲン」も思い出され、なんとなく「原発の町に住むのは嫌だな」と思ったという。友達のお母さんが、大熊町にある研究所に勤めていたが、原発作業員らの染色体を調べたら異常があるとか、作業服を洗濯する人も被ばくしているなどの話を聞いた。一方で、卒業後、東電に就職する同級生も多いうえ、親戚の飲食店も東電の社員が客なので、「原発怖い」と素直に言えない雰囲気があった。
京都の大学に入学した奈緒美さんは、卒業後も京都に住み続け、発掘の手伝いなどをしていたが、ストレスが重なり、32歳の時、全身に痛みやこわばりがでる「線維筋痛症」にかかった。妹のいる東京に移り住んだが、1年後の33歳の時には精神の病にかかり、東京の精神病院に8ケ月入院、その後は精神科医の勧めもあり、福島県いわき市の病院へ転院した。
2008年、夏頃退院し実家で療養生活を始める。父との二人暮らしだが、体の痛みで動けない時期が続いた。思春期におきた突然の母親の死が受け止めきれず、33年~35年分の疲れがどっとでた感じだった。そんななか、2010年秋からハローワークに通い出し、2011年事故の1週間前には障害者の就職相談会に参加するなど前向きな気持ちになっていた。
◆「被ばく」も怖かったが、毎日生きるのに精いっぱいだった
そんな矢先に事故が起きた。奈緒美さんは父と二人で富岡町の多目的ホールに避難した。持ち出せたのは毛布2、3枚と通帳、下着程度。配給はペットボトルl本とパン1個。寝られずに迎えた翌朝、避難範囲が3キロから10キロに広がり、移動することになった。7時半車で出発、24キロ先の川内村に移動したが、満杯で入れず、渋滞の中のろのろ運転で田村郡の船引の廃校の小学校に到着したのが15時半頃。その直後、1号機が爆発したと友達からメールで知らされた。支援物資は少なく、食事は1リットルの水と塩気のない小さなおにぎり。昼間、渋滞の道の反対車線から茨城交通のバスがいっぱい走っていたことを思い出す。あとで知ったが、それは大熊町が避難のために手配したバスだった。車のラジオで、しきりに「水位が下がった」などと言っていたことも思いされた。怖かったものの、現実はそれどころではなかった。毛布も不足しているし、食事も毎日甘い菓子パンが続く。味噌汁も小さなプリンのカップのような容器に二口だけ……。
配給の少ない避難所からは、被災者はどんどん別の避難所に移動していく。事故のことも気になるが、避難所暮らしのことで頭はいっぱいだった。
その後、父の親せきが避難する会津若松の高校に移動。そこは比較的支援物資は多いものの、寒い上に持病のある奈緒美さんは、目を開けているのも辛かったという。原発も気になるが、当時は1日1日を生きることに必死だった。あるとき薬局で、特殊な奈緒美さんの薬が、入手できなくなるかもといわれたこともあり、ひとりで避難することを、父や親せきに訴え、説得させた。将来子どもを産むかもしれないから、被ばくしたくないとの思いだった。
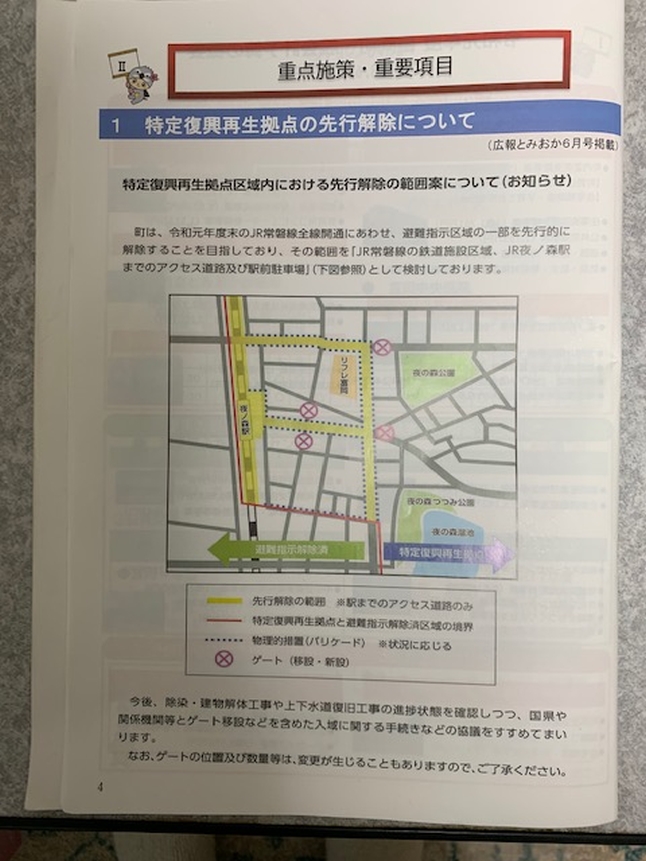
3月23日、友達のいる東京にバスで逃げ、その後は千葉の友達の家、親戚の家などを転々とした。
「福島にいていたらなかなか情報がわからないが、福島を出ると、本質的に何か大変と共有できる人が大勢いるから、それは良かったと思う」と当時を振り返る。
◆家族と別れ、たった一人で関西へ避難
その後、父から「家族単位で避難しなくてはならないから」と連絡があり、仕方なく栃木県日光市に移動。富岡町と災害協定を結んでいた品川区の保養所が、駅から車で10数分の山の中にあった。精神科医のボランテイアに相談し、個室を与えられた奈緒美さんは、観光シーズンの始まる8月末までそこに居た。その精神科医が、父親を説得してくれ、奈緒美さんは再び一人で関西へ避難することとなった。単身で住める宝塚の借り上げ住宅に入り、家電6点セットや掃除機、こたつなどを支援者に用意してもらった。とても助かると思った。初めての町で、近所に避難者もいなかった。その後、宝塚の「避難者のカフェ」などに行ったが、立場が様々なので、人とつながるのに時間がかかったという。
2012年、関西で瓦礫焼却の問題が起きた際には、勉強会で知り合った方と一緒に署名活動などをした。リハビリにも通い、のろのろ運転で試行錯誤しながら、日常生活を取り戻してきた。2013年から吹田にある「モモの家」で避難者カフェのスタッフに加わり、今も継続中。
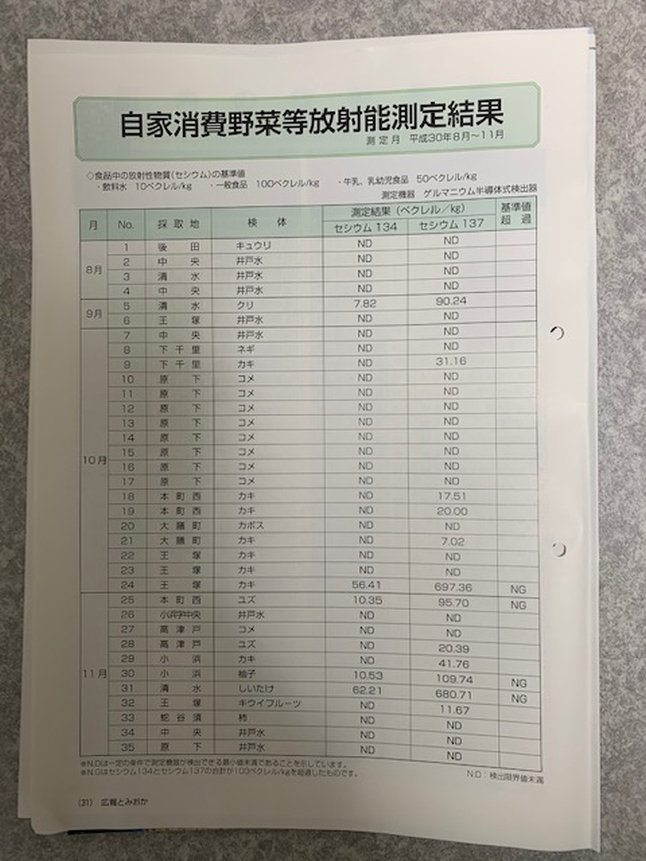
◆「ひょうご原発訴訟」の原告となる
事故当時、就労活動の準備中だった奈緒美さんの賠償金は少なかった。東電は、フォーマットにあてはまる問題から少しでも外れていたらはじいてくる。「ハローワークに何回いった」「面接に何回いった」。「99・9%の確実で就職する予定だった」と確認されないと、就労保障は無理とわかった。そのADRの担当だった弁護士に勧められ、奈緒美さんは、2014年3月「ひょうご原発訴訟」の原告となった。
「いろんな避難者に接していると、自分の内面を癒したい気持ちと、裁判などで社会問題として解決したと思う人たちと、うまく交わってという部分もあるが、両極に分かれることもあると感じている。私はそれよりも避難した事実そのもの、そのしんどさを分かちあえればと考えています。表現スタイルは人それぞれだが、ちょっと大局的にものごとを見ていきたいとは思います」と奈緒美さんは語る。
「ひょうご訴訟」の原告は、現在97人。これから本人尋問が始まる。一昨年、裁判長が変わった際、奈緒美さんが行った意見陳述の一部を紹介する。
「事故前は病気に理解ある叔母や叔父に助けられていた。また私の複雑な生い立ちを理解してくれる友人、もしくは東京などに住む同郷の友人が帰省したら会うことができた。周囲の人々に有形無形で助けられていた。自分自身が不安定でも、自然に恵まれた、安定した環境でゆっくり自分の病気に向き合うことができた。庭では亡き祖父が大切にしていた梅の木に癒され、父は山でワラビやゼンマイを取り、叔母は川沿いで拾ったクルミを使った料理でもてなしてくれた。避難後はヘルパーさんや訪問介護を利用して、なんとか日常生活を送っている。就労はしているものの、事故前より、不安を感じやすくなっている」。
奈緒美さんは、以前読んだ詩集で、広島の「原爆自閉症」という言葉を知ったという。被爆の苦しみを言えずに自閉症みたいになり、いっそのこと、ほかの土地にもピカが落ちればと思ってしまうという症状だ。そして「そうやって、問題が内に籠り、はけ口が見いだせなくなることが怖いと思ってしまいました」と話す。意見陳述の最後を奈緒美さんはこう締めくくった。
「私はただ原発事故によって、放射能が拡散された事実を、ありのままに受け止めて、避難の選択をし、それが続けられる権利を求めたい」。

▼尾崎美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。最新刊の『NO NUKES voice』22号では高浜原発現地レポート「関西電力高浜原発マネー還流事件の本質」を寄稿

