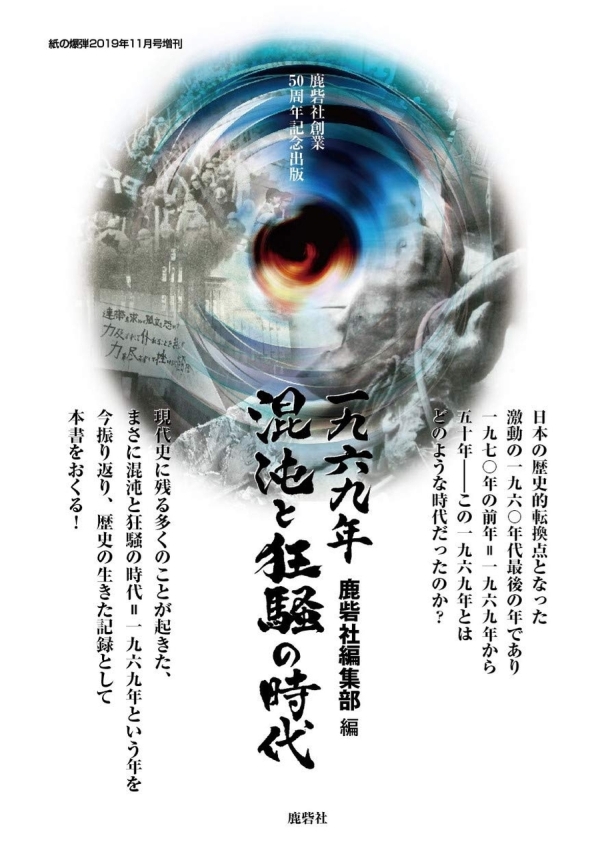カルロス・ゴーン氏の「逃亡」事件および、同氏による「日本の司法制度は人質司法」という批判をうけて、法務省がHPに「言い訳」のような見解を発表した
「我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html」がそれである。
ゴーン氏の記者会見がもっぱら、日本政府と日産関係者の陰謀よりも、日本の非人道的な人質司法に向けられたことから、国民と国際世論に訴えるかたちで公表されたものだ。
しかしその内容は、みずから基本的人権を欠いた「人質司法」であることを暴露するものになっている。具体的にみてゆこう。
Q3 日本の刑事司法は,「人質司法」ではないですか。
A3 日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,「人質司法」との批判は当たりません。
すべての場合を網羅したデータはないので、わたし個人の場合を挙げておこう。本欄でも連載した「40年目の三里塚開港阻止闘争」で明らかにしたとおり、わたしは三里塚闘争で逮捕され、1年間の未決拘留を受けている。1年間というのは、訴状と求釈明および冒頭意見陳述が終わり、公判が軌道に乗ったということをもって、保釈が許可されたからである。その間、2度の保釈許可と検察抗告による却下があった。
しかしながら、取り調べで自白した被告(同一犯罪)は、同じ罪名でありながら二か月ほどで保釈が許可になっている。つまり、自白をしないかぎり裁判が軌道に乗るまで保釈はしない、ということをこの事実は意味しているのだ。これが「人質司法」の実態である。一般に公安事件ではこの基準が現在も維持されている。ではなぜ、判決によらない刑罰とも言うべき1年間もの拘置が不法に行なわれるのか?
Q4 日本では,長期の身柄拘束が行われているのではないですか。
A4 日本では,どれだけ複雑・重大な事案で,多くの捜査を要する場合でも,一つの事件において,逮捕後,起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は,最長でも23日間に制限されています。
起訴された被告人の勾留についても,裁判所(裁判官)が証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると認めた場合に限って認められ,裁判所(裁判官)の判断で,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たると認められない限り,保釈が許可される仕組みとなっています。
要するに、自白をしていないから「証拠隠滅のおそれがある」というのだ。それならば、冒頭手続きが終わって保釈したあとは、証拠隠滅をしないと言えるのだろうか? 捜査が終了したあと、単に書面の準備が整わないから1年もの期間拘置をつづけているのだろうか?
そうではない。刑の先取りを行なうことで、長期の拘留に耐えられなくなった被告が「謝罪」「自白」あるいはその政治的な成果である「転向」することを強いているのである。そのいっぽうで、被告は裁判のための準備を十分に行なえない。被告の身体を拘束することで弁護権を奪い、裁判を検察側の有利に運ぶ、これを「人質司法」と言わずして何というのだろうか。
Q8 拘置所での生活環境はどのようなものですか。
A8 拘置所においては,被収容者の人権を尊重するため,居室の整備,食事の支給,医療,入浴などを適切に行っています。
入浴については,被収容者の健康を保持し,施設の衛生の保持を図る観点から,1週間に2回以上実施しています。夏季などには,必要に応じて回数を増加させています。
1週間に2回の入浴を多いと感じるか、それとも少ないと感じるかは個人的な差があるかもしれないが、わたしは少ないと思う。夏場ならシャワーは毎日朝夕浴びるし、冬場は隔日入浴(週3~4日、しかも1日複数回)がふつうの生活だと思う。
拘置所といえば東京拘置所がよくマスコミに登場するが、全国に111カ所ある。そのうち、刑務所の管轄が99、独立した拘置所は6カ所である。未決拘置者の生活は、懲役労働がないだけで、房内処遇はほぼ禁固囚と同じなのだ。戦後に一部が改正されたとはいえ、その基本骨格は明治41年制定の監獄法である。けっして「証拠隠滅」の恐れがあるから、ちょっと留め置くよ。みたいなものではないのだ。
所内生活は命令と服従、点呼時には房内で正座して「〇〇です!」と答えさせられる。24時間房内に閉じ込められているのだから、懲役囚よりも処遇は厳しいといえよう。房を出られるのは1日15分の運動時間(運動場も独房)と面会時間、入浴の時だけである。歩くときは刑務官が「進め」「止まれ」と、命令して先導する。かように窮屈な処遇というのも、明治監獄法がそのまま生きているからだ。
刑務官に「〇〇しろ!」と命じられ、従わないなら「懲罰房」に入れられる処遇のどこに「被収容者の人権を尊重する」ものがあるというのだろうか。拘置所とは刑務所なのである。ゴーン氏ならずとも、まだ判決を受けていないのに、不当な刑罰を受けている。と感じるのは当たり前だろう。
だから、テレビのワイドショーでゴーン氏の逃亡を「悔しいですね。日本の司法がバカにされて」とかのたまわっている識者は、一度でいいから拘置されてみるといい。判決もないところで刑罰を受ける不思議に、きっと脱獄を考えたくなることだろう。
もうひとつ日本の司法の前近代性をあらわしたものに、ゴーン氏の身柄を取り戻せないことがある。ゴーン氏の身柄をレバノンが引き渡さない理由は、じつは日本に死刑制度があるからなのだ。日本が被疑者身柄引渡し条約を韓国とアメリカの2国しか結んでいない不思議を「島国だから、その必要がない」とか何とかいい加減なことを言っている論者もいるが、そうではない。
いまだに死刑制度がある前近代的な日本の司法制度に驚嘆し、日本で法を犯した自国の被疑者を引き渡さない。当然の人権感覚があるから、死刑存置国(アメリカ=過半数の州で廃止、韓国=事実上の死刑判決回避)しか相手にしてもらえないのだ。この点については、死刑廃止運動の動向とあわせて稿を改めたい。
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業。「アウトロージャパン」(太田出版)「情況」(情況出版)編集長、最近の編集の仕事に『政治の現象学 あるいはアジテーターの遍歴史』(長崎浩著、世界書院)など。近著に『山口組と戦国大名』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『男組の時代』(明月堂書店)など。