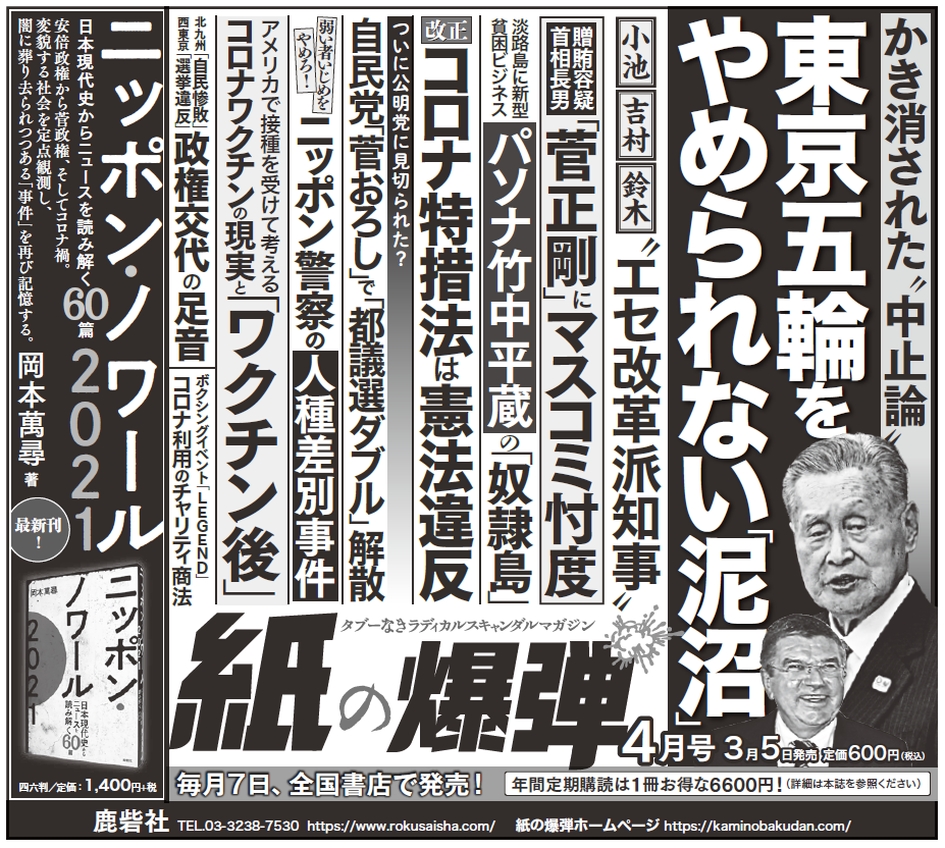前回につづいて、昭和天皇の戦争指導を検証していこう。日中戦争の泥沼化のなかで、暴走する軍部(関東軍)およびそれを統制できない政権に懐疑的だった天皇は、開戦劈頭(へきとう)の「大勝利」に浮かれた。そして、大元帥としての軍事的才能を開花させるのだ。
◆開戦前から和平への道を模索する
日米開戦が決定的になった時期、昭和天皇は講和への外交工作を気にかけている。
「戦争終結の手段を初めより充分考究し置くの要あるべく、それにはローマ法皇庁との使臣の交換等親善関係につき方策を樹つるの要あるべし」(『高松宮日記』天皇から木戸幸一への下問)と、開戦前に講和工作を模索しようとしていたのだ。
この天皇の要求を、軍部も無視していない。
開戦に当っての大本営政府連絡会議の「腹案」には、独ソ講和によって日独伊三国が英国を降伏させ、ソ連を枢軸側に引きこむ。蒋介石専権の打倒および米豪の海上交通路を遮断し、アメリカをして戦意喪失させる、という希望的展望が盛り込まれている。
さらには具体的に、前掲の天皇の意を受けて、スウェーデン、ポルトガルを通じたローマ法皇庁への外交戦略も付加されている。開戦後も連合軍のシチリア上陸時に、ドイツがルーマニアの油田を失う可能性が論じられ、日本として独ソ妥協を講じられなければ、戦争方針を変更しなければならないことが検討されている(『真田穣一郎日記』)。
これらの戦争戦略、外交政策による戦争の早期終結が実現しなかったのは、戦争の性格がそれまでにない、総力戦に変わっていたからにほかならない。
総力戦とは国民経済(生産と消費)の戦争経済(軍需に集中)への転換であり、それは軍事技術・兵器の高額化と大量化に促されたものだ。
その意味では、昭和天皇が開戦にあたって、和平への道を模索していたのは、講和が容易だった日清・日露戦争、あるいは第一次大戦を限定的に戦った歴史から考えていたものにすぎない。
総力戦の時代には政治(外交)が後景化され、軍事(戦闘)が最優先になる。政治と軍事が逆転するのだ。そしてそれは、兵器の大規模化と国民の総動員によって、国家の崩壊まで突き進む。このことを天皇は理解していなかった。いや、天皇自身が総力戦に呑み込まれていくのである。
◆龍顔ことのほか、うるわしく「あまり戦果が早く挙がりすぎるよ」
開戦劈頭、日本は海軍が真珠湾にアメリカ太平洋艦隊の主力を撃滅し、陸軍もマレー上陸から怒涛の進撃を開始する。開戦三日目には、イギリス東洋艦隊(戦艦プリンスオブウェールズ、レパルス)を航空作戦で壊滅させた。
2月にはシンガポール陥落(英軍降伏)、バンドンでオランダ軍が降伏。海軍もインド洋で残存英国艦隊(空母ハーミスほか)を壊滅させ、艦隊決戦となったスラバヤ沖海戦、バダビア沖海戦においても、米・豪・蘭・英の連合軍を敗走させた。赫赫たる勝利である。
龍顔ことのほか、うるわしく「あまり戦果が早く挙がりすぎるよ」と天皇は喜びを述べている。じつは天皇自身が、イギリス艦隊の動き(出港)に注意するよう、戦争開始前から軍部に指示をしていた。南部仏印進駐時やイギリス艦隊の動向など、軍事的な才能さえ感じさせる発言が残されている。
フィリピンのコレヒドール要塞の攻略に手こずったとき、天皇は大本営陸軍部を執拗に督励し、追加部隊の派遣を要求している。まさに大元帥として、戦争を指揮し、督戦しているのだ。
◆陸軍機は使えないのか?
米豪の交通を断つ目的で、日本海軍はニューブリテン島にラバウル基地をつくり、さらにソロモン諸島に戦線を延ばした。ニューギニアの攻略を目的とした陸軍とのあいだに、齟齬が生じるようになってしまう。昭和17年の南太平洋における戦いは、天皇にとって陸軍と海軍の提携が気になって仕方なかった。
「ニューギニア方面の陸上作戦において、海軍航空隊では十分な協力の実を挙げることができないのではないか。陸軍航空を出す必要はないか」(田中新一『業務日誌』)。
陸軍はこのとき、中国の重慶攻撃のために爆撃機を南方から撤退させる計画を進めていた。しかも陸軍機は、洋上での航法に慣れていなかった。編隊からはぐれてしまうと、海上で迷子になったまま帰還できない爆撃機も少なくなかったのである。
ガダルカナル島の飛行場が米軍に奪われると、天皇は三度目の督促をする。
「海軍機の陸戦協力はうまくいくのか、陸軍航空を出せないのか」(「実録」)と。
このガダルカナル島の苦戦を、軍部以上に気にかけていたのは昭和天皇だった。
「ひどい作戦になったではないか」(「実録」)と、感想をのべている。
珊瑚海海戦、南太平洋開戦で海軍が得た勝利も「小成」と評価はきびしい。開戦当初の勢いからすれば、アメリカの戦意を喪失させる大勝が待ち遠しかったのである。
◆日露戦争の教訓から注意を喚起するも
学者的な几帳面さで、歴史にも通じていた昭和天皇は、困難な時期にも軍事的な天才ぶりを見せている。海軍がガタルカナル島の米軍飛行場を、夜間艦砲射撃しようとした(天皇に上奏)さいのことだ。
「日露戦争に於いても旅順の攻撃に際し初島八島の例あり、注意を要す」(『戦藻録』)と釘を刺したのだ。
日露戦争の旅順閉塞戦のとき、戦艦の初瀬と八島が機雷によって沈没した、ある意味では貴重な戦訓を、海軍の永野修身軍令部総長に伝えたのである。
この天皇の警告は、的中してしまった。海軍にとって二度目の艦砲射撃(一度目は戦艦金剛と榛名)だったが、同じような航路をとってガタルカナルに接近した戦艦比叡と霧島は、待ち構えていたアメリカ軍の新鋭戦艦のレーダー砲撃の餌食となったのだ。夜間攻撃であれば、いちど成功した航路をたどりやすい。アメリカは用意周到にこれを狙い、昭和天皇も歴史に学ぶ者にしかない直感で、危機を感じ取っていたことになる。
昭和17年6月には、ガタルカナル島攻防(撤退)とならんで太平洋戦争のターニングポイントになるミッドウェイ海戦で、海軍も致命的な敗北を負った。
この年の12月、昭和天皇は陸海軍とも「ソロモン方面の情勢に自信を持っていないようである」「如何にして敵を屈服させるかの方途が知りたい」「大本営会議を開くべきで、このためには年末年始もない」と軍部を突き上げた。
そして実際に、12月31日に大本営会議が開かれた。ガタルカナル島撤退後、どこかで攻勢に出なければならない、という天皇の焦りが感じられる。
◆決戦をもとめる天皇
昭和18年になるとアッツ島玉砕をはじめ、アメリカ軍の反転攻勢がめざましくなる。
「どこかの正面で、米軍を叩きつけることはできぬか」(『杉山メモ』)という言葉を何度も発している。
昭和天皇の発言だけを見ていると、軍部にやる気が感じられないかのようだ。いや、軍部は戦力的な手詰まりに陥っていたのだ。太平洋上に延びきった前線では、アメリカ軍との戦いよりも、兵士たちは飢えと感染症に苦しんでいた。輸送船が潜水艦に狙われ、海軍は前線の補給のために駆逐艦を使わなければならなかった。

昭和19年の元旦には「昨日の上奏(上聞)につき」として「T(輸送船)北上につき、敵の牽制なるやも知れず『ニューブリテン』西方注意すべし」と、侍従武官を呼びつけて警告している。この年も大晦日まで、軍務にかかる上奏を受けていたことになる。
それはともかく、実際にアメリカ軍は輸送船団を陽動部隊にして、日本軍の注意をニューブリテン島に惹きつけておいて、ニューギニア北部に上陸していたのだ。昭和天皇の細かい注意力は、数千キロ離れた戦場に向けられていたのである。
しかし全般的に、昭和天皇の戦争指導は減退してゆく。
敵機動部隊(スプルーアンス提督が率いる15隻の空母部隊)がサイパンに近づくと、天皇はサイパン失陥で東京がB29の爆撃範囲に入ることを考え、海軍に不退転の決戦をもとめる。
「このたびの作戦は、国家の興隆に関する重大なるものなれば、日本海海戦のごとき立派なる戦果を挙げるよう作戦部隊の奮励を望む」(「業務日誌」)と。
しかるに、日米の空母機動部隊同士による海空決戦(マリアナ沖海戦)は、日本海軍の惨敗に終わる。空母3隻を喪失、艦載機400機を失ったのである。そしてサイパン島も、上陸したアメリカ軍の支配するところとなった。
意気消沈した天皇は、吹上御所で夜ごとにホタルの灯をながめていたという。このときこそ、昭和天皇は戦前からの持論であった「講和交渉」を始めるべきであった。
結果論で批判しているのではない。みずから語った日本海海戦に比すべき戦いに負け、サイパンが陥落したのだから、東京空襲の災禍は誰の目にもわかっていた。国家を崩壊させる総力戦の威力を、しかし天皇は徐々に知ることによって「和平」のタイミングを逸し、国民を絶望的な戦いに巻き込んでしまうのだ。(つづく)
◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。