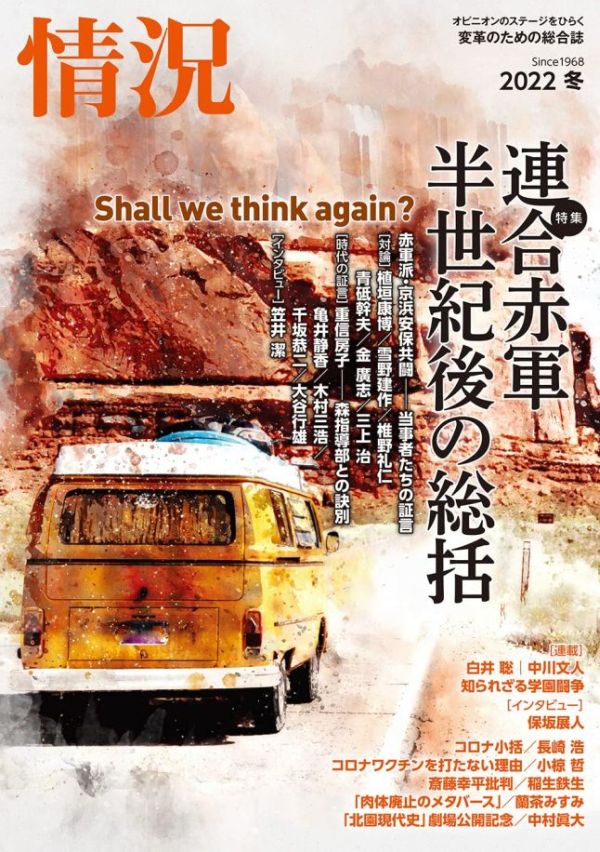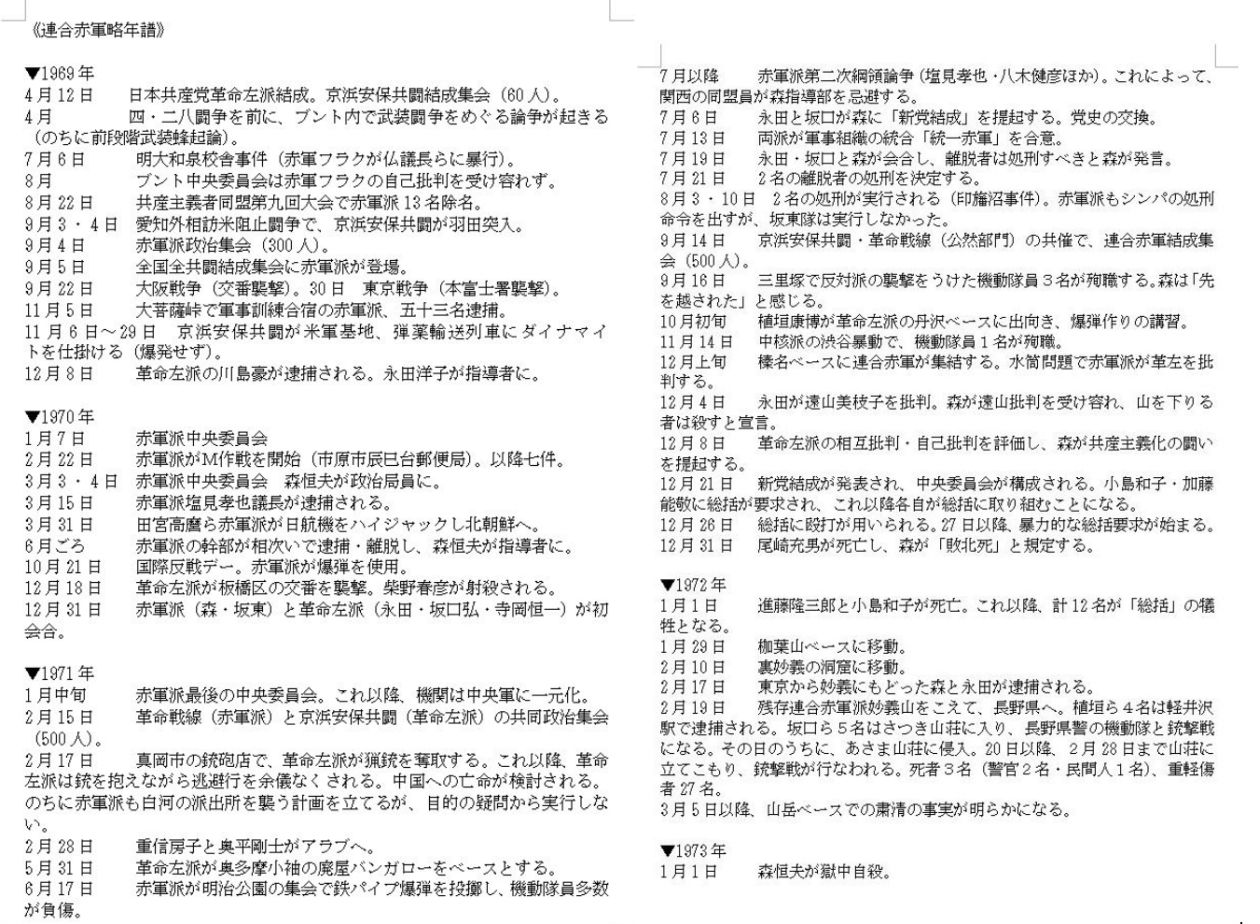◆共産主義化とは何か?
森恒夫によれば、各自の革命運動へのかかわりを問い質し、みずからの活動の総括(反省)をもとめる。その「総括」を達成することで、銃と高次な結合(共産主義化)が果たせるのだという。
これが、連合赤軍の指導者森恒夫の「共産主義化論」である。もともと赤軍派は、組織的に「相互批判・自己批判」を行なってこなかった。
この「相互批判・自己批判」は、中国共産党が延安への「長征中」に行なった、整風運動の方法である。お互いに批判し合い、自己批判することで政治的態度を改める。それを通じて党員の思想傾向を改め、党風を整頓する。いわば党内の思想闘争である。
この思想闘争はもともと、赤軍派にはないものだった。思想闘争にもとづいた、精緻な組織活動。その違いは、両派が遭遇した「同志の処刑」で露呈したものだ。
革命左派が呻吟ののちに「処刑」を実行したのに対して、赤軍派は曖昧なまま実行できない組織だったのである。
植垣康博はその違いを「真面目な革命左派にたいして、われわれはいい加減だった。その違いだった」と語っている(『情況』2022年1月発売号)。
だからこそ、森は「革命左派は進んでいる」と感じたのだ。そして森は、革命左派の「進んでいる部分」を巧みに摂取する。
森はこう記している。
「赤軍派に於て69年の闘争時から中央軍兵士のプロレタリア化(共産主義化=引用者注)の課題が叫ばれ、大菩薩闘争の総括では『革命戦士の共産主義化』が中心軸として出されてはいたが、その方法は確立されていなかった。私は革命左派の諸君が自然発生的にであれ確立してきた相互批判・自己批判の討論のあり方こそがそうした共産主義化の方法ではないかと考えた」(逮捕後の「自己批判書」)。
ところで、森の理論的な卓抜さに対抗できる指導者は、革命左派にはいなかった。
その結果、森の「共産主義化」の理論をそのまま受け容れることになるのだ。森は革命左派の組織内の相互批判を、上記の「共産主義化のための総括」に適用したのだった。
そこまでならば、山岳ベースで大量の死者が出ることはなかった。
いかに過酷な相互批判・自己批判であっても、討論をしているだけで人が死ぬことはない。同志たちが死んだのは、総括の「援助」として殴ったからなのである。食事を与えず縛り上げ、死ぬほど殴ったから死んだのだ。極寒の中で放置されたからこそ、かれら彼女らは死んだのである。
◆森の総括体験
その暴力は、どこからやって来たのだろうか。この連載の前回で、連合赤軍の「処刑」がどこから発想されたのは、いまも流布している「連合赤軍服務規律」(ニセ文書)を参考にしたのではないか、という公安当局の推測を批判してきた。それが共産主義政党の綱領的な部分に抵触するがゆえに、政治的な「服務規律」足りえないことも明らかにした。したがって、「処刑」は規約によるものではない。だがまぎれもなく、連合赤軍は「処刑」を実行したのだ。当初の「敗北死(総括をしきれずに、敗北することで死んだ)」から始まり、12名の同志が殺されたのである。
その「暴力的な総括支援」の思いつきは、じつは森恒夫の高校時代の体験にあった。高校時代の森恒夫は、剣道部の主将だったのだ。かれは剣道の稽古のさなか、転倒して後頭部を打ったことがある。脳震盪で意識をうしない、その後覚醒して「生まれ変わった気分だった」という。
剣道協会によれば、つばぜり合いのときに後ろ頭から倒れて脳震盪を起こす事故があるという。それを避けるために、倒れるときは腰を落として倒れるのが、事故防止のためには良いとされている。森はこの脳震盪を体験したのである。読者諸賢はいかがであろう、脳震盪の「意識喪失」の体験はありますか?
ボクシングでダウンするのは、グローブでの打撃が脳を揺さぶり、脳震盪を起こすからだ。ラグビーもタックルで何度か、頭からぶつかるうちに脳震盪を起こす。かつては「魔法のヤカン」で頭に水を垂らすと、倒れていた選手が蘇生するシーンを見たものだ。あれはしかし、きわめて危険である。脳震盪をくり返すうちに、それがパーキンソー病の因子になる。
ともあれ、森恒夫は高校剣道部時代の体験から、気絶する(脳震盪を起こす)ことで、人間が生まれ変わると信じていたのだ。永田もそれを信じていた(『あさま山荘1972』坂口弘)。
◆「同志」を殺した戦後教育の体罰
じつは森恒夫をして、気絶させて蘇生させる「総括援助=体罰」は、戦後教育の遺産なのである。けっして戦前のものではない、戦後民主主義教育の体罰なのだ。
現在、60歳以上の男性なら記憶にあるはずだ。教室で早弁(お弁当を早めに食べる)しては、教師から往復ビンタを喰らい、野球部の部活では「ケツバット」の罰をお見舞いされた。昭和50年代までの日本では、体罰はふつうに行なわれていたのだ。
家庭でも同じだった。戦争(軍隊)を生き残った父親はすこぶる厳しく、ことあるごとに息子を殴ったものだ。筆者も同年齢を前後する3歳ほどの同輩の証言で「親父を殺したいと思ったことがある」というのを聞いたことがある。ちなみに、小学生のわたしを殴った父親は、片耳が聴こえなかった。予科練で教官に殴られたときに、鼓膜を失ったのである。
もともと野球やラグビー、サッカーなどの「外来競技」は、きわめて民主的でスポーツマンシップにあふれたものだった。少なくとも、戦前のスポーツはリベラルアーツ(教養主義)を体現したものであって、体罰などとは無縁のものだったのだ。
ところが、近代の市民革命を経なかった日本の軍隊は、上からの暴力的な畏怖をもって、農民兵(当時の国民の大半)を統制する必要があった。スパルタ式という体罰教育も、じつは旧軍由来のものなのだ。
陸軍における内務班暴力(公認された私的制裁)、海軍における精神注入棒。最も先進的とされた海軍兵学校ですら、上級生による問答無用の鉄拳制裁が容認されていたのである。
こうした旧軍における暴力が徴兵された男たちに叩き込まれ、戦後になって日本全国に伝えられたのだ。
それは息子を鍛える父親の家庭における教育、部活動の指導者の暴力的な指導であり、教室内でも教師の暴力制裁は行なわれた。運動会における軍隊式の行進、スポ根アニメの流行、応援団のシゴキ(内部リンチ)、そしてその暴力は左翼運動にも持ち込まれていた。
森恒夫の体育会的な「総括援助」はまさに、戦後教育がもたらしたものだったのだ。殴って教える、殴って総括させる……。
この森の総括援助は過酷な厳しさを求め、やがて食事を与えずに縛りあげ、極寒の山中で同志たちを死に至らしめたのである。連合赤軍の「同志」たちは、左翼の共産主義理論ではなく、旧軍隊ゆらいの暴力によって殺されたのだ。(つづく)
[関連記事]
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈1〉71年が残した傷と記憶と
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈2〉SM小説とポルノ映画の淵源
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈3〉連合赤軍と内ゲバを生んだ『党派至上主義』
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈4〉7.6事件の謎(ミステリー)──求められる全容の解明
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。