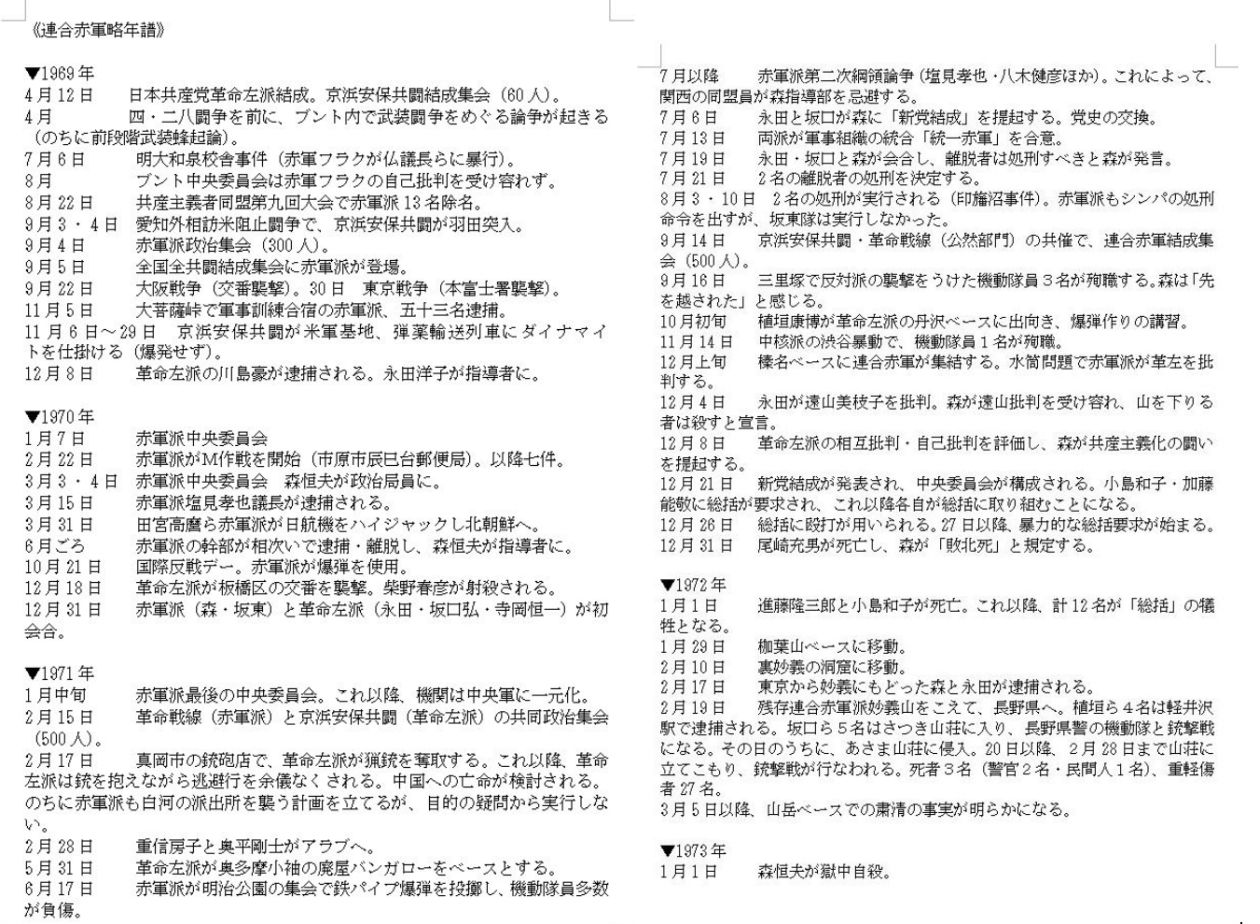◆山岳ベースの魔女に仕立てられた永田洋子
8日間にわたる、あさま山荘銃撃戦のあとに同志殺しが発覚し、日本じゅうが驚愕の渦に叩き込まれた。そのとき、メディアが書き立てたのは森恒夫と永田洋子という、ふたりの指導者像についてだった。とりわけ、女性指導者という話題性から、永田洋子の個人的な資質について週刊誌は詮索したものだ。
おりしも日本社会はウーマンリブの台頭期であった。いまの若い人は知らないBG(ビジネスガール=売春婦を想起させる)という言葉がOLに改められ、女性の社会進出が世情を騒がしていた。
マスメディアの俎上に上げられた永田洋子はすこぶる悪評で、まるで殺戮の魔女のような扱いだった。そして法廷でもその資質が問題にされ、事件の本質が彼女と森恒夫の資質にあったかのごとく評されたのである。
1982年6月18日の一審判決(中野武雄裁判長)から見てゆこう。
「被告人永田は、自己顕示欲が旺盛で、感情的、攻撃的な性格とともに強い猜疑心、嫉妬心を有し、これに女性特有の執拗さ、底意地の悪さ、冷酷な加虐趣味が加わり、その資質に幾多の問題を蔵していた」
「他方、記録から窺える森の人間像をみるに、同人は巧みな弁舌とそのカリスマ性によって、強力な統率力を発揮したが、実戦よりも理論、理論よりも観念に訴え、具象性よりも抽象性を尊重する一種の幻想的革命家であった。しかも直情径行的、熱狂的な性格が強く、これが災いして、自己陶酔的な独断に陥り、公平な判断や、部下に対する思いやりが乏しく、人間的包容力に欠けるうらみがあった。特に問題とすべきは、被告人永田の意見、主張を無条件、無批判に受け入れて、時にこれに振り回される愚考を犯した点である」
「被告人永田は、革命志向集団の指導者たる資質に、森は長たる器量に、著しく欠けるものがあったと言わざるを得ない。繰り返し言うように、山岳ベースにおける処刑を組織防衛とか路線の誤りなど、革命運動自体に由来する如く考えるのは、事柄の本質を見誤ったというほかなく、あくまで、被告人永田の個人的資質の欠陥と、森の器量不足に大きく起因し、かつこの両負因の合体による相互作用によって、さらに問題が著しく増幅発展したとみるのが正当である。山岳ベースリンチ殺人において、森と被告人永田の果たした役割を最重要視し、被告人永田の責任をとりわけ重大視するゆえんである」
事件が革命運動とは無縁の、指導者個人の資質的欠陥によるものだったと、いわばとるに足らない凶悪事件と断じたのである。これ自体は、裁判官による永田と森への皮肉をこめた悪罵に近いものがある。
いっぽう、森は裁判の開始を待たずに獄中で自殺した(1973年1月1日)。そのとき永田は「森君、ずるい」と思わず口にしている。世間の非難を一手に引き受けることになった永田に、左翼陣営は同情的だった。
とくに、山岳ベースにおける処刑が革命運動自体に由来するものではなく、永田の個人的資質の欠陥、および森の木量不足に起因するという判決には、事件を個人的なものにしていると批判的なものが多かった。あくまでも、革命運動上の問題としてとらえるべきだという、ある意味では真っ当な批判といえる。
しかしながら、個人の資質に還元すべきではない、という論調のあまり、指導者の資質問題が軽視されてきたのも否めない。森恒夫が発議した体育会的な、暴力による総括援助がなければ、同志殺しが起きていないのは明らかである。そして永田洋子の総括発議と告発がなければ、共産主義化のための総括が始まらなかった可能性は高い。独裁的な指導部として、ふたりが事件の責めを一身に負わなければならないのは言うまでもない。
◆森恒夫の実像とは
判決で「実戦よりも理論、理論よりも観念に訴え、具象性よりも抽象性を尊重する一種の幻想的革命家」と評された森恒夫は、しかしマスメディアでは「臆病者」と評されていた。
事件発覚から初期の段階で、明大和泉校舎事件(69年7.6)から「逃亡した」とされていたからだ(複数の週刊誌報道)。森が7.6事件の現場にいなかったのは事実だが、逃げたというのは事実の歪曲である。
森恒夫が行方をくらましたのは、7.6事件に先立つ6月27日の全逓合理化反対集会の司会役でありながら、現場に現れなかったというものだ。これが事実である(重信房子・花園紀男らの証言)。その後、森は大阪の工場で旋盤工として働いていたという。
それより前に、森恒夫はブントの千葉県委員長として三里塚の現地闘争責任者を務めている。のちに連合赤軍事件を知った反対同盟農民は「森がそんなこと(同志殺し)をするとは思えない」と感想を述べたという。
上記の「逃亡説」に基づいてか、週刊誌は「関東派のリンチに遭って、森はテロらないでくれと哀訴した」と報じている(角間隆の『赤い雪』に採録)。
アスパック粉砕闘争の過程で、赤軍フラクが「関東派」からリンチを受けたのは事実である(『世界革命戦争への飛翔』赤軍派編)。しかし「藤本敏夫といっしょにリンチを受け、藤本は古武士の風格で対応したが、森は自己批判した」(週刊誌報道)というのは誤報である。藤本は単独で毎日新聞記者を名乗る何者かに渋谷で拉致され、数日後に解放されている。そのかんの記憶があいまいで、生前もこの事件について何も語らなかったという(加藤登紀子)。
元赤軍派のS氏に聞いた、森恒夫の人物評を紹介しておこう。相手に対しては、きわめて厳格な物言いをしたという。「お前はどうなんだ?」が口癖だったとは、山岳ベースでの執拗な総括要求を思わせる。
そのいっぽうで、年下の者たちには「親父さん」と慕われていたことは、つとに知られるところだ。理論的には突出力があり、連合赤軍で森に対等の議論ができたのは、塩見孝也の秘書役だった山田孝しかいなかった。
◆残された謎
相互批判・自己批判が「銃と兵士の高次な結合」という「共産主義化論」に応用され、森の体育会的な「総括援助」が暴力の発動となったこと。その思想闘争は際限のない「総括地獄」へと堕ちていった。これらが連合赤軍事件の概略である。
だがそれにしても、犠牲になった「同志たち」がなぜ、山岳ベースから逃げなかったのか。修羅場と化していた「処刑場」から、なぜ逃避しなかったのか、という疑問が残るのだ。じっさいには下山(逃亡)したメンバーがいるので、逃げられなかったという解釈は成り立たない。次回はこれを考察していこう。(つづく)
[関連記事]
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈1〉71年が残した傷と記憶と
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈2〉SM小説とポルノ映画の淵源
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈3〉連合赤軍と内ゲバを生んだ『党派至上主義』
◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈4〉7.6事件の謎(ミステリー)──求められる全容の解明
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。