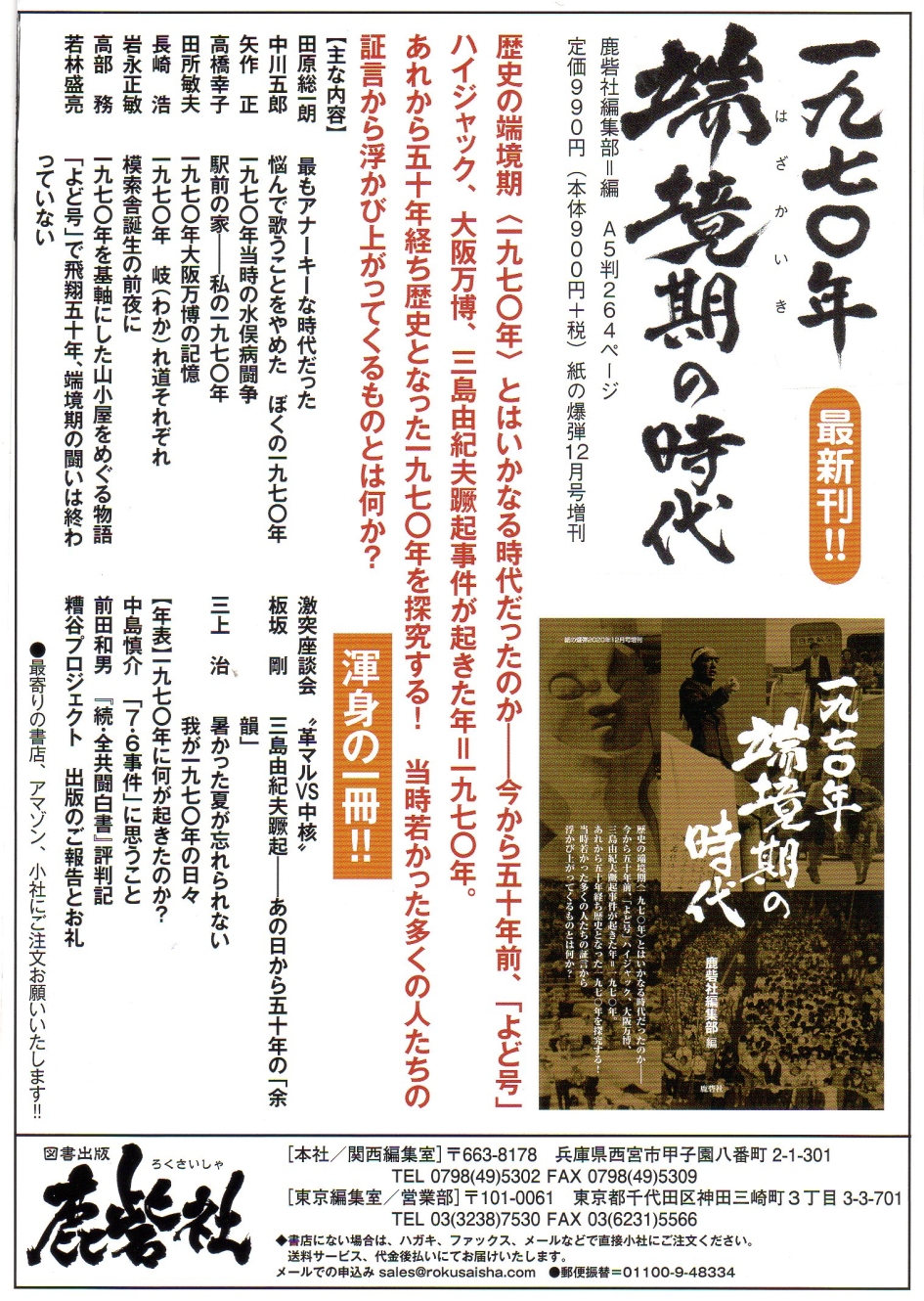終刊のお知らせだった記事の後半ですが、新たな創刊(『情況』第6期)のお知らせとなりました。68年に創刊し、「新左翼の老舗雑誌」と呼ばれてきた『情況』が、来年1月に第6期を創刊することを、謹んでお知らせいたします。これまで同様のご支援、ご愛読をいただければ幸甚です。

本稿の前半では、中核派と共産同首都圏委員会の「米帝の戦争論」批判を紹介してきた(『情況』7月発売号の拙稿を抄録)。
ウクライナ戦争はロシアの侵略戦争であって、アメリカ・NATOは参戦していない。したがって、共産同首都圏委の「帝国主義間戦争」論は、ゼレンスキー政権が傀儡政権でなければ成り立たないと批判したのだった。
戦争と革命という、一般の読者から見れば浮世離れした議論かもしれないが、新左翼の論争とはこういうものだと。覗き見をしたい方はどうぞお読みください。
◆首都圏委員会の論旨改竄(論文不正)
この「侵略戦争論」と「帝国主義間戦争論」は現在、新左翼・反戦市民運動をおおきく二つにわけている。ところが、相手を名指しで批判(論争)しているのは革マル派(中核派の小ブル平和論の傾向を批判)、革共同再建協議会(いわゆる関西中核派=中核派のウクライナ人民の主体性無視・帝国主義万能論を批判)だけであり、論争らしいものにはなっていない。
『情況』は左派系論壇誌として、この論争・議論のとぼしい路線的分岐という運動状況に、一石を投じるものとして「特集解説 プーチンのウクライナ侵略戦争をどう考えるか? 真っ二つに割れた日本の新左翼・反戦運動」を、15頁にわたって掲載したのだった。
とくに帝国主義間戦争論を前面に掲げた、共産同首都圏委員会(「radical chic」44号)には、前回抄録紹介したとおり、全面的な批判を行なった。
ここまで批判しつくされたら、さすがに反論は出来ないであろうという読者の評判だった。だが腐っても、組織ではなく理論に拠って立つブント系党派である以上、沈黙することはないであろう。と思っていたところ、反論らしきものが出た。わたしの解説に対する正面からの批判ではなかったが、「radical chic」(46号・以下引用は号数で記す)に、「早川礼二」の筆名で「『情況休刊号』のコラムを読む」という文章が公表されたのだった。その意気やよし。
まず笑わせてもらったのは、本文15頁・1万8000字にわたる「特集解説」(二部構成で、目次付き)を、「コラム」と称していることだ。解説の筆者も「文責・編集部横山茂彦、編集協力・岩田吾郎」と明記しているにもかかわらず、早川は「コラム筆者」としているのだ。
つまり、自分たちが全面的な批判にさらされたのを何とか覆い隠し、コラムで扱われた程度のことにしたい、のであろう。その心情には、こころから同情する。
だが、論文作法としては、他者の記事や論文を引用するのであれば、タイトルと筆者を明記しなければならない。これをしないので困るのは、読者が容易に出典を引けないからだ。早川が雑誌情況の「コラム」と一般名称にしてしまっているので、読者は『情況』の30本前後ある記事の中からタイトルをもとには探し出せない。そもそも当該の論攷は「解説」であって、いわば雑誌の論説記事である。コラム(囲み記事)ではないのだ。原稿用紙換算45枚、大仰な目次まで付いたコラムなど、どこの雑誌にあるというのだろうか。まぁでも、これはどうでもいいだろう。
問題なのは、批判する相手の論旨を「改ざん」していることだ。他者の文章を引用する場合は、それが部分的なものであっても、絶対に論旨を改ざんしてはならない。これは論文だけでなく、文章を書く上での大原則である。
論旨の改ざんは論点をずらし、議論を成り立たなくする。それはもはや議論ではなく、論争をスポイルする不正な作為である。
蛇足ながら、他者を批判するときに、論証をともなわない批判は、単なる誹謗中傷となる。素人の文章にありがちな傾向である。
それでは、早川礼二による「特集解説」の論旨改ざん、みずからの文章の改ざんを具体的に見てゆこう。
◆核になるフレーズの削除で、180度逆の結論に
早川礼二は云う。
「コラム筆者は『米軍が直接参戦していない以上、首都圏委の言う「帝間戦争論」は成り立たない』とし、『反帝民族解放闘争の独自性を承認するのは、国際共産主義者の基本的責務である』と批判する」
「第一の疑問は、コラム筆者がウクライナ戦争で米軍が果たしている役割については触れようとしないことだ。米帝・NATOによるロシア封じ込め、米帝と結託したゼレンスキー政権の軍事的挑発に触れることが『プーチンの開戦責任を免罪することになる』という。」
早川の愕くべき論旨改ざんは「米帝が直接参戦していない以上」の前にある、わたしのフレーズ「ゼレンスキー政権が米帝の傀儡でなければ」を意識的に削ったことだ。このことで、わたしの主張の結論は180度ちがってくる。
首都圏委を批判するわたしの問いの冒頭は「それでは問うが、この戦争が帝国主義間戦争であれば、ゼレンスキー政権は米帝の傀儡政権・買弁ブルジョアジーとして、打倒対象になるのではないか?」なのである。
つまりここからは、ゼレンスキー政権が傀儡政権であれば、帝国主義間戦争は成立する、という結論がみちびかれる。それが誤った認識であれ、論としてはいちおう成立する。早川は論旨の改ざんに手を染めることで、みごとに180度違う結論を偽造したのだ。
わたしは帝国主義間戦争論が成り立たないと批判しているのではなく、ゼレンスキー政権の階級的な性格を明らかにせよ、傀儡政権として打倒対象なのか否か、と指摘していたのだ。
早川はこの質問には答えられないまま、「ロシア帝国主義による明らかな侵略戦争」であることを前面に主張しつつも、「かつ米帝・NATOによる帝国主義間戦争」だと、さらに言いつのる。くり返すが、ゼレンスキー政権が米帝・NATOの傀儡でなければ、代理戦争としての帝国主義間戦争論が成立しないのは言うまでもない。
いっぽうで「ロシアの侵略戦争」ならばなぜ、ウクライナ人民の救国戦争(民族解放闘争)を評価できないのか。「この戦争の基本性格はウクライナを舞台とした欧米とロシアによる帝国主義間戦争」(44号)としていた早川は、ウクライナ人民の救国戦争への連帯には、けっして心がおよばないのである。
およそ革命党派のしめすべき指針は、打倒対象と連帯するべき味方を明確にすることだ。ゼレンスキー政権を支持するウクライナ人民、ロシア帝国主義の侵略と戦うウクライナ人民への連帯を承認・支持できないがゆえに、早川の帝間戦争論は砂上の楼閣のごとく崩壊するのだ。
いま、全世界でウクライナ避難民が抗露戦争への支援を訴え、あるいはロシア連邦からの政治難民(ブリヤート人など)が「プーチンストップ!」を訴えている。抽象的な「世界の被抑圧人民・プロレタリアートと連帯」(46号・早川)などという抽象的な空スローガンではなく、具体的な指針を示すべきなのだ。現にロシア帝国主義と戦っているウクライナ人民との連帯、かれら彼女らがもとめる軍事をふくむ支援なのだと。
「あらゆる〈戦争国家〉に反対する」(44号・早川)も市民運動の理念としてはいいだろう。だが、首都圏委は革命党派なのである。そもそも民族解放戦争の大義、社会主義革命戦争の大義を語れなくなった党派に、共産主義者同盟の名を語る資格があるのか。この党史をめぐる議論に乗って来れない首都圏委には、稿をあらためてブント史論争として、議論のステージを準備したいものだ。
◆論旨の改ざんは、論争の回避である
さて、上記の引用中で早川は、もうひとつ大きな改ざんを行なっている。
「(横山の主張は=引用者注)ゼレンスキー政権の軍事的挑発に触れることが『プーチンの開戦責任を免罪することになる』という」(46号・早川)。
「触れる」? そうではなかったはずだ。44号論文から再度引用しよう。
「米帝・NATOの東方拡大によるロシアの軍事的封じ込め政策、多額の軍事支援とテコ入れにより二〇一五年の『ミンスク合意』を無視してウクライナ東部のロシア系居住区域への軍事的圧迫と攻勢を強めたゼレンスキー政権の強硬策がロシアを挑発し、今日の事態を招いた直接的な原因」だと。
ハッキリと、ゼレンスキー政権の強硬策が「直接的な原因」だと述べているではないか。「要因(factor)」などではなく「直接的な原因(direct cause)」だ。
「直接的な原因」とした以上、プーチンのウクライナ侵攻は「結果」にすぎないことになる。これが「プーチンの開戦責任の免罪」でなくて何なのか。
開戦の責任をプーチンにではなく、ゼレンスキーにもとめていた早川は、「直接的な原因」を「触れる」と言い換えることで、自分の論旨を改ざんしたのだ。
まともに論争をしようと思えば、自分の前言撤回も厭うべきではない。そこに相互批判による議論の深化があるからだ。論軸をずらさずに、誠実に議論することで新しい理論的地平も切り拓けるのだ。今回の早川の改ざんは、論争を回避する恥ずべき行為だと指摘しておこう。
◆太平洋戦争の原因は「ABCD包囲網」か?
かつて日本帝国主義は、中国戦争における援蒋ルート(蒋介石政権への欧米の支援=4ルート)を封じるために、フランスが宗主国だったインドシナに進駐した(仏印進駐・1940~1941年)。これに対して、アメリカ・イギリス・オランダが政治経済にわたる包囲網を敷いたのだった。この三国と中国をあわせて、日本に対するABCD包囲陣と呼ばれたものだ。
とりわけアメリカの対日石油禁輸が、日本経済を苦しめた。追いつめられた日本は、真珠湾攻撃をもって開戦に踏み切ったのである。これを歴史修正主義者は「アメリカが日本を戦争に追い込んだ」とする。まさに共産同首都圏委の主張(米帝・ゼレンスキー原因論)は、旧日本帝国主義を弁護するネトウヨなど、歴史修正主義者のものと同じ論理構成だと言えるだろう。
だが、ABCD包囲網をつくり出したのは、ほかならぬ日本帝国主義の中国侵略、傀儡国家(満州国)の建国にある。ウクライナにおいても、ロシアによる2014年のクリミア併合以降、欧米のウクライナ支援ロシア包囲陣が生じたのは、ほとんど日中戦争と同じ政治構造である。
1994年のブタペスト合意でのウクライナの核放棄(世界で三番目の核保有国だった)、ロシア・アメリカ・イギリスをふくむ周辺諸国の安全保障が、もっぱらロシアによって反故にされたこと。すなわち、兵士に肩章をはずさせたロシア軍による、クリミア・ドンバスへの軍事的圧迫が、ウクライナ人民をして、マイダン革命をはじめとする反ロシア運動の爆発となって顕われ、欧米の支援が「東方拡大」のひとつとして顕在化したのである。ロシアによるクリミア併合・東部・南部諸州併合は、日帝の満州国建国と比して認識されるべきものだ。
このような流れの中では、首都圏委が金科玉条のごとく持ち出す「ミンスク合意」(二次にわたる)は、ロシア軍が介入した内戦停止のための休戦協定にすぎないのである。何度ミンスク合意がくり返されても、ロシア帝国主義のウクライナ侵略は終わらない。なぜならば、ロシアはウクライナそのものを併合・併呑しようとしているからだ(プーチン演説)。
◆改ざんだけでなく、誤記満載の「反論」
共産同首都圏委員会は、わたしへの「反論」の中で、いくつかの論点を新たに提示している。ひとつは、わたしが主張した反帝民族解放闘争への疑義である。
中井和夫(ウクライナ史)の『ウクライナ・ナショナリズム』(版元は岩波書店ではなく東京大学出版会)から引用して、民族自決への疑問をこう呈している。
「中井も『国家の急増』が国際社会に与えてきている負荷・コストの大きさ」に触れ「民族自決」を「民族自治」にかえていくことと「他(ママ→多)民族の平和的統合の政治システムとしての連邦制の可能性」を論じている。(46号・早川)
そうではない。この「民族自治」と「連邦制」こそが、ソ連邦時代の「民族の牢獄」を形づくってきたものなのだ。中井和夫がいみじくも「帝国の復活を現代考えることは無理である」とする前提を見落として、早川が「民族自治」に着目することこそ、プーチンの帝国のもとにウクライナ人民をはじめとする諸民族を封じ込める発想。すなわち民族解放闘争の否定にほかならない。
レーニンの「分離の自由をふくむ連邦」を継承しながらも、スターリン憲法およびそれを継承したロシア連邦憲法は、分離の手続きの不備によって、事実上独立をゆるさずに、諸民族の自治に封じ込めてきたのだ。プーチンのクリミア併合以降は、領土割譲禁止条項によって、分離そのものが違法となったではないか。
ソ連邦の崩壊後のなだれ打った旧ソ連邦内国家の独立は、米・NATOの東方拡大だけではなく、東欧人民の反ロシア革命(民族独立革命および人民民主主義革命)だった。首都圏委が暗に主張する帝国主義の陰謀ではなく、これが人民による民族自決の体現にほかならない。
その反ロシア革命の動因は、膨大なエネルギー資源をもとにした軍事大国による圧迫への抵抗であり、世界最大の核兵器保有国による覇権支配への人民の恐怖と大衆的反発である。つまりロシアの帝国主義支配への民族的な抵抗なのである。したがって、21世紀のいまも帝国主義と民族植民地問題として、20世紀型の戦争と革命が継続しているといえよう。いや、プーチンにおいては18世紀型の帝国なのである。
70年代なかばのベトナム・インドシナ三国の反帝民族解放戦争の勝利、社会主義革命戦争とウクライナ戦争を比較して、早川は自信のなさそうな書き方でこう提起する。
「端的に言って、米ソ冷戦体制の下、帝国主義の植民地支配からの独立をめざしたベトナム人民の民族解放闘争と、グローバル資本主義が全世界を蓋い(ママ)、〈戦争機械〉と結託した帝国主義諸国の利害が複雑に絡み合いつつ、国境を越えて介入し他国の支配階級と結びついて暗躍し、権益拡大のために他国を容赦なく戦場化する時代のウクライナ戦争を、同列に論じることはできないのではないか。」(46号・早川)。
長いセンテンスで現代世界の複雑さを強調したからといって、何ら説得力があるというものではない。ベトナム戦争とウクライナ戦争の違いを、早川は上記の文章以上に論証することができないはずだ。
なぜならば、ベトナム・インドシナにおけるフランスの植民地支配、のちにはアメリカの介入を、現在のウクライナ戦争におけるロシアに置き換えれば、まったく同じ政治構造だからだ。ソ連のアフガニスタン侵攻、アメリカのイラク侵攻もまったく同じ、帝国主義の覇権主義的侵略戦争である。
第一次大戦以降、列強の利害は複雑に絡み合い、第二次大戦以降も、そして現在も、米ロをはじめとする帝国主義は「国境を越えて介入し他国の支配階級と結びついて暗躍し、権益拡大のために他国を容赦なく戦場化」(早川)しているのではないのか。
そして帝国主義の侵略が、ほかならぬ人民大衆の闘いと民族自決の奔流に強要された、悪あがきであることに着目できないからこそ、早川は現代世界の複雑さだけを、論証抜きで強調したくなるのだ。そこには大衆叛乱への信頼や共感は、ひとかけらもない。
それにしても、上記の引用における誤記・版元の誤り(別掲文献の版元名も間違えている)をみると、早川の論旨改ざんは意識的なものではなく、文章そのものを正確に判読できていない可能性もある。首都圏委においては、この頼りない主筆に代わり、組織的な討議を経た文章で、改ざんの釈明および誤記・版元間違いを訂正してもらいたものだ。
◆ウクライナ戦争はロシアの敗北でしか決着しない
いま求められている戦争の停止、もしくは終了がどのように展望できるのか。降伏の勧めや無防備都市の提案は、そのままロシアへの隷属・大量処刑を意味する。だが現実的ではないにせよ、すくなくとも具体的である。
もっとも具体的なのは、ゼレンスキー政権とウクライナ人民が、侵略者ロシアを国境の外に追い払うことである。いまそれは、第三次大戦の危機をはらみながらも、実現に向かっている。
ところが、あらゆる〈戦争国家〉に反対し、ゼレンスキー政権と闘うウクライナ人民(どこにいるのか?)に連帯するべきだと、首都圏委は呼び掛けるのだ。
ロシアの侵略に反対し、米帝・NATO・ゼレンスキー政権の戦争政策に反対する、世界プロレタリアートと連帯せよという。このきわめて原則的な反戦運動の呼びかけはしかし、現実に有効な階級闘争ではない。かれらの頭の中に創造された、死んだ抽象にすぎないからだ。
そして、現実のウクライナ戦争をになっている人民を無視するばかりか、ウクライナ人民の戦争支援の要求(兵器の供給)に反対しているのだ。このままでは、プーチンの侵略戦争の代弁者となり、ウクライナ人民の反帝救国戦争の敵対物に転落するしかないと指摘しておこう。
なお、1月創刊の『情況』第6期においても、ウクライナ戦争論争を他の論者を招いて掲載する予定である。われわれの「解説」の評価(賛意)や、早川礼二の民族解放闘争への不理解を指摘する声も上がっている。乞うご期待。(了)
◎『情況』第5期終刊と鹿砦社への謝辞 ── 第6期創刊にご期待ください
〈前編〉http://www.rokusaisha.com/wp/?p=44351
〈後編〉http://www.rokusaisha.com/wp/?p=44456
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。