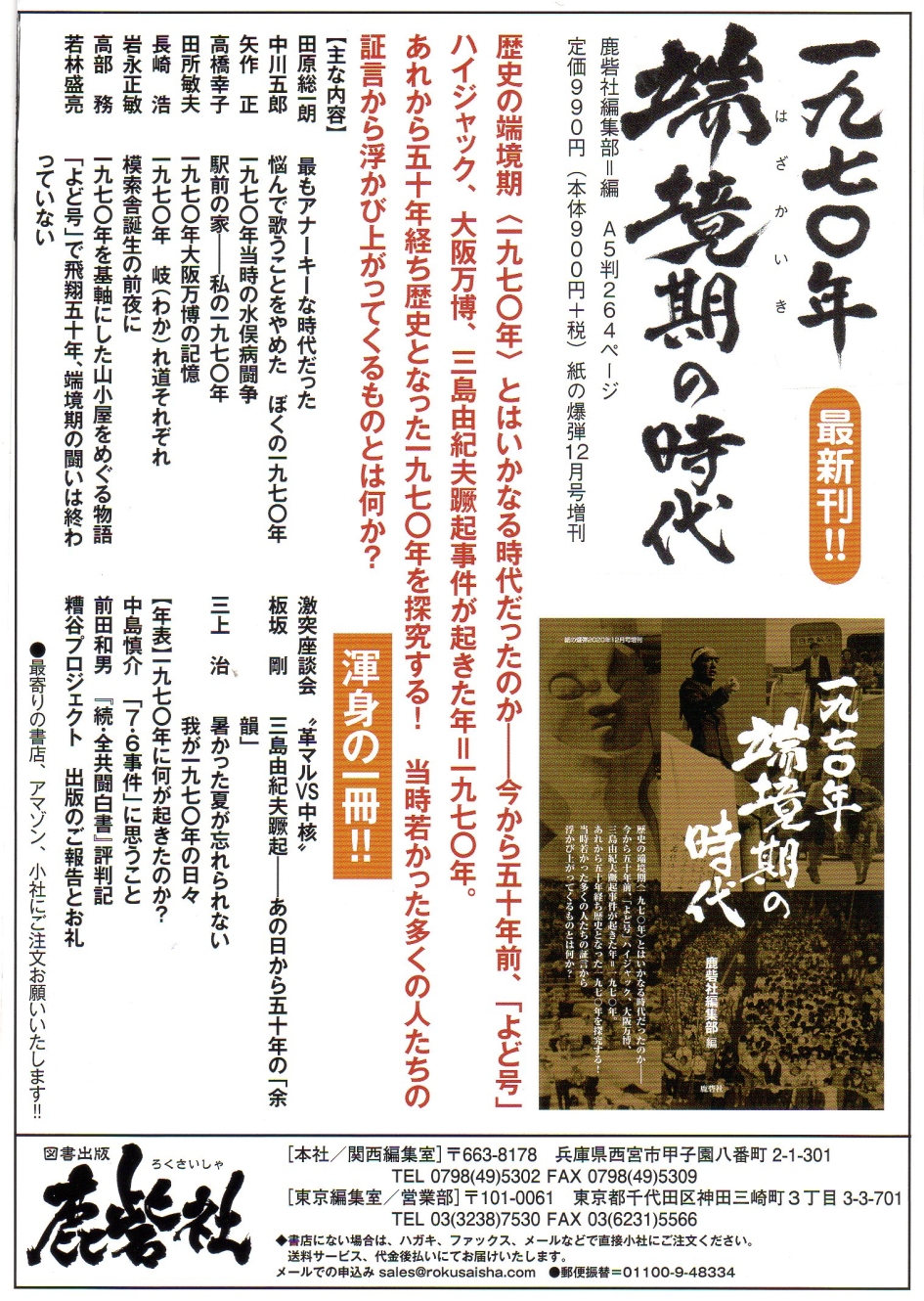わたしが編集長を務めていた雑誌『情況』が休刊しました。この場をかりて、読者の皆様のご支援に感謝いたします。同時に、広告スポンサー(表3定期広告)として支援いただいた鹿砦社、および松岡利康社長のご厚情に感謝するものです。ありがとうございました。こころざしの一端を等しくする鹿砦社のご支援は、いつも勇気を与えてくれる心の支えでした。

なお、情況誌第6期が若い編集者を中心に準備されています。時期はまだ未定ですが、近い将来に新しいコンセプトを背負った第6期創刊が達成されるものと熱望しています。そのさいは、変わらぬご支援をお願いいたします。
さて、総合雑誌の冬の時代といわれて久しい、紙媒体構造不況の昨今。しかし専門的雑誌は、いまも書店の棚を飾っています。
ということは、21世紀の読者がもとめているのが総合雑誌ではなく、シングルイッシュー(個別課題的)に細分化されたニーズであるのだと思われます。
その意味では、ロシア革命100年、68年特集、連合赤軍特集といった、社会運動に特化した特集が好評を博し、このかんの情況誌も増刷という栄誉に預ったものです(増刷による在庫過多という経営的な判断は別としても)。
いっぽう、情況誌(というよりも左派系紙媒体)に思いを寄せてくれる研究者や論者、たとえば五木寛之さんなども「少部数でも、クオリティ雑誌をめざすという手があるのではないですか」と、ご助言くださったものです。
クオリティ雑誌といえば、高級商品の広告を背景にしたお金持ち相手の趣味系の雑誌や男性ファッション誌などしか思い浮かべられませんが、フランスの新聞でいえば「リベラシオン」(大衆左派系雑誌)に対する「ルモンド」のイメージでしょうか。人文系では岩波の「思想」や「現代思想」「ユリイカ」(青土社)あたりが情況誌の競合誌となりますが、学術雑誌(紀要)よりもオピニオン誌系をめざしてきた者にとっては、やはり左右の言論を縦断した論壇ステージに固執したくなるものです。
新しい編集部がどんなものを目指すのか、われわれ旧編集部は決定には口を出さず、アドバイスも控え目に、しかし助力は惜しまないという構えです。
さて、結局いろいろと模索してきた中で、新左翼運動の総括や政治革命、戦争への左派の態度など、おのずと情況誌にもとめられるものがあります。ちょうど50年を迎える「早稲田解放闘争」「川口君事件」つまり内ゲバ問題なども、他誌では扱えない困難なテーマで、本来ならこの時期に編集作業に入っていてもおかしくないはずでした。このあたりは、残された宿題として若い人を主体に考えていきたいものです。
もうひとつ、第5期の終刊にあたって心残りなのは、ウクライナ戦争です。いよいよロシアが占領地を併合し、侵略の「目的」を達しようとしている情勢の中で、早期終結を提言するべきだが、ウクライナ人民にとっては、停戦は「緊急避難」(ミンスク合意の焼き直し)にすぎないはずです。その意味ではロシアが併合を「勝利」として、停戦に応じたからからといって、プーチンの戦争犯罪が許されるわけではない。
また、ウクライナ戦争は台湾有事のひな型でもあり、日本にとっても重大なテーマと言えましょう。そこで、情況誌第5期休刊号において、新左翼・反戦市民運動の混乱(大分裂=帝国主義間戦争か侵略戦争か)について、解説記事をまとめて掲載しました。その核心部分を紹介することで、本通信の読者の皆さまにも問題意識を共有いただければ幸甚です。
なお、新左翼特有の激しい批判、難解な左翼用語まじりですが、ご照覧いただければと思います。筆者敬白
◆休刊号掲載のウクライナ論争
まずは記事の抄録です。中核派批判から始まり、筆者も過去に関係のあったブント系の分派(共産同首都圏委員会)の批判につづきます。


【以下、記事の抄録】
中核派はこのように主張する。
「ウクライナ戦争は、『プーチンの戦争』でも『ロシア対ウクライナの戦争』でもなく、本質的にも実態的にも『米帝の戦争』であり、北大西洋条約機構(NATO)諸国や日帝も含む帝国主義の延命をかけた旧スターリン主義・ロシアに対する戦争であることが、ますます明らかになっている」(「前進」第3242号、5月2日「革共同の春季アピール」)と。
アメリカとNATO、そして日本までがウクライナ戦争に参戦し、ロシアに戦争を仕掛けているというのだ。事実はちがう。日本は北方開発と漁業でロシアと協商しているし、アメリカは武器支援にこそ積極的だが、軍隊を送り込んでいるわけではない。中核派は政治的な深読みである「米帝の戦争」を強調するあまり、プーチンの犯罪(開戦責任)を免罪してしまっているのだ。
中核派の「アメリカ帝国主義の戦争」を的確に批判しているのが『未来』(第342号、革共同再建協議会)である。革共同再建協議会はこう断じる。
「彼らは、今回のロシアの侵略戦争を米帝バイデンの世界戦争戦略が根本原因で、『米帝・バイデンとロシア・プーチンの代理戦争』と言い、さらには『米帝主導の戦争だ』とまで言う。そこには米帝の巨大さへの屈服はあっても、ロシア・プーチンの侵略戦争への批判は一切ない」と。
「プーチン・ロシアからの解放を求めて闘うウクライナ人民の主体を全く無視している。彼らの『代理戦争』の論理は、帝国主義とスターリン主義の争闘戦の前に、労働者階級や被抑圧民族は無力だという帝国主義と同じ立場、同じ目線であるということだ。ロシア・ウクライナ関係、ウクライナ内部にも存在する民族抑圧・分断支配に接近し、マルクスのアイルランド問題への肉迫、レーニンの『帝国主義と民族植民地問題』を導きの糸に解決していこうとする姿勢はない」と、厳しく批判する。
まがりなりにも「帝国主義間戦争」と言い切っているのは、共産同首都圏委員会である。だが米帝とゼレンスキー政権の強硬策が直接的な原因だとして、これまたプーチンの開戦責任を免罪するのだ。云うところを聴こう。
「この戦争の基本性格はウクライナを舞台とした欧米とロシアによる帝国主義間戦争であり、米帝・NATOの東方拡大によるロシアの軍事的封じ込め政策、多額の軍事支援とテコ入れにより2015年の『ミンスク合意』を無視してウクライナ東部のロシア系住民居住区域への軍事的圧迫と攻勢を強めたゼレンスキー政権の強硬策がロシアを挑発し、今日の事熊を招いた直接的な原因」(「radical chic」第44号、早川礼二)であると。
それでは問うが、この戦争が帝国主義間戦争であれば、ゼレンスキー政権は米帝の傀儡政権・買弁ブルジョアジーとして、打倒対象になるのではないのか? ベトナム・インドシナ戦争におけるグエン・バン・チュー政権、ロン・ノル政権と同じなのか。旧日本帝国主義の中国侵略戦争における、汪兆銘政権と同じなのだろうか。
「ゼレンスキー政権の民族排外主義、ブルジョア権威主義独裁に頑強に抵抗しつつ、ロシアの帝国主義的侵略に立ち向かうウクライナの人々に連帯する。ブルジョア国家と労働者人民を峻別することは我々の原則であり、自国も含めたあらゆる〈戦争国家〉に抗う労働者人民の国際連帯こそが求められている。」(前出)と云うのだから、わが首都圏委においては、戦争国家のゼレンスキー政権打倒がスローガンになるようだ。
だが今回の戦争の本質は、ロシア帝国主義の侵略戦争とウクライナの民族解放戦争である。抑圧された民族の解放闘争が民族主義的で、ときとして排外主義的になるのは、あまりにも当為ではないか。中朝人民における日帝支配の歴史的記憶が、いまだに民族排外主義的な抗日意識をもたらすのを、知らないわけではあるまい。ウクライナ人民のロシア(旧ソビエト政権)支配に対する歴史的な憤懣も同じである。
第一次大戦と第二次大戦も、帝国主義間戦争でありながら、植民地従属国(セルビア=ユーゴ・東欧諸国・フィンランド・中国・インド・東南アジア諸国など)の民族解放戦争という側面を持っていた。
それは支援国が帝国主義国(第二次大戦におけるアメリカの中国支援など)であるとかは、まったく関係がない。反帝民族解放闘争の独自性を承認・支持するのは、国際共産主義者の基本的責務である。
侵略戦争に対する民族解放・独立戦争はすなわち、プロレタリアートにとって祖国防衛戦争となる。それは侵略者に隷属することが、プロレタリアにとっては二重の隷属になるからにほかならない。だから民族ブルジョアジーとの共同闘争が、人民戦争戦術として必要とされるのだ。したがって首都圏委のように「ブルジョア国家と労働者人民を峻別する」ことは必要ないのだ。中国における抗日救国戦争(国共合作)がその典型である。
「民族生命の存亡の危機に当たって、我等は祖国の危亡を回復救助するために平和統一・団結禦侮(ぎょぶ=敵国からのあなどりを防ぐ)の基礎の上に、中国国民党と了解を得て共に国難に赴く」(中国共産党「国共合作に関する宣言」)。
わが首都圏委によれば、マイダン革命も米帝の画策ということになる。そこにはウクライナ人民が民族主義者に騙され、米帝の関与によって政変が起きたとする陰謀史観が横たわっている。世界の大衆動乱はすべて、CIAやダーク・ステートの陰謀であると──。
人間が陰謀史観に支配される理由は、自分たちには想像も出来ない事態を前にしたときに、安心できる説明を求めるからだ。自分たちの経験をこえた事態への恐怖にほかならない。シュタージの一員としてベルリンの壁崩壊に直面して以来、プーチンに憑りついた恐怖心は民衆叛乱への怖れなのである。おなじ恐怖心が首都圏委にもあるのだろうか。
オレンジ革命とマイダン革命に、国務省のヌーランドをはじめとするネオコン、NED(全米民主主義協会)などの支援や画策があったのは事実だが、数千・数万人の大衆行動が米帝の画策だけで実現するとは、およそ大衆的実力闘争を体験したことがない人の云うことだ。おそらく実力闘争で負傷したことも、逮捕・投獄された経験もないだろう。
陰謀史観をひもとけば、ジェイコブ・シフらのユダヤ資本がボルシェヴィキに資金提供したからといって、ロシア革命がユダヤ資本に画策されたと見做せないのと同じである。われわれは大衆の行動力こそ、歴史の流れを決めると考えるが、いまの首都圏委はそうではないようだ。
記事の抄録は以上です。ここからさらに、ブント(新左翼)史に引きつけて、革命の現実から出発してきた共産主義運動の軌跡、ロシアと中国を官僚制国家独占資本を経済的基礎とする覇権主義的帝国主義であると理論展開する。
ここまでボコボコに批判すれば、およそ反論は難しいであろう。この記事を読んだ市民運動家や元活動家の感想はそういうものだった。
しかし、他党派の批判など気にしない中核派(大衆運動が頼み)とちがい、ブント系(組織が脆弱なので理論だけが頼り)において、批判への沈黙は党派の死である。どんな反論をしてくるのか楽しみにしていたところ、それはもの凄いものだった。
なんと、首都圏委員会は相互の論旨を「改ざん」してきたのである。わたしの言い分を部分的に引用することで歪曲し、自分たちの主張も核心部(わたしの批判の核心部)を隠すことで、みごとに(いや、臆面もなく)論軸をずらしているのだ。つまり論文不正を行なったのである。あまりの愕きに、おもわず笑い出してしまったものだ。(愕きと爆笑の後編につづく)
▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)
編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。