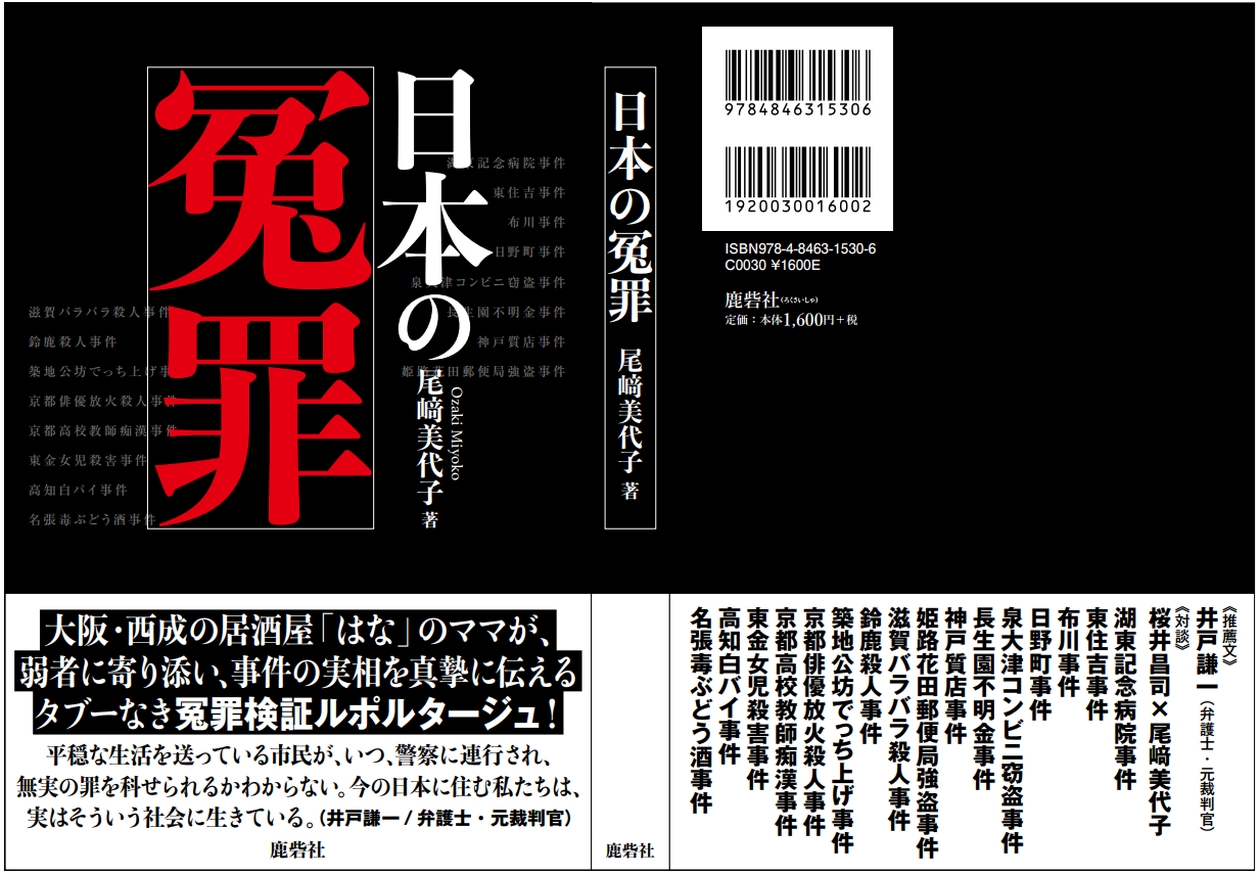昨年12月24日、大阪ピースクラブで「冤罪と司法を考える集い」が開催された。そこでの井戸謙一弁護士のお話を全4回に分けて紹介する。

◆戦前と人的な切断ができてない ── 青法協問題と日本会議
もうひとつは、戦前と人的な切断ができてないという事です、戦前の「おいコラ警察」。天皇の下、人々を弾圧していた警察官がそのまま戦後も警察の幹部になっていった。特高警察の一部は公職追放されましたけど、しばらくしたらまた戻ってきたので人的に切れてない。
そして裁判所は一切、戦争責任を取らなかった。だから戦前その天皇の名の下に裁判をして、治安維持法に基づいて人々を処罰していた裁判官がそのまま戦後も裁判官になって、中で要職に就いていく。するとそういう権力的な裁判官の発想というものが次の世代にも引き継がれていくと事が現にありました。
1970年頃、司法反動という大問題があって、ご存じの方もおられるかもしれませんが、当時その新憲法下に基づいて憲法に基づく裁判をしようという事で、がんばっていた青年法律家協会(青法協)の中に裁判官部会というのがあって約300人の裁判官がいました(協会自体は学者とか弁護士も含んでいるのですけれど)。ここに「脱会しろ」という裁判所からの圧力がかかり、民主的な裁判官が再任拒否という事で首を切られたりして大問題になりました。
これを推進したのが、石田和外(いしだ・かずと)という最高裁長官。この人は戦前からの裁判官で司法省の人事課長までやった人ですが、この人が最高裁裁判官を辞めた後に何をしたかというと、元号法制化(実現)国民会議初代議長でした。この元号法制化国民会議が、そのまま名前を変えたのが今の日本会議です(1997年に「日本を守る会」と合同し「日本会議」となった)。完全に右翼団体なんですね。ここの初代議長をしたのがその石田和外元最高裁長官なのです。こういう人が戦後の裁判所でずっと実権を握ってきて民主的な裁判官をずっと排除し、弾圧してきたという事が、今の裁判官の世界にも大きな影響を与えているという歴史的な背景があるという事も知っていただければと思います。
◆なぜ被告人の訴えが裁判官に届かないのか
では、こういう冤罪を出してしまう裁判官の責任ですけれども、もう少し分析的に考えると、なぜ被告人の訴えが裁判官に届かないのか? 検事の言い分をそのまま採用してしまうのか?
ひとつは、裁判官は両方の当事者から全く等距離で公平でなければいけないのですけれども、心理的にはどうしても検察官と近くなるという事があります。ひとつの刑事部のひとつの係の立ち合い検事は固定されているので、どの事件も同じ検事がします。だから裁判官と検事はまったく同じ人間がその係の事件を全部やる。
一方で、弁護人は事件ごとに違います。そういう意味で、検事と弁護人では、裁判官との接触の時間がまったく違う。弁護人はそうそう簡単に裁判官室に行けませんよね、裁判官室に行こうと思ったら、「裁判官と面会したい」と書記官に声をかけてから、裁判官室に迎え入れられる事もあるし、裁判官が書記官室まで出てくる事もあります。
一方、検事は多くの場合、平気で裁判官室の中へ入っていきます。毎日一緒に仕事をしているから、書記官とも顔見知りです。それだけ物理的時間的にも多くの時間を共有している。
それからやはり裁判官と検事は役割は違うけれども、協力して治安維持を担っているという意識が、刑事裁判官の中にだんだん作られてくる。裁判をすると、否認して「私はやってません」という事件は一定の割合でありますし、その多くの事件は、本当はやってるけれどもやってないという人もいる。否認事件の中でも、そういう事件が多い。
しかし、中には本当にやってない人がいるわけです。だから否認事件の中で本当にやってない事件を見極めなくてはいけないのです。けれども、多くは否認していても有罪で決着するので、裁判官は「検事が起訴した事件はまず間違いないだろう」という意識を持ってしまう。刑事裁判官の経験が長ければ長いほど、そういう意識を持ってしまう。そうすると否認している被告人がいた時に、「こいつ、本当はやってんのにやってないと言うてるだけじゃないか」と、最初から色眼鏡で見てしまうという傾向になります。(つづく)
◎[参考動画]冤罪と司法を考える集い(大国町ピースクラブ)/たぬき御膳のたぬキャス(2023.12.24)
◎井戸謙一《講演》「冤罪」はなぜ生まれるか 元裁判官の経験から
〈1〉80年代、刑事裁判の変質
〈2〉青法協問題と日本会議
〈3〉湖東記念病院事件の西山美香さんの場合
〈4〉代用監獄、弁護士立ち合い、人質司法という問題