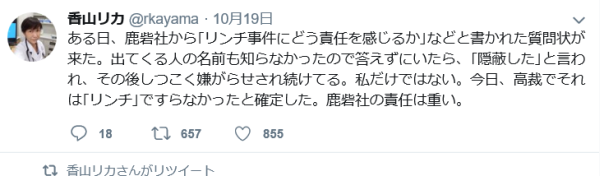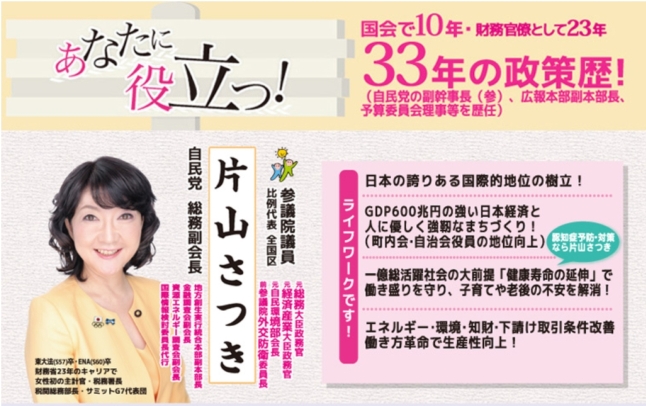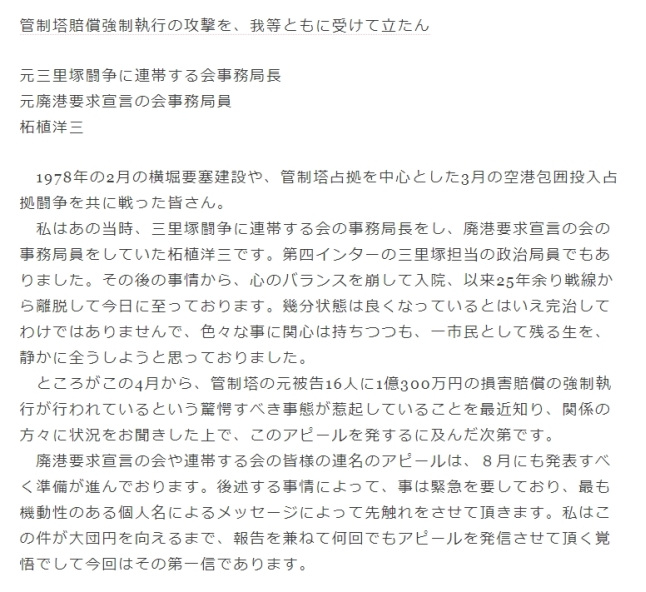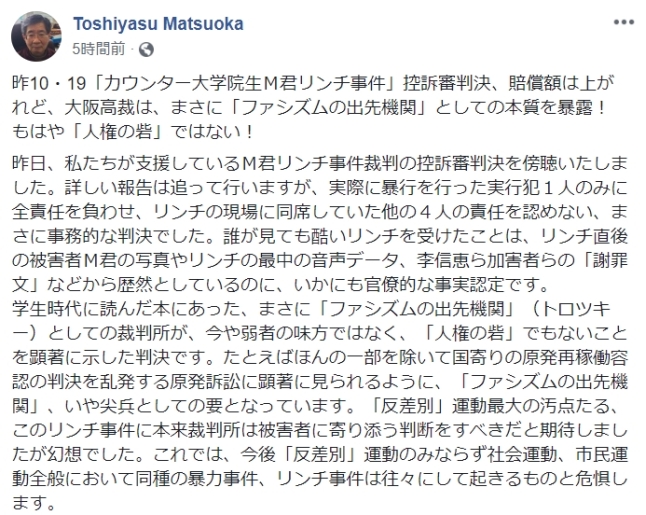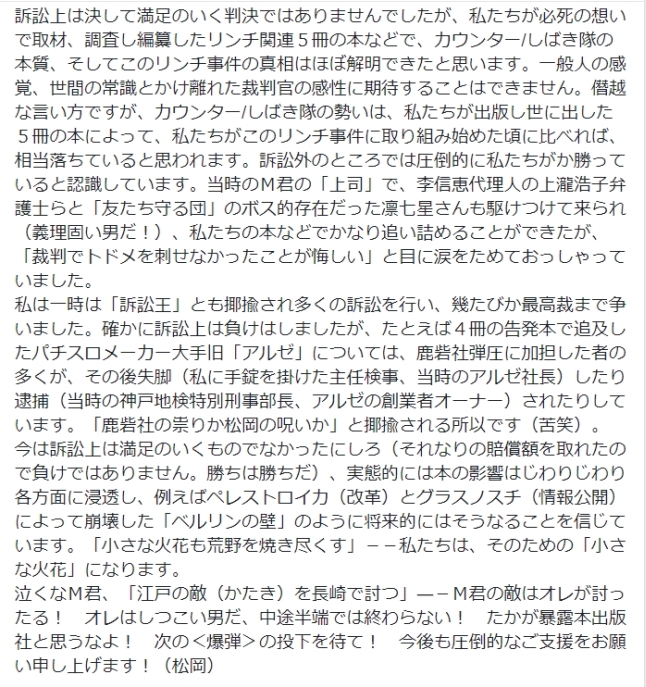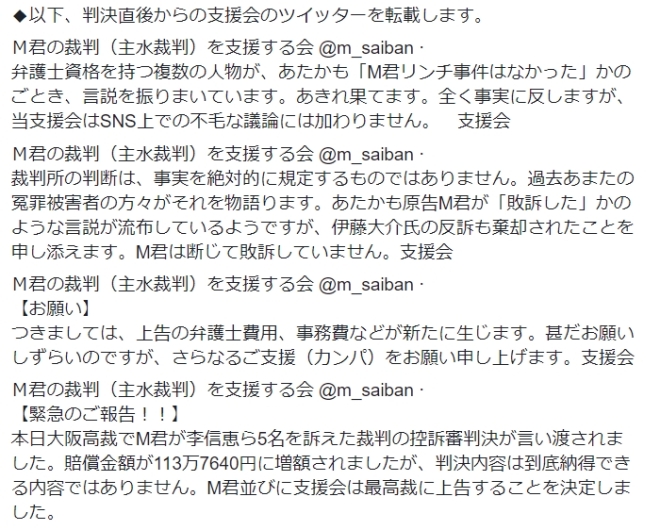平均寿命が延び、高齢の親御さんやご親戚家族の健康について、悩みを抱える方が多いのではないでしょうか。私自身、予期もせず元気で健康、快活だった母の言動に異変を感じたのは数年前のことでした。そして以降だんだんと認知症の症状が見受けられるようになりました。今も独り暮らしを続ける89歳の母、民江さん。母にまつわる様々な出来事と娘の思いを一人語りでお伝えしてゆきます。同じような困難を抱えている方々に伝わりますように。
◆一つ目の壁 お医者さんに診てもらう
一昨年、87歳だった民江さんの異変に気付いて真っ先に思ったのは、「一度専門のお医者さんに診てもらわなくちゃ」ということでした。けれども、問題はどうやって言い含めて連れて行くかです。自分がボケてるなんて全く思っていないプライドの高い民江さんをどんな言葉で説得しよう……当時私はそればかり考えていました。
かかりつけのお医者様にお願いしておいて、先生から本人に話してもらったという人の話を聞きましたが、民江さんにそんな主治医はいません。本人から「心配だから医者に連れて行ってほしい」と頼まれたという人の話も聞きました。その人は自分より母親が先に気が付いたことをとても悔やんでいらっしゃいました。もちろん民江さんにそれは望めません。かわいい孫から言わせた、そんな話も聞きました。さて、何と切り出しましょう。
少し機嫌の良さそうな日、「ねぇ、お母さん。お母さんは若い頃、めまいがして脳のCT撮ったことあったけど、最近は検査してないよね。年齢も年齢だし、一度検査してもらわない?物忘れも時々あるでしょ、それもお薬でよくなるかもしれないらしいよ。ね。」
反応を見ながらゆっくり聞いてみました。すると「そうね、なっちゃんが連れて行ってくれる?」あっさりオッケーの返事がきました。すかさず「じゃあ、伯母さんの通っていた病院に予約を入れておくね。」と言いました。病院が済んだらそのままフランス料理のお店に行き、姉と三人で久し振りのランチまでセッティングして備えていたのに、そんな鼻先に人参のような小細工は必要ありませんでした。
◆二つ目の壁 デイサービスへ行かせたい
こうして無事に認知症専門のクリニックで診ていただき、ついでにフレンチも美味しくいただき、一つ目の壁を越えることができました。今からちょうど一年半前のことです。
2か月ぐらい経った頃、次に私はデイサービスへ行かせたいと考えました。認知症の薬というのは、進行が遅くなるのに僅かでも役立てばいいという程度で、実はあまり当てにはしていません。それよりも、自由気ままに一人で過ごしていることが悪い方に作用しているのではないかと思い、人と接して話をしたり考えたりする機会を増やし、刺激を受けることが大切なのではないかと思ったからです。
以前にも何度か勧めてみましたが、その時は馬鹿にして全く聞き入れてくれませんでしたので、これをまた説得するのは私にとって高い壁です。数年前にハイキングで転倒し腰椎圧迫骨折をした時でも、せっかく頼んだヘルパーさんをたった三回で勝手に自分から断った実績があります。ヘルパーさんに対する文句ばかり聞かされたことを思い出しました。
ところが、その二つ目の壁も案外簡単に超えることができたのです。民江さん自身の口から「デイサービスに行こうかな。」と言ってきました。驚いて聞き返したことを覚えています。
理由を聞いてみると、「○○ちゃんも行ってるらしいから」と。その方は小学生の頃からの友達で元開業医、とても知的な方です。だんだん同級生が減っていく中で、たまに電話でお喋りをしたり一緒に映画に行ったりお食事をしたりできる数少ない友達のお一人でした。おかげで民江さんは自分から行ってみようという気になってくれたのです。早速ケアマネージャーさんに手配をしてもらい、お試しに行きました。するとどうでしょう、大変気に入った様子で翌週から週に三回デイサービスに行くことになり、現在は週に五回も通っています。
受診もデイサービスも私が心配していたよりも案外と壁は低かったのです。二つ目に関しては低いというより壁などなかったということでしょう。不思議な感じです。でもこれが老いというものなのかもしれません。
▼赤木 夏(あかぎ・なつ)
89歳の母を持つ地方在住の50代主婦。数年前から母親の異変に気付く